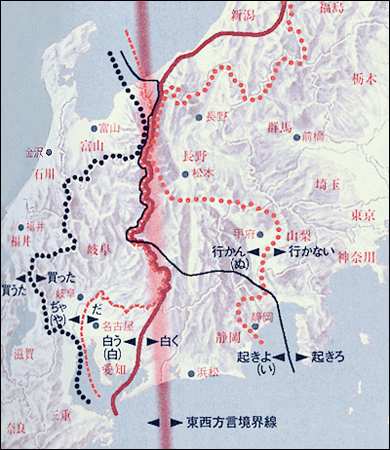
君:日本の方言は文法において著名な中部地方、それも飛騨山脈を境とした東西対立があるのだけれど、文法の要素によってその境界が中部地方内において全てが立山連峰で重なるものの、あるものは少し西に、あるものは少し東にずれているのは何故か、という事について突然に思い付いた事があるという事ね。
私:少しどころじゃない。とんでもなくズレていると主張したい。
君:その通りね。ごめんなさい。言い直すわ、明らかにずれている要素の内容だけど、★ハ行動詞のウ音便と促音便、★指定の助動詞「だ・じゃ」、★ク形容詞のウ音便の有無、★ラ行動詞命令形「よ・ろ」、★否定の助動詞「ない・ぬ」、以上の五つね。
私:ところがこの五つの線には一つの、というか強烈な共通項がある。
君:というと。立山連峰で重なっている事以外、という意味ね。
私:その通り。いきなり結論だが、交差せず、中部地方を西から東へと、南北に並んでいるという事。静岡県東部でラ行動詞命令の線と否定の助動詞の線がわずかに交差しているが、誤差範囲でしょう。線同士が重なっている部分も多いが、少なくとも交差部分は無いに等しいんじゃないか。
君:確かに言われてみればそうね。
私:これらの線は概ね自然地形と一致している。険しい飛騨山脈、人の自由な行き来を妨げる大自然、だから境界線が出来てしまったのかな、と考えていたのが昨日までの自分。成書の多くにもそのように書かれている。
君:ほほほ、線が出来たのは自然地形のせいではない、とでも言いたそうね。
私:あらら、直ぐに見破られてしまったか。その通り、これらの線が出来たのは実は自然地形のせいではないんじゃないか。
君:ほほほ、またまた、質問になっていないわよ。原因が自然でなければ、原因は人、つまりは中央、大和朝廷の影響、つまりは文化的な要因でできた線なのじゃないか、と言いたいんでしょ。
私:その通り。この五つの線は実は古代における大和朝廷の勢力範囲を示している可能性がある。ところで魏志倭人伝こそが日本が世界で初めて文献にあらわれる書、そこに記載されている大和朝廷の場所はどこ?女王・卑弥呼はどこに住んでいた?
君:九州以外の人は畿内であろうとお考えでしょうね。
私:岐阜県民の僕としては畿内・奈良か大阪平野のどこかであろうと思う。そして大和の国の勢力圏から考えられるこの五つの線の関係は?
君:関東東北に蝦夷(えみし)がいて、それは大和朝廷にとって外国、当初の大和朝廷の勢力範囲はハ行動詞のウ音便と促音便の線のあたり、これが段々と東へ勢力範囲を伸ばし、その土地土地に住む人々を日本人化、つまりは言葉を和語の文法体系に組み込み、というような形で五つの東西文法対立線が周圏論的に西から東へと並ぶように出来ていったのでは、という考えね。
私:そう、単なる考え。つまりは仮設。というか単なる思い付き。冒頭に戻るが、一時間ほど前に、ハタと思い付いた。つまりは西に位置するハ行動詞のウ音便と促音便の線が出来た年代が一番古くて、否定の助動詞の線が出来た年代が一番新しいんじゃないかな。真ん中三本は奈良時代初めあたりかな。つまりは律令制が確立し、飛騨高山に国分寺が出来たころといってもいい。あるいは征夷大将軍・坂上田村麻呂が日本人としてはじめて飛騨山脈を越え、蝦夷の国・今の長野県入りしたころの話といってもいい。彼は蝦夷に対峙するのに中央突破、つまり乗鞍超えの道を選んだ。
君:仮説は仮設、詳細な文献等の考察が無いとアウトね。
私:悔しいかな、古文書は読めない。あくまでも日本語の歴史ロマンを語っているだけ。でも、ひとつだけ気になる事がある。
君:とは。
私:日本語の音韻・音便の歴史。当サイトでも繰り返し取り上げているが、音便の歴史を簡単にひと言、イ音便、ウ音便、撥音便、促音便の順に古い。つまり一番古いのがイ音便。一番新しいのが促音便。でも、これは一般論であって、音便の歴史についても、もっと深く掘り下げてみる必要がある。「買った・買うた」の東西対立というと、なんだか江戸と難波の対立、現代語に通じる新しい時代の変化のように勘違いするかたもおみえであろうが、実はそうではない。問題はハ行動詞において東西対立がみられるという事、従って古代には「かふぃて」であった言い方が、上古の時代に畿内ではハ行転呼し「かうぃて・かうて」の音韻変化でウ音便が成立する一方で、当時、岐阜・愛知には大和朝廷の影響はなく、畿内の言葉が伝搬する前に「かふて・かって」という促音便が形成されたのでは、という事が国語学会編・国語学大辞典の音便の箇所に記載があり、なるほどと思った。
君:なあんだ。大和朝廷影響説はあなたのオリジナルじゃないのね。
私:いや、違う。国語学大辞典には東日本のハ行動詞の促音便成立は多分、相当に古いですよ、と書かれているだけ。それで僕は、東西対立は自然地形が原因ではなく、大和朝廷の勢力範囲が徐々に西から東に広がった過程と一致しているのかな、と思った。それだけの事。
君:まずは考察第一段ね。方言学の書も文献も多いでしょうから、そのような記載がないか探すことだわ。
私:勿論だよ。僕が考える様な事はどなたかが既にお書きで、それを僕が気づいていないという事かも。コツコツと資料集めだ。こりゃ楽しい人生だな。がはは
君:ライフワークというわけね。要は生まれ育ちという事なのよ。亀山の服部四郎先生も、都城の平山輝男先生も。あなたは生まれも育ちも飛騨なので、つまりは、日本の二大方言境界線、糸魚川浜名湖線と白山木曽三川線、この二つに挟み撃ちされている地域の出身だから、決してつまらない事ではない・一生をかけて調べよう、という気持ちになるのよ。ほほほ