君:そうね。女子が使う言葉ではないけれど。
私:なにいってんだい。母親がやんちゃな息子を「くらつける」という事で、力の有る者が無い者に行う行為じゃないか。
君:愛の鉄拳制裁という訳ね。語源ってあるのかしら。
私:ははは、この動詞は飛騨方言にあるが、実は全国各地に結構、方言として残っていて、つまりは古語に由来する。従って語源を考察するのは極めて容易だ。
君:「くら」の意味が問題よね。何かヒントは?
私:ヒントは複合動詞。つまりは答えを教えたも同然。
君:つまりは「くら」は動詞。しかも連用形という事なのね。
私:その通り。つまりは幾つかの音韻が脱落した結果、「くらつける」になったという事。「愛の鉄拳」もヒントだね。
君:ほほほ、わかったわ。「くら」は「食らわす」の連用形「食らわし」なのよね。
私:その通り。「食らわしつける」が「くらつける」に変化した。
君:どのような音韻変化があったのかしら。
私:冒頭に申し上げたように、「くらつける」は全国の方言になっている。従って、小学館日本方言大辞典で各地の音韻も拾う事が可能だ。まずは「わ」の脱落で「くらしつける」。この音韻が残る地方も多い。そして、続いては促音便になるんだ。つまり「くらっつける」、そして促音便も脱落して飛騨方言「くらつける」が生まれたんじゃないかな。地域名は割愛するが「くらっける、くらすける、くらいつける」等々の方言がある。
君:なるほどね。となると古語としては他サ下二「くらはす喰」で決まりね。
私:その通り。「くらはす喰」は更に品詞分解が可能だ。自ハ四(自動詞ハ行四段)「くらふ喰」の未然形「くらは」+使役の助動詞「す」という事だね。
君:そうね。使役の助動詞「す・さす・しむ」よね。皆様に簡単にご説明してね。
私:うん、それがいい。三者ともに奈良・平安の重要助動詞で、三者とも未然形に接続、「す」は四段に付き、「さす」は四段以外に付く。「しむ」は使役尊敬という事で、平安に至り盛んに尊敬語として用いられるようになった。ただし、「しむ」も上古から用いられていたが、単に使役の意味で「す・さす」と変わらなかった。ところが平安に至り和文、つまりは平安文学に用いて尊敬語の地位が確立するし、その一方、漢文の訓読文用には専ら「しむ」が用いられるようになり、「しむ」は格調高い助動詞である一方、「す・さす」は上代に変わらず普通の使役の助動詞のまま現代に至る、ってなとこだな。
君:「あが背/古語辞典総動員にて/違ひ/知らしめ給ふ/こそ/をかしけれ」、ほほほ。
私:ははは、茶化しゃあがって。くらつけたろか。
君:お願い。世界の女性を敵に回さないで。
私:読者の皆様は僕が今、必死にオチを考えてキーボードを叩いている事をご想像だろうね。ところで自ハ四「くらふ」だが、古語の時代から、あまりいい言葉ではないようだね。現代語でも「飯でも食うか」はぞんざいな言い方で、普通は「ご飯を食べる」という。
君:そもそもが上古の動詞・他ハ四(他動詞ハ行四段)「くふ食」からして、いい意味では無かったのよ。動物がエサを食う事、虫などが食い破る事とか、好ましくない行為を身に受けるとか。「一杯食わされた」として現代語に生きているわ。「たべる」の語源は他バ下二「たぶ食」から来ているけれど、「たまはる」「たばる」の謙譲語から来ている言葉だからスタートからして良い言葉、それが現代語「食べる」に引き継がれているのよ。
私:なるほどね。他マ四「はむ食」はどうかな。
君:万葉集に有名な歌があるわ。「うりはめば子供おもほゆ、くりはめばましておもほゆ・・」つまりは古代は人に用いていたけれど、中世以降はもっぱら動物・魚がエサをはむ事に用いられ、あまり良い言葉ではないわね。
私:「たべる」を使うのが無難という事だね。母親がやんちゃな息子に「親のゲンコツをたばらしめたまへ」といって、そっとなでるように子供の頭を叩くのはありかな?
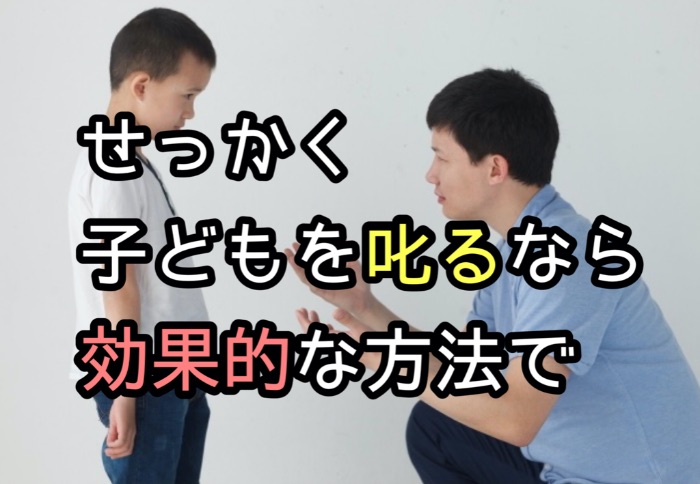
君:まなご愛子/さらば/こそ/あやまち/さとり/ぬれ。ほほほ