
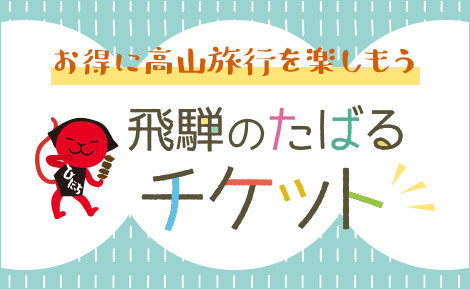
飛騨高山グリーンホテル・飛騨高山で春を探しに出かけようキャンペーン
私が三度の飯より好きなのが飛騨方言についてあれこれ調べものをする事なので、先ほどは、飛騨のたばる箱、という言葉を発見して、思わずにんまりでした。たばる、は下一段動詞・食べる、を五段活用し、可能表現に用いる表現ですが、このテーマについては最近、あれこれ調査を始めたばかりで、これってもしかしてギア方言(岐阜・愛知に共通する方言という意味の立派な学術語)でしょうかね。と申しますのも、生まれも育ちも名古屋の私の家内に、おぼわる、という言葉を投げかけたら立派に通じてしまいました。おぼわる、は飛騨方言で、覚えることができる、という意味です。おぼわる、は東京では通じません。
中部地法の方言の学術書で飛騨方言の飛騨方言の下一段動詞の五段化可能表現で必ず引き合いに出される言葉は、★たばる(=食べる事が出来る)、★掛かる(=掛ける事が出来る)、★植わる(=植える事が出来る)、★おぼわる(前述)、など数個の動詞程度でしょう。但し、たばる、は飛騨の俚諺動詞の可能性が高く、高山グリーンホテル様は、この点を最大限にアピールして方言を持したチケットを販売なさっているのでしょう。蛇足ながら。同サイトの右上で、たばるとは、というアイコンで、とっておきにする事、との説明にがありますが、少し首をかしげています。尤も、たばっておく、という飛騨俚言動詞があり、貯めておく、と言う意味です。つまり、たばっておく、という意味で、たばる、をお使いになったという事のようです。
本日のもうひとつのテーマは ネットの無料の辞書 weblio辞書です。キーワードは下一段活用で(ここ)、ア行下一段活用から最下段のラ行一段活用まで、ずらっとおそらくは数百種類の動詞が出て来ますので、おそらくは広辞苑などを網羅していると考えられ、日本語研究の好材料だと思います。暇に任せて、ア行から順番に五段活用させて可能表現になるか内省(自分でブツブツ言いながら飛騨方言のセンスに合っているかいないか脳内思考実験する事)してみましたが、途中で頭がチンチンになってしまい、なにがなんだか分からなくなりました。内省の悲しい点、学問としては使えないような感じですかね。他方の古典文法では下一段動詞は、蹴る、の一語のみ。現代口語文法では数百とも、無数の下一段動詞があるのに。生徒が疑問に思うのも当然、これに対して明確に答えられれる国語教員こそが正に国語教員の鏡、というわけです。
蛇足ながら、高校三年間で赤尾の豆単約一万語を暗記しましたが、医学部に進学しもっとひどい目にあってしまいました。解剖学の酒井恒教授が鬼教官で解剖学用語集という書物があってラテン語で約九千個の身体部分の語彙があるのですが、これを完全暗記し正しく綴らねば単位はやらぬ、とおっしゃるのです。解剖学は八か月の講義です。毎日、必死に覚えました。なんとかその甲斐あって試験は一回で合格、成績上位十人のひとりでした。尤もラテン語は医学英語の基礎ですから必須の素養とも言えます。座右の書ドーランド医学英英辞典には約20万語の語彙ですが、ほぼ全ての単語が理解できます。ラテン語の素養のおかげです。恩師酒井先生に感謝する毎日です。下一段動詞の数が数百といっても大した数ではありません。
そもそもが、これらの下一段動詞の五段化作業で、ふと気づかされる事は、例えば上述の動詞かかる、は、他動詞かける、に対して自動詞の意味、つまりは服が鴨居にかかる、というような文例の如く、もはや可能の意味は無いといってよいでしょう。おぼわる、という方言の表現にしても、名古屋方言が自然におぼわる、という使い方も可能で、むしろ名古屋方言ないしギア方言の自動詞といってもよいでしょうね。