君:サイトを訪問すると必ず新情報、という作戦ね。
私:継続は力なり。日々の進歩はわずかだが、少しずつ方言学の全体像がみえつつある。という事でいつもの画像。
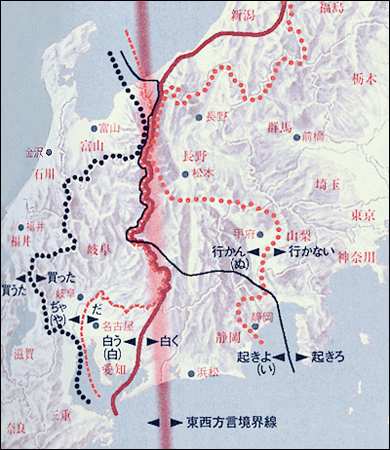
君:今日の主題はどういう内容?
私:五本の境界線の持つ意味について。★ハ行動詞のウ音便と促音便、★指定の助動詞「だ・じゃ」、★ク形容詞のウ音便の有無、★ラ行動詞命令形「よ・ろ」、★否定の助動詞「ない・ぬ」、以上の五つの線だが、実はたったひとつの意味がある。
君:用言という事ね。
私:その通り。完全正解だ。方言文末詞と言い換えてもいい。もうひとつ、この五本の境界線には強烈な共通項がある。
君:ヒントを言わなきゃ。
私:分布パターン。これを言ってしまうと答えを教えたも同然。
君:なるほど。日本を東西に二つに分ける、という共通項があるわね。しかもそれは一本の線であるという事。あるいは日本海のある村から太平洋のある村に至る一本の線。
私:そうなんだよ。数学的に記載しよう。以上の五つの線は、一つの面において二つの事象が碁やオセロの白黒陣地図と同じで、つまりは相補分布している、という最も簡単なパターンなんだ。つまりはこの五つの線は西側と東側を綺麗に二分する境界という事。しかも★ラ行動詞命令形「よ・ろ」、★否定の助動詞「ない・ぬ」は少し交差しているが、★ハ行動詞のウ音便と促音便、★指定の助動詞「だ・じゃ」、★ク形容詞のウ音便の有無、以上の三つの線は交差すらしないんだ。不思議だな、と思わないかい。
君:ほぼ自然地形に沿っているようだし、あまり疑問には思わないわ。
私:まあいいだろう。総論だから細かい事をいっても始まらない。そもそもが東西対立が生じたのは日本には都が二つあった事によるが、この五本の線は日本語の歴史を物語っている。僕にそう言われて何か気づく事は無いかい?
君:歴史と言えば、小学生でも知っている事、つまりは平安時代の京都と江戸時代の東京という事ね。ははあ、わかったわ。
私:そう。★ハ行動詞のウ音便と促音便、★指定の助動詞「だ・じゃ」、★ク形容詞のウ音便の有無、の三本は中世あたりに出来た日本語の対立で中部地方内でも西側に有り、★ラ行動詞命令形「よ・ろ」、★否定の助動詞「ない・ぬ」は近世あたりに出来た対立で中部地方内でも東側に有るどころか関東にはみ出てそうだ。つまりは中世の対立は西側、つまりは京都側にあり、近世の対立は東側、つまりは東京側にあるんだよ。これは決して偶然ではない。どこの本にも書かれていないんじゃないかな。
君:なるほど、古い対立の線は京都に近く、新しい対立の線は東京に近いのね。必然そのものだわ。よく気づいたわね。
私:お世辞でもうれしい。有難う。何も付け足す事は無い。君の心に乾杯。言いかえれば中部地方、特に愛知・静岡の両県は中世語と近世語の対立が同居しているという事。言い換えれば京都の影響と東京の影響をお行儀よく半々ずつ受けている。その一方、飛騨方言に関しては中世語と近世語の対立が存在しない地方だ。つまりは飛騨方言は純粋な中世語に近い、つまりは畿内文法に近いというわけだ。
君:ではおしまい。
私:先ほどは相補分布という言葉を紹介した。それだけでは勿体ない。方言分布には栁田國男の方言周圏論、服部四郎の基層説、基層理論(substratum theory)が有名。
君:ひと言で説明お願いね。
私:方言周圏論は池の真ん中に石を投げると丸い波が広がるのと同じ理屈で、都の言葉がじわりじわりと周囲に広がるという説。基層理論は周圏論を部分的に捉えたもので、言葉には時代に共通して伝搬する方向がある事を説いたもの。
君:なるほど。東西対立は周圏論的解釈としては京の都と江戸、この二つの中心から同心円状に文法が各地に伝番した結果と捉えられるわね。
私:純粋に畿内文法の地方では、その地方に於いて基層理論が当てはまるのだし、坂東方言の地方にしても然り。
君:中部地方は二つの異なる発信源からの波が複雑に入り混じった地方という意味になるわね。
私:飛騨方言の成立機序としては律令制の時代、数世紀に渡って続いた飛騨工という人頭税制度、各村々から一人一年の短期赴任、延べ総動員数数万人、が利いていると思う。つまり、奈良と京都の波が直接届いたって事。
君:江戸時代に飛騨は天領だったけれど、江戸の波は飛騨には届かなかったようね。
私:そのようだね。近代語及び現代語の時代に至って、東京の大波が飛騨に到達した、って事だ。
君:東京が首都である限り、東京語が全国を席巻し続けるのよね。飛騨方言なら任せとけ、頑張れジモティ左七。東京語に負けるな。ほほほ