君:今日は何のお話かしら。
私:前回にお話しした相補分布について。その前にいつもの図をご覧いただこう。
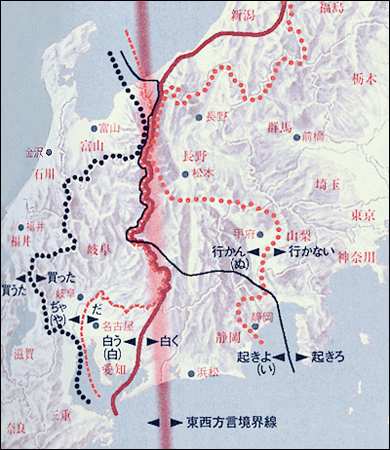
君:相補分布の定義とは囲碁やオセロの白黒陣地図の事ね。一つの面に二つの相反する要素しかなく、然も全ての面がどちらか一つの要素によって埋め尽くされている事。
私:その通り。より厳密には、相補分布(complementary distribution)とは言語学で、2つまたは3つ以上の異なる要素の間に、異なる環境で背反的に出現する関係があることをいう。多くの場合には、これらは外見上異なる要素だが、深層では同じ要素である。様々なレベルに適用できる概念であるが、特に音韻論と形態論で用いられる。
君:深層では同じ要素であるという事は、二つの言葉に共通の祖語があるという事ね。
私:その通り。男女の仲から子供が生まれるが、その逆で、一組の夫婦から二人の子供が生まれるという事。親が同じなので、二人の子供は似て当然だが、似ていなくても、よくよく見ると共通点があるというものだ。
君:では早速に五つの要素について説明お願いね。
私:ざあっと羅列的にお示ししよう。
★ハ行動詞のウ音便と促音便、買った、と、買うた、祖語はハ行動詞「かふ」だ。これの連用形の音便が分かれたお話だが、まずは「かふ」が「かふぃたり」、奈良時代だよね。対立は無い。これが西ではハ行転呼で平安に「かうぃたり」やがて「こうたり」になった。他方で東では鎌倉当たりから「かったり」になった。
★指定の助動詞「だ・じゃ」、の祖語は「であり」。つまり格助詞「で」+ラ行動詞「あり」。西では「ぢゃ」が「じゃ」、近世語以降は「や」になった。他方で東では「であり」が「でぁ」になったのが中世、そして近世には「だ」になった。
★ク形容詞のウ音便の有無、これは西側では平安辺りにウ音便になったが、他方の東では音便化せず、上古の音韻がそのままだ。
★ラ行動詞命令形「よ・ろ」、これは前述の「だ・じゃ」の逆で、西では命令形「よ」が上古から現代まで未変化なのに対し、近世語、つまり江戸っ子が突然に「ろ」と言いだしてから東西対立が生まれたパターン。でもそもそもが何故、「ろ」なのか、これはラ行上一段活用が、ついついラ行四段活用につられて、という事で決まりだな。つまりは江戸っ子のナウい言い方として始まったのだろうね。
★否定の助動詞「ない・ぬ」、これは少し手ごわいな。打消しの助動詞「ず」だか、連体形が「ぬ」、そして已然形が「ね」、然し古くは奈良時代に未然形「な」、連用形「に」があった。つまりは伝統的にナ行で活用していた。これは西の話。他方の東では、上代に打消しの助動詞「なふ」があった。容易に想像できるように「なふ」は未然形古形「な」に反復継続の助動詞「ふ」がついたもの。以上は万葉のお話。つまりはそれ以前の時代にナ行の共通祖語があったには違いないだろうが、なにせ資料がないので、萬葉集以前のお話は古代語ロマンというとりとめのないお話。
君:やはり全ての東西対立要素のそのひとつ毎に共通の祖語があったのね。
私:然も或る年代にポンと完成したのではなく、上代から近世にかけて、ざっと千年かけて生まれた東西対立という訳だ。
君:結論としては東西対立も基本文法は完全に同じ日本語であり、東西対立とは音韻の対立と心得たり、という事ね。
私:勿論。文法の対立があったとすれば、それはもう日本語ではない。東西対立とて共に日本語。つまり文法は全く同一です。
君:なるほど。
私:付け加えるに母音の調和、つまりは有坂・池上法則。日本人は皆がこの法則に従って無意識に話している。東京も大阪も。
君:ほほほ、つまりは東西対立と言っても文法は同じ、音韻が若干異なるけれど、音韻の基礎中の基礎、母音の調和は同じなので、音韻変化の要素のなかでもほんの少しが東西対立の本態という事ね。
私:正にその通りだ。もっと大切な事がある。文末詞について東西対立がある、という事。つまりは文の最後の部分だけの違いだ。
君:正にその通りじゃ。つまりは文の最後の部分だけの違いじゃ。もっと大切なポイントは文末詞についてのみ東西対立がある、という事ね。ほほほ