君:ええ、ではまず基層説ね。
私:こんな感じだ。
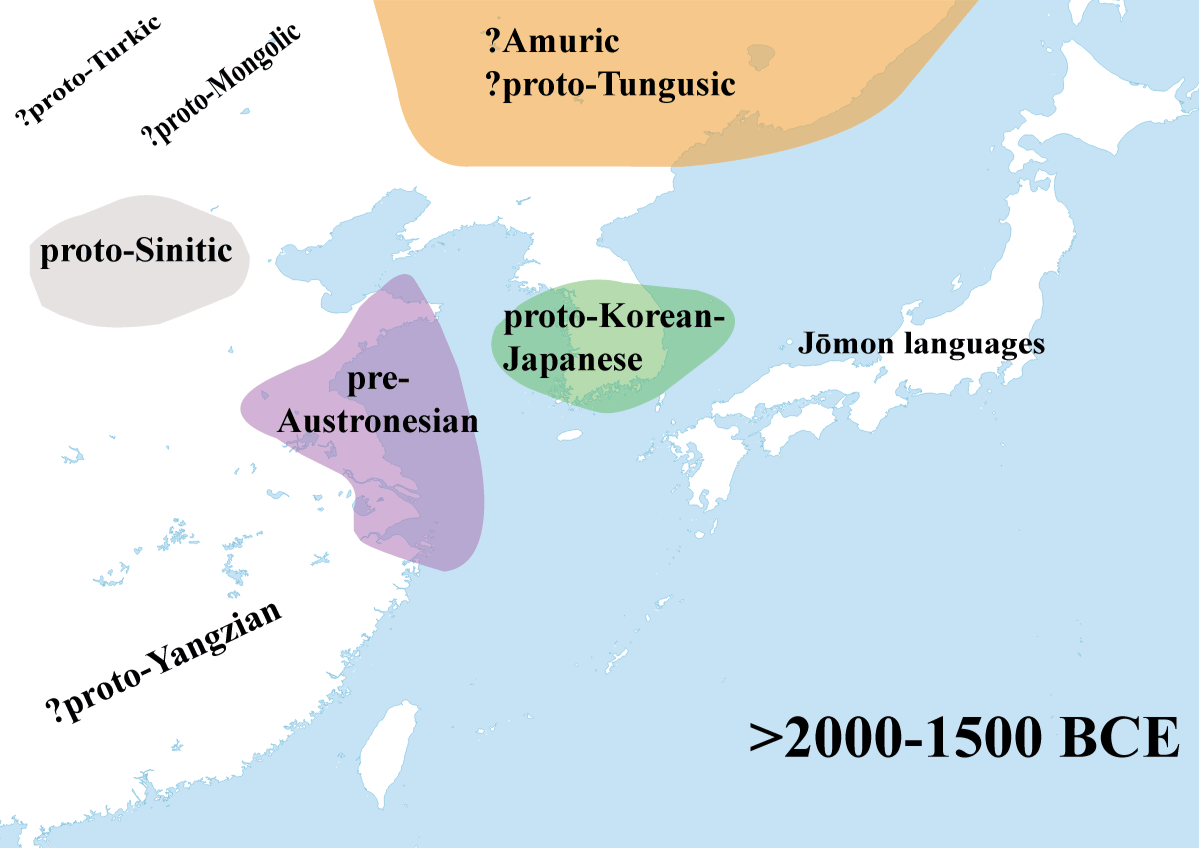
君:元々が縄文語というものがあって、大陸の方からいろんな言語が次から次へと、といっても千年単位のとてつもなく長い期間に幾つも幾つも日本列島へ押し寄せてきた、という感じね。
私:うん、まあそんなところだ。続いては方言周圏論だが、栁田國男の蝸牛考が有名すぎる話だが、それでは面白くない。松本修氏の「全国アホ・バカ分布考」資料をご覧いただこう。

君:これはまた見事なまでに京都を中心として言葉が同心円状に日本列島全体に分布しているという事ね。
私:その通り。大変にきれいな図だ。
君:相反する二つの理論という事ね。
私:そうかな?そうじゃないと思うよ。
君:えっ、どういう事?
私:両者は共に波を表している。
君:方言周圏論は波として理解できるわね。でも基層説は大陸から日本列島へ、つまりは西から東への移動だわよ。
私:波を規定するものと言えば、まずは発生源の位置、波の3要素(周波数、振幅、波形)。これを当てはめる事ができる。
君:なるほど。基層説とは実は、発生源がユーラシア大陸、周波数はとても低いという事で、つまりは日本列島だけを見ると西から東へ波が伝わっているだけ、ただしそれは見かけの現象ね。方言周圏論とは発生源は京都、周波数はとても高く、日本列島全体を眺めると言葉の伝わりを波ととらえる事は容易、言葉一個一個も明瞭に異なるものばかりなだけに波形も極めて複雑、という事ね。
私:その通り。それともうひとつ、発生源が固定される限り、どんな複雑な波形の波であっても様々な周波数と振幅の単振動に分解できる。これをフーリエ解析という。
君:そんな理論はどうでもいいから、そもそもが言葉は人から人へ伝わるものだから波に決まっているじゃないの。
私:正にその通り、言葉は波そのものだ。千年周期の波もあるし、数十年周期の波もあります、と言えばいいんだよね。
君:そう。そして発生源は二つあるのよ。ひとつはユーラシア大陸で、ここからの波はゆっくり伝わる。もうひとつは京都が発生源で、ここからの波は全国にあっという間に伝わる。外国からの波が基層説で、国内のみの波が方言周圏論ね。ほほほ