君:では早速にね。そもそもが「母音の三角形」とは?
私:母音は発声器が複雑な三次元空間を形成して出来るわけだから図式は難しい。ただし発声器は左右対称だから頭部の正中矢状断で、どのあたりが使われるかという二次元表示が可能だ。
君:そうね。
私:その二次元表示を究極化させて点と線のフレーム構造で示したのが国際音声記号(IPA)のうちの国際音声字母。
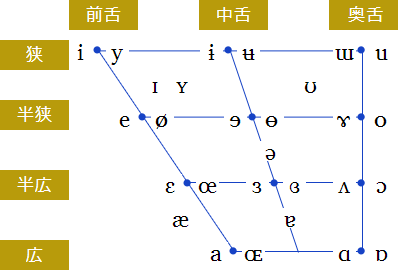
君:台形で縦横 3 x 4 = 12 の行列ね。
私:そう。まずは行、つまり横だが、読みは前舌(まえじた)、中舌(なかじた)、後舌(うしろじた)、つまりは舌の盛り上がった部分を示す。
君:となると、列、つまり縦は、狭(せま)、半狭(はんせま)、半広(はんひろ)、広(ひろ)、の読みね。意味は?
私:縦列は実は口の開きを表す開口度の表現なんだ。舌の上下の動きという意味ではない。
君:世界のあらゆる母音は畢竟、二因子(舌の盛り上がり位置、口の開き具合)、このたった二因子で表現できるとは、大胆な考え方だわよね。ところで長方形でないのは何故?
私:「い」の母音(i,j)は殊更に口の開きが大きいのでその事を示す。
君:ひとつひとつのギリシャ文字がひとつの母音という事で、世界の諸言語の母音はこの一枚の図で示されるという事ね。そしてその数は28。
私:その通りだが、日本語・東京語には「あいうえお」の五種類の母音しかない。これを示すのが母音の三角形。
イ・・・ウ
・ ・
エ オ
・・
ア
あまり、どころかとてもかっこよくない図だが、許してね。
君:まあね。気持ちだけは伝わるわよ。
私:ありがとう。「イ」は前舌狭、「ウ」は後舌狭、「エ」は前舌半狭、「オ」は後舌半広、「ア」は中舌広、だと思えば当たらずと言えども遠からず。
君:「エ」は「イ」と「ア」の中間にあると思えば当たらずと言えども遠からずなのよね。
私:その通り。そして「オ」は「ウ」と「ア」の中間にあると思えば当たらずと言えども遠からず。
君:そこで出てくるのが連母音融合。
私:そういう事。「アイ」は「エー」になり易く、「アウ」は「オー」になり易い。例えば、「高い」が「タケー」、「似合う」が「ニオー」。
君:その裏返しというか、「イウ」「ウイ」「エオ」「オエ」「イオ」「オイ」「ウエ」「エウ」は連母音にはならないのよね。
私:そう。中間の母音が無いから連母音にはならない。また逆に「イエ」「エイ」「エア」「アエ」「ウオ」「オウ」「オア」「アオ」も近すぎて連母音にはなりにくいね。
君:要は連母音は二つだけ。「アイ」が「エー」、「アウ」が「オー」。
私:そこまで簡単にしてしまっていいのか、という気持ちもあるが、一言で言えばそういう事だ。実際には名古屋市方言の母音は8個を先頭に、諸方言の母音数は違うので、細かい事を論じていれば切りがない。沖縄与那国方言は母音が「ア・イ・ウ」だから、これは流石に連母音が生ずるわけが無いね。その一方、名古屋市方言は八個の母音に足す事の十通りの連母音がある事で知られている。今日の結論だが、だもんで名古屋弁をなめてぁあかん。
君:故郷飛騨を離れて名古屋とその界隈に既に50年ね。左七君、少しは慣れましたか?
私:全然だぎゃー。あかんわ。
君:戦前のお生まれの方達の言葉よね。今じゃほとんど聞かれないのじゃないかしら。ほほほ