君:アクセントが同じだからよね。
私:その通り。飛騨方言をマスターするには語彙さえ覚えればいい。逆に、飛騨方言は語彙さえ変えれば共通語になるので、方言は簡単に矯正可能で、方言の発音で苦労する事は無いと思う。
君:表題と少し論点がずれているわよ。
私:失礼。今夜は日本語の子音について。母音の話でもよかったが、アイウエオの五個だけだからね。
君:子音だってアカサタナ・・十個ほどだわよ。
私:うん、そういうお話ではなくて、国際音声字母 IPA について。国際音声記号とも言う。
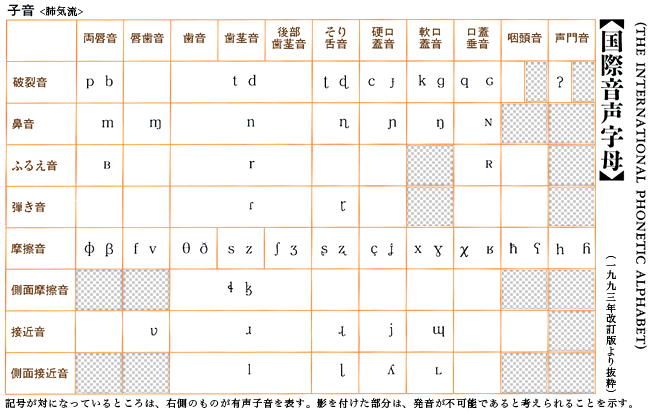
君:表の左上に子音<肺気流>と書かれているわね。なるほど、各種の子音は縦の欄と横の行の二つの要素から成るのね。
私:その通り。国際音声記号という言葉からもわかるように、全世界の言葉の子音は上記の表のどこかに含まれる、という事で日本語の子音もこの中のどこかに必ず含まれる。
君:耳慣れない言葉ばかり。横の行は8で、縦の列は11だから、理論的には2要素によって88種類に分類される子音でしょうけど、網掛けのセルが17個あるから、人類の子音は88-17=71の音声学カテゴリーというわけね。
私:その通り、ただし同じセルに複数子音がある事にも着目。さて日本語は諸外国より子音の数が圧倒的に少なく、言語の中では話しやすい部類になる。縦の列の意味、横の行の意味、分かるよね。推して知るべし。
君:縦の列には解剖学の言葉、つまりは唇・歯・歯茎・舌・軟口蓋・硬口蓋・口蓋垂・声門、が羅列されているわね。
私:そう、その通り。全て口の中のパーツだ。だから、これは子音が出る場所を示す。左から右に並ぶのも一つの法則で並べてある。
君:ほほほ、お口の入り口のパーツから順に中側へ、そして一番の奥がのどぼとけ・声門。その奥の器官は無いというわけね。
私:その通り。声門の奥・気管と気管支から声が出る事は無い。ただし食道発声という声の出し方がある。
君:聞いた事ないわ。
私:これはげっぷで作る声だ。喉頭がんのおかたは喉頭、つまりは声門あたりを全摘出する。つまりは声が出せなくなる。しかし訓練によって、息を食道に飲み込み自在にげっぷを出させる事によって声を作る事ができる。ご本人の努力とセラピストのご熱意が実を結ぶという訳。
君:なるほど、おしゃべり、って財産なのね。
私:そう、財産。ところで子音というのは肺から出る空気が狭い場所を出る時の音だから、どこの場所ととどこの場所、つまり二か所のペアで一つの音が作られる。例えば歯音だが、実際には舌先・舌端と上歯の裏の組み合わせだ。つまりは下の歯を使って発音する人類はいない。必ず舌と上の歯のペア。また、ペアの組み合わせだが、ひとつのグルーブは下唇と舌、この二つだけ。そしてもうひとつのグループは上唇・上の歯・硬口蓋・軟口蓋・口蓋垂・喉頭の六つだけ。また解剖学的に下唇は上唇か上の歯にしかくっつかないし、舌は硬口蓋・軟口蓋・喉頭、この三つのどれかひとつとしかくっつかない。
君:声門が抜けているわよ。
私:失礼。声門だけは別格。声門は左右対称の声帯から成る臓器で声帯同士しかくっつかない。
君:動くのは上下の唇、舌、軟口蓋、口蓋垂、声帯、この六つよね。他の部分、つまり骨・歯は動かない。
私:おっ、鋭いな。その通り。そしてこれら六つには強烈な共通項がある。
君:横紋筋という事かしら。
私:その通り。随意筋だ。つまりは小脳で動き方をプログラミングしている。そして小脳を動かすのが大脳皮質の運動野、運動野に働きかけるのが前頭葉。
君:そのあたりは中学生でも知っているわね。理科で習うから。
私:うん。では横の行の意味はどうだい。
君:縦の列は二つの解剖学的部分のペア、つまりは声の出る場所だけど、横の行は、その出し方、音の振動の仕方という事かしら。
私:おっ、鋭いな。
君:からかわないでよ。ふるえ、とか、弾き、とか書かれていたら、誰だってわかる事じゃない。
私:その通りだね。摩擦音と接近音はきわどい音の違いだ。わずかな隙間の音が摩擦音で、明らかな隙間の音が接近音。
君:でも、子音といえば、(ア)カサタナ、カキクケコ、の発想しかないから想像が難しいわね。第一に、考えながら発音しているわけじゃないし。
私:方言学というのは話し言葉の学問だから避けては通れない問題だが、今日は入門の話という事にしよう。以上の議論にて世界の諸言語が無数に近い組み合わせ、つまりは解剖学的にどことどこがくっつくか、そしてその振動の仕方は、という事で子音が作られるのだが、日本語の子音はごく限られたパターンしかない。具体的には、無声両唇破裂音(パ・ポ)、有声両唇破裂音(バ・ボ)、有声両鼻破裂音(マ・モ)、無声歯茎破裂音(タ・ト)、等々、10ほどのパターン。
君:でも諸外国の子供に比べ日本人の子供が言葉が早い事はないわよね。子供という人種は世界中で一、二歳の頃から片言をしゃべりはじめるわよ。
私:そう、その通り。以上が前置き、では今からが本題。赤ちゃんは驚くほど耳がいい。どんな意味かな?
君:・・。うーん、わかったわ。生まれたときから親が何を話しているか、キチンと聞き分けているけれど、ただし、何という意味か最初はわからないし、でも、そのうち、・・ははあ、こういう意味なんだな・・と気づき、親が話す言葉がまずは理解できるようになる、自分も答えて親と会話をしたいが・・うーん、どうしよう、声が出ない、どうして僕は泣く事しかできないんだろう・・と考えている。
私:その通り。正解だ。唇や舌を上手に振るわせたり弾かせたり、直ぐにできるわけではない。彼らは大人以上に耳がいいので言葉のイメージはきちんと持っている。なんとかそれに近づけようと一生懸命に子音の練習をしているのが赤ちゃん。
君:ほほほ、お孫さんの事ね。
私:ああ、一歳半が二人いる。「バイバイ」が言えるようになった。有声両唇破裂音だ。「パパ・ママ」も楽勝だ。「パパ・ママ」は赤ちゃんが最初に言える言葉10傑の堂々一位・二位だね。「パパ」が先か、「ママ」が先か、どちらの言葉を先に言えるようになるか、若い夫婦の最大関心事だろう。ママの事をパパと発音してもがっかりする事は無い。彼らにとってはパパもママも身近な大人という意味なのだから。そのうちすぐにママとパパの意味の違いに気づくようになる。
君:乳児の時から英語教育をしたほうがいいかしら。
私:夫婦が国際結婚ならそうすべき。でも夫婦が共に日本人の場合はどうかと思うね。眠い。今夜はここまで。
君:有声両唇破裂音は舌を使わない子音なのよね。そりゃあ簡単だわね。なんといっても舌を使う子音の発音が難しいという事のようね。まずはキチンと日本語の発音を教える事ね。それには赤ちゃんに言葉のシャワーを浴びせかける事よね。胎教も大切ね。胎児は聞いている。ほほほ