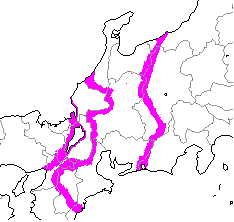 日本語における存在の動詞、ある・ゐる・をる、ですが、物が主語なら、ある、を使用しますが、人が主語の場合は、東日本(いる)/西日本(おる)の東西対立がある事で有名です。居る・飛騨方言、存在を示す動詞・おる、の分布(図の説明)もご参考までに。さて図を見て単純な東西対立では無いと言う事をどなたも直感なさるでしょう。ただし、現象を語ることは簡単でもその説明は一筋縄ではいきませんね。それでも私なりの説明、要は佐七節、を試みましょう。 日本語における存在の動詞、ある・ゐる・をる、ですが、物が主語なら、ある、を使用しますが、人が主語の場合は、東日本(いる)/西日本(おる)の東西対立がある事で有名です。居る・飛騨方言、存在を示す動詞・おる、の分布(図の説明)もご参考までに。さて図を見て単純な東西対立では無いと言う事をどなたも直感なさるでしょう。ただし、現象を語ることは簡単でもその説明は一筋縄ではいきませんね。それでも私なりの説明、要は佐七節、を試みましょう。
まず古語辞典をみます。あり、在り・有り、アリ、自ラ変、存在する、文例・竹取
ゐる、イル、自ワ上一、かかる・置く・つく、文例・万葉
をり、居り、オリ、上一、ゐありの転・いる、文例・万葉 ただし中世・近世に「いる」の意味に転
つまりは、いる・ある、が最古参の言葉であり、おそらくは古代日本語だったのでしょうね。東京語を代表とする東日本の言葉、いる・ある、は実は古代日本語なのでしょう。古代には中央、つまり奈良でも話されていた事でしょう。
そして、おる、も相当に古い言葉ではあるものの、語源が、ゐる連用形+自ラ変あり、と言う事は随分と丁寧な言い方であると言う事です。この言い回しが始まったのは中世・近世の上方です。ふるい言葉・ゐる、が全国で話されていた所で都の新しい言葉・をり、が地方に広まったのです。
ところが筆者にとって最大の謎は、何故に、大阪、滋賀県の一部、福井県の一部、が、いる、の話される地方なのか、という事ですが、これも筆者なりの説明をご用意しました。つまりは、一つにはこれらの地方は、奈良にとっては近い田舎という共通項があるのでしょうか。近い田舎は奈良の都の言葉・おる、を話すのに抵抗を感じて昔からの、いる、を話したという事ですかい。遠い田舎・偉大なる田舎の飛騨は喜んで都の言葉・おる、を話して現代に至っているのでしょう。
まとめですが、飛騨は南北は、おる・の地方、つまり美濃越中、に挟まれ、東西は、いる・の地方、つまり信州越前、に挟まれているのです。飛騨工説を信じたい佐七ですが、奈良の都言葉・おる、は飛騨へは南北両方向から流入した可能性も高い。しゃみしゃっきり。
|
日本語における存在の動詞、ある・ゐる・をる、ですが、物が主語なら、ある、を使用しますが、人が主語の場合は、東日本(いる)/西日本(おる)の東西対立がある事で有名です。居る・飛騨方言、存在を示す動詞・おる、の分布(図の説明)もご参考までに。さて図を見て単純な東西対立では無いと言う事をどなたも直感なさるでしょう。ただし、現象を語ることは簡単でもその説明は一筋縄ではいきませんね。それでも私なりの説明、要は佐七節、を試みましょう。