| 詩歌なう |
| 俳句紀行 |
| 小川双々子の世界 |
| アートシーン |
| 奥の細道ぼちぼち歩き |
| 俳画&俳句バックナンバー |
| 新・黎明俳壇 |
わが師、小川双々子の言葉の世界は、私にとって大いなる謎である。
なぜ、かくも双々子の言葉は緊密に響き合っているのか。
そして官能的、物質的に迫ってくるのか。 それを、この欄で追究して行きたい。
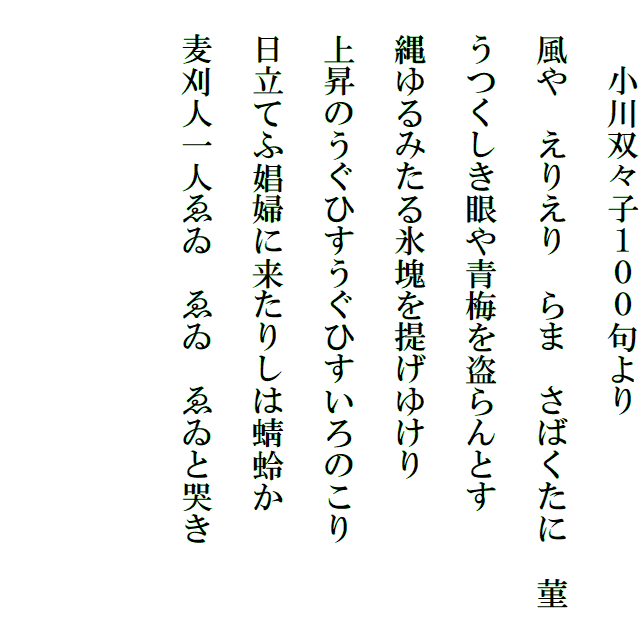
『幹幹の声』1962年、110頁
田圃の真中に一本足で立つ案山子が見えてきます。しかし、その案山子は、文部省唱 歌「案山子」(武笠三作詞)にある「天気のよいのに蓑笠着けて」の案山子ではありま
せんでした。継ぎの当たったボロの背広にボロのズボンをはき、穴の空いた中折れ帽を かぶった近代的なルンペン姿の案山子でありました。
所有物と言えば「一本の棒」があるにすぎません。しかし、ルンペン案山子は誇ら
しげでした。「一本の棒」の周りは一面黄金色に実った稲でしたから。まさに「年は豊年満作」(唱歌「村祭り」)なのです。
私は、「一本の棒」を取り巻くこの「豊作」を見ている内に、「一本の棒」が一本
の筆に見えてきました。作者は自らをルンペンと称し、筆一本で表現者として立つ姿勢を示した句に私には思えてなりませんでした。黄金色に実った稲、作品を満足そうに見渡し、田圃の中に無一物ならぬ一本の棒によって立つ案山子の矜持に私はこころ震わせるのです。
『囁囁記』1981年、73頁
この句を「くるりくるり」と「わらひける」の間に「回りながら」が省略された
ものとすれば、とても分かりやすくなります。
枯草をくるりくるりと回りながらわらひける
と読むわけです。でもそれでよいのでしょうか。「枯草をくるりくるりとわらひけ
る」に「回りながら」を補って読んで、それで満足してもよいのでしょうか。
「くるりくるりとわらひける」と表わされたその不可思議な「わらひ」はどこへ
行ってしまったのでしょう。
この句は、情景としては、「枯草の上をくるりくるりと回りながらわらった」と
いうことでしょうが、この枯草の上を回る人物は、「くるりくるりとわら」ったの
です。この笑いの質をこそ見届けなければなりません。
「くるりくるりと」には、身体を丸めて枯れ草の上を回る軽やかな身体の動きと
同時に、その姿勢で笑う苦しさが表されているのではないでしょうか。
この枯草というわびしさの上で軽やかにくるりくるりと回ってみせるこの人は、
その軽やかな動きの中で、笑うほかない苦(くる)しみの笑いを発しているように
思えるのです。深い悲しみが伝わってくる句です。
では、枯草以外が全てひらがななのは、どうしてでしょう。それは、枯草の上を
回る人物の連続する動きを、読者の目に感じさせるためです。三つの「る」が、
印象的です。
![]()
『非在集』2012年、12頁
まず、次のように読めます。
「柊挿す」は、節分に、焼いたいわしの頭を刺した柊の枝を戸口に挿し、邪気を
払うと歳時記にあります。言い換えれば、これは結界を張ることでもあります。
結界内は、外から災いをもたらす呪霊(えたいのしれないもの)が進入できない
ようにされた所です。そのため、結界内にいるものにとっては、そこは独房とお
なじなのです、と。
しかし、一句では、「柊挿してあり」は、節分の邪気払いの風習の意味を超え
ています。
「柊挿してあり」の「柊」は、結界をつくる呪物(まじない)としての鰯の頭か
ら切れた柊となっています。
キリスト教世界では、葉の縁に鋭いとげ(棘)をもつ柊は、キリストが張り付
けになるときにかぶらされた棘(いばら)の冠になぞらえられます。その意味に
節分の柊を転換したのがこの句です。柊は聖なるものとなっています。この生な
るもの柊は当然結界を張る力をもつものなのです。ところが、この結界を張る柊
は、罪人(つみびと)を封じる聖なるものにほかなりません。柊に封じられたそ
こは、犯罪者の押し込められる独房にひとしいと、罪人は言っているのです。
だが、その独房の入り口に挿されていたものは、青々とした美しい柊なのであ
りました。
『囁囁記』1981年、105頁
小川双々子の句集『囁囁記』(一九八一年)の一句である。
双々子の句は、端的に言えば、言葉の重層化によって成り立っている。言葉の多
義性を巧みに使い、一義的ではない重層的な奥行きのある句に仕立てているのであ
る。即ち一句を構成する一つひとつの言葉が相互に響き合って複数の意味・イメー
ジが現われることによって、読者の前に一句の世界が開けてくるのである。
さて掲出句であるが、一読、漢字片仮名表記の部分は、大雪の昭和十一年二月二
十六日午前五時ごろ勃発した、二・二六事件と呼ばれるクーデターの際に、反乱軍
兵士に宛てて戒厳司令部から発せられた投降を促す文書、放送の一節だということ
が分かる。
下記は、飛行機から撒かれたガリ版刷りのビラ(伝単)の文句である。これは戒
厳司令部の文書「兵に告ぐ」を簡略にしたものである。(原文は、漢字に片仮名
の振仮名が付いている)
下士官兵ニ告グ
一、今カラデモ遅クナイカラ原隊ヘ帰レ
二、抵抗スル者ハ全部逆賊デアルカラ射殺スル
三、オ前達ノ父母兄弟ハ国賊トナルノデ皆泣イテオルゾ
二月二十九日 戒 厳 司 令 部
さて、一句である。
一体、一句において何が「今カラデモ遅クハナイ」ないのか。そんなことは分か
っているではないか、と言われるであろう。今からでも遅くないから、自分の属す
る原隊に帰れば罪を問われない、いうことだと。歴史的にはそうであろう。二月二
十九日午前八時四十八分の臨時ニュースで放送された「兵に告ぐ」の一節において
は、
今からでも決して遅くはないから、直ちに抵抗をやめて軍旗の下に復帰する様
にせよ。そうしたら今までの罪も許されるのである。
とあるので、まずは、そう取れるであろう、と言っておこう。
次に、ではなぜ、「雪の電線」か。
読者は答えるであろう。二・二六事件当日は大雪であった。故に「雪の電線」
とは、当日の雪が電線に積もった光景を描いているのだと。
果たしてそれだけか。状況還元的な読み方ではそうかもしれないが、一句の言葉
に即してよむならば、「雪の電線」に象徴性を帯びた言葉が見えてくる。
「雪」及び「電」はともに雨冠の、天の象を表わす漢字である。漢字片仮名交じ
りの言葉は、常ならぬ言葉であり、それは、天から下された言葉であった。(大日
本帝国憲法を想起せよ)放送され、仮設されたスピーカーからも繰り返し流された
「兵に告ぐ」には、冒頭こうある。
兵に告ぐ 勅命が発せられたのである。既に天皇陛下の御命令が発せられたの
である。
それは、兵士たちにとっては、正に天からの声であった。そして、二月二十九日
午後二時、下士官兵は全て原隊に復帰した。
このように、一句は、「雪の電線」から「今カラデモ遅クハナイ」へと、無理な
く展開する。
しかし、ここで再度問おう。「果たしてそれだけか」と。双々子の読者は、双々
子の方法たる言葉の重層性を踏まえて読みを進めなければならないのだ。
「今カラデモ遅クハナイ」は、「雪の電線」で明確に切れを読切った時、大元帥
たる近代の天皇(制)とは別の超越者の言葉へと転換するのである。双々子はその
超越者の言葉を「今カラデモ遅クハナイ」と一句に書き留めたのである。
雪の電線今カラデモ遅クハナイ
の一義は、前述のように戦争を目的とする全体主義的国家総動員体制(総力戦体
制)の確立へと急速に展開する画期となった二・二六事件である。その二・二六事
件の象徴的言葉「今カラデモ遅クハナイ」は、一句において、双々子によって、意
味の転化がなされたのである。
双々子の超越者は言う。あなた方はまだ
「今カラデモ遅クハナイ」。
同じ道を歩むな、と。
「雪の電線」の句は、このような多義性が統一された一句なのである。
*久保純夫編集・発行『儒艮』№16所収
『囁囁記』1981年、18頁
この句は、「稲を刈る音一つつれゆく」と目的語を隠して読者の興味をそそり、
下五で「白き世を」とそれを明かす構造になっている。そして、このように書
くと「稲を刈る音一つつれゆく白き」を得ることができる。これも双々子が、
この句で倒置と呼ばれるレトリックを結果として出現させた理由かもしれない。
体も「白き」ことになるのである。そして「音」がつれゆく「世」も「白き世」
となる。「白き」と「世を」との間に僅かに間を取らせる、もしくは取るところ
が双々子的である。さらに、倒置の作用として、既成概念としての文法に沿った
語順にもどろうという意識が読者にはたらき、「白き世を」が「稲を刈る音一つ
つれゆく」に続くようにもどって読む方向に行くのである。
このようにエンドレスに。
稲を刈る音一つつれゆく白き世を
↓
白き世を/稲を刈る音一つつれゆく
↓
稲を刈る音一つつれゆく白き世を
↓
白き世を/稲を刈る音一つつれゆく
↓
:
稲を刈る音が一つするたびにその音が刈る者の内なる白き世を何処ともなく連
れ去るのである。その「白き世」のイメージはタブララーサ=白紙ゆえに読む者
によって違ってくる。しかし、連れ去ることも白いとされるので、稲を刈る音は
虚無の響きを発するのである。それがいつまでも繰り返されるのが一句の世界で
ある。
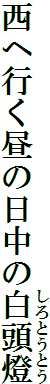
西へ行く昼の日中の
一
「西へ行く昼の日中の白頭燈」とは一体何であるか。一句を読み下してみよう。
何かが「西へ行く」、それも「昼の日中」に。明るい昼間のそのまた明るい光の
中、さらに明るい白い光を煌かせ頭燈なるものは西へ行くのである。「昼の日中」
を貫き。
そして、「昼の日中の」からは、「日中」が、読者の眼前に見えてくる仕掛け
となっている。「西へ行く」から「日中」そして、「白頭燈」となれば、誰もが、
軍用列車を詠んだ西東三鬼の昭和十二年の作、『旗』(昭和15年3月25日刊)の
「黒」三句のうちの冒頭、
を思い出すであろう。「日中」は「日中戦争」を想起させ、「西へ行く昼の日中
の白頭燈」は、軍用列車の先頭を行く機関車の前に付けられた前照灯(注1)を指
すにちがいないのである。
歴史的に双々子の「白頭燈」の句を読めば、まさしくこれが、昼の日中に前照
灯から白色光を放ちながら「西へ行く」ものの正体であった。
それにしても「白頭燈」という言葉の夢幻性はどうだ! 真昼間にその強烈な
白色光を照射しながら、一個の異様な美しさを持った物が西へ疾駆しているので
ある。
二
双々子は、『小川双々子全句集』の「差異時記―全句集の覚書―」(507頁)
で次のように語っている。
「次第に見馴れて、白頭燈の軍用列車は日常のことになった。大方は客車二三
輌、貨車十数輌編成で来る。小旗で、見送る。」
白頭燈は、双々子の言葉により、兵士や軍馬を大陸へ送るため西へ向かう軍用
列車のヘッドライトであることがはっきりした。しかし、先に私が「白い光」と
した「白」が本当に「白い光だったか、事実である証拠はない。
しかし、それも「列車のヘッドライトとテールライトが消えたら・・・」(鉄
道建設本部計画部「鉄道豆知識」№2、『鉄道・運輸機工だより』新春号)に出
あってほぼ解消した。
そこには、「鉄道に関する技術基準第119条」(合図及び標識)が引かれ、在
来線にあっては「前部標識:列車の最前部車両の全面に白色灯1個以上(昼間に
あっては、標識を表示しないことができる)」と書かれていたのである。
白頭燈は前照燈もしくは前燈のことであり、機関車の前部標識として前照灯は
白色灯を義務付けられていた。しかし、昼間は、点けても点けなくてもよかった
が、この句では、「昼の日中の白頭燈」と尋常でない響きを持って表現している
ので、この機関車は頭燈を白く燈していることになる。
李賀は「南山田中行」において、九月、「鬼燈如漆照松花」(鬼燈漆の如く松
花を照らす)と歌ったが、双々子の白頭燈は、白昼何を照らし出しながら西へ疾
駆するのだろうか。
そして、双々子の句のように、軍用列車は昼間も白色灯を点けていたのか。
三
「京大俳句を読む会」のブログ2013.05.29Wednesday|09.41で、
兵隊が征くまつ黒い汽車に乗り 昭和12年
を鑑賞している佐々木峻氏が、そこで、「こんな実景を見た人はもう殆どないで
あろう。僕は少年時代の印象に強く残っている。どこかの任地に送られるのであ
ろう。何輌もの長い長い黒い貨車に兵隊が満載されて征く」と述べていたので、
さっそく「白頭燈」について聞くことにした。佐々木氏に手紙を出した。「昼間
行く軍用列車の先頭の機関車に付けられた前照灯は、点っていましたでしょうか」
と。一週間後に待望の返事が来た。次の通りである。
……少年時代の一時期、私は山陰線の鉄道近くに住んでいましたので、黒い
貨車、それも無蓋車に膝を接するほど兵隊が詰められてゆく景をよく見ました。
その機関車は、霧の日などには、煌々と前照灯を点けていました。また、兵
を積んだ軍用トラックが列をなして通るときには、白昼でもヘッドライトをて
らして走っていたのを覚えています。これは、他の車などをさけさせて優先的
に行くための一種の威嚇行為ではなかったでしょうか。それは、昼の日光のも
とでは、黄色でなくて白色に光っていたとの感覚はよくわかります。
小川双々子の句はそれではないでしょうか。「西」が意味深長ですね。
「昼の日中の白頭燈」、それは、昼の日中=日常世界を照らし出すかのような
威嚇の光であったのだ。
(注1)「白頭燈」、これは日本の辞書にはなかったので、ネットでWebio
中日対訳辞書にあたったところ、「汽車頭燈」が出てきた。日本語では「前照灯」
とあった。これで、「頭燈」の出所が分かった。「頭燈」とは中国語だったのだ。
「白」は当然「白色灯」の「白」である。「白頭燈(しろとうとう)」とは双々
子の造語であった可能性が高い。ちなみにネットで中国人が「白頭燈」という表
現を使っていた例を発見した。英訳は、white head lightであった。
(注2)川名大氏が『現代俳句 上』268頁で、「初出『京大俳句』昭和十三年八
月号で、『兵隊が征く』の表記になっている」といっているが、初出は「『京大
俳句』第五巻(昭和十二年)第八号」である。(「京大俳句を読む会」のブログ
2013.05.29Wednesday|09.41による。
ところで、三鬼が、初出「征く」を句集では平仮名「ゆく」にしたのはなぜか。
ここはあまり深く考えずに、「兵隊がゆくまつ黒い汽車に乗り」にしたのは、
「ゆくまつ黒い」とすることで、「黒」をより際立たせたかったからではないか、
としておこう。
![]()
殉教者たちが、X字架刑に架けられる春。
その春が、天上を今まさに行くのである。
全人類を救うためにイエスが架けられた十字架ですら異様なことなのに、楽しか
るべき春にX字架刑はなされ、その春は天上=神の世界をただただ過ぎ行くのだ。
神の子イエスの死だけで足りずに、復活の春にさらにX字架に架けられなければな
らない殉教者の出現する人間界。そこに生きる罪深い人間は、ただ天上を行くX字
架刑の春を見上げるのみ。
注)12使徒の一人で、シモン(=ペトロ)の兄弟の聖アンデレが、ギリシャのア
カイアのパトラスで磔刑に処せられた。その十字架がX字の形をしていた(手足を
広げた姿を想像していただきたい)。それを、「聖アンデレ十字架」という。「X
字架刑」とは、直接には、聖アンデレの磔刑=殉教を指す。
![]()
いきなり意味づけをして読みにかかってはならない。
一面真っ赤な落椿の世界。落椿とは文字通り椿の木から落下して来た椿なので
ある。
「すべて」は、落下し終えた椿ではない。椿の木に咲いていた「すべて」の花
のことなのである。落椿はその「すべて」の花の「一つ一つ」なのだ。
ここでは、無数の落椿の中に立っている無数の花を咲かせている、今ここに書
かれていない椿の木をイメージしなくてはならないのだ。作者はそれを見ている
のだ。一箇一箇の生あるものの一箇一箇の滅びの姿を。
そして、信仰ある読者はその「すべて」、即ち「全なるもの」を「神」へと昇
華するであろう。
一句をどのように意味づけかは読者の自由であるが、まずは句に即して読み解
かねばならない。そうでないと俳句が散文に溶解してしまう。
![]()
玉虫は美しい虫である。あの光沢のある緑の輝きは、まるで宝石が歩いているよ
うである。それゆえ、「玉虫のかがやき」と書き起こされると、山口青邨の
玉虫の羽のみどりは推古より
を思い、ロマンチックな展開を期待するのであるが、意に反して、「新聞紙を歩き
つ」となる。
「新聞紙」は、いうまでもなく人間の欲望を巡る喜怒哀楽、阿鼻叫喚に満ちた日
日営みの総体が、表裏余すところなくびっしりと書き込まれ詰め込まれている物で
ある。その新聞紙という物を、あの美しい「玉虫のかがやき」照らしながらが歩い
たというのだ。
だが、果たして、「玉虫のかがやき」は、新聞紙に蠢く人間の欲望を浄化するこ
とになったであろうか。
「玉虫」の雅と「新聞紙」の俗との見事な対比の中に展開される不思議な世界が
ここにある。
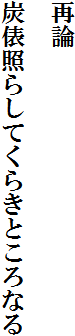
再論「炭俵照らしてくらきところなる」
-李賀と小川双々子-
小川双々子の『荒韻帖』(2003年年6月、邑書林)「亡郷」に次の句がある。
炭俵照らしてくらきところなる
炭俵とは藁で出来た俵の中に炭の詰まった物である。その真っ黒な炭が詰まっ炭
俵という物が照らしたそこは暗いところであったというのだ。
炭=暗黒の塊が詰まった「炭俵」に照らされることによって、白日の元に「くら
きところ」はさらされるのである。
そして、一句において、暗黒によって照らされるにも関わらず、それは照らす、
即ち光を当てることによって物を際立たせることと変わりのないことを読者に納得
させるため、「炭俵照」以下が「らしてくらきところなる」という平仮名表記にさ
れている。通常の光と違い、照らすことによって「くらきところ」を際立たせる光
がここに現れる。
それを、一人の人物が見つめている。炭俵が照らし出した「くらきところ」とは
外でもない、自分自身の内部なのではないかと。
「炭‐俵」と言う言葉の持つ物質感が一句にリアリィを与え、読む者を捉えて離
さない。
実は、話はここで終わらない
中國詩人選集⑭『李賀』(注1)(荒井健注、岩波書店)を読んでいたら「鬼燈
如漆照松花 鬼燈漆の如く松花を照らす」(「南山の田中の行(うた)」)という
句に出会ったのである。「鬼燈(鬼火=人魂)が漆(うるし)のように真っ黒な光
で松花を照らしている」と読んだ俳人である私は、双々子の「炭俵照らしてくらき
ところなる」が脳裏に浮かんだ。
しかし、荒井は「松花」に注して、次のように言う。
松花 春に咲く、黄色い松の花。李賀の「神絃別曲」にも「松花は春風のうち
に山上に発(ひら)く。」とある。但し、この詩の場合は、季節が秋とはっきり
しているから、松の花ではおかしい。或いは秋の末に熟する松の実かも知れない
。現代中国語で松花(スンホア)と言えば松の実をさすのが普通。(前掲書79頁)
今は九月(新暦十月)である。それなのに春に咲く「松花」とは「おかしい」と
いうのだ。そこで、「松花」は「松の実」かもしれないという。現代中国では「松
花」は「松の実」を指すからと。
しかし、これは詩である。しかも、李賀である。荒井も中國詩人選集⑭『李賀』
の解説で言っている。
死せる美女に対する思慕の念にあふれる「蘇小小の歌」(40ページ)、真夜中
の墓場をえがく「感諷(其の三)(98ページ)、さまざまな化け物の現われる「
神絃曲」(177ページ)等を見よ。そこには極度にロマンチックな幻想の世界が
展開される。元来、中国の文学は、夢幻的なイメージの創造を得意とはしない。
詩も、大半は日常のありふれた経験をテーマとし、その傾向は時代が下るにつれ
て次第に強まる。かれは中国文学史上孤立した詩人と見なしてよい。(前掲書、
5頁。下線、武馬)
そうなのだ。ここは「日常のありふれた経験」をもとに読んではならないのだ。
死者の世界の出来事として読まねばならないのだ。ここではあくまでも松の「花」
である。「鬼燈」(鬼火)が照らすからこそここでは散ったはずの「松花」なので
ある。漆黒の光で照らされるが故に「松花」は妖しくこの詩の中に現るのである。
荒井は「鬼火がうるしのように光り、松花を照らしている」と訳しているが、
ここは現代の俳人として、李賀は「鬼火の発する光を、一度生命の尽きたものを照
ら出し甦らせ現前化する力を持つ漆黒の光」としてイメージしていると取りたい。
李賀の句と、双々子の句が交差するところはここである。照らすのは明るい光だ
けではない、漆黒の光、暗黒の光が照らすこともあるのだ。そして、照らされて現
れるものは日常的な世界を踏まえつつも日常を超えたものなのである。
<注>
1 李賀:791年~817年。中唐の詩人。27歳で死去。「鬼才」と呼ばれた。
補論 1 李賀「南山田中行」を読む
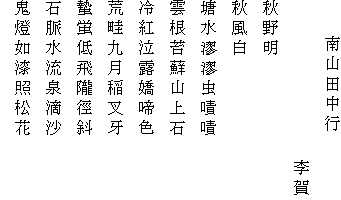
参考までに、李賀の傑作「南山の田中の行(うた)」の全文を掲げ、読んでみ
よう。語釈は、*で示す。
南山田中行 南山の田中の行 李賀
秋野明 秋野明るく
秋風白 秋風白し
塘水漻漻虫嘖嘖 塘水漻漻 虫嘖嘖
*池の水は清く澄み切って深く、虫はしきりに鳴いている。
雲根苔蘚山上石 雲根 苔蘚 山上の石
*雲が湧く山上の岩は青くこけむしている。
冷紅泣露嬌啼色 冷紅 露に泣く 嬌啼の色
*冷ややかな赤い花は露の涙を流し、その泣く姿は、なまめかしい。
*『中國詩人選集』の訓読は「冷紅 露に泣き 啼色嬌(うつく)し」
であるが、ここは原田憲雄訳注
*「蘇小小の歌」に鬼火(翠燭)を形容して「冷翠燭」とある。
荒畦九月稲叉牙 荒畦九月 稲
*九月の荒れた田は、稲穂がまるで歯が欠けた様だ。
蟄蛍低飛隴逕斜 蟄蛍低く飛び 隴逕に斜めなり
*昼間かくれていた蛍が、畑中の道を低く斜めに飛んで行く。
*『中國詩人選集』の訓読は「隴逕斜めなり」であるが、ここは原田憲
雄訳注『李賀歌詩編』によった。
*「斜」は李賀のキーワードの一つのように思われる。「斜」は尋常で
はないイメージ
の結句に「露脚は斜めに飛びて寒兎を湿(うるお)す」とある。「露脚」
は滴る露。「寒兎」は月に棲む兎。
石脈水流泉滴沙 石脈水流れて 泉
*石の筋目を通って泉となって湧き出た水が、砂に滴る。
鬼燈如漆照松花 鬼燈
このように、「南山田中行」の第1句から第8句目までは、南山のふもとの田野
の道を歩いて行く時の本来はなんの変哲もない風景を歌った詩である。しかし、結
句「鬼燈漆の如く松花を照らす」まで読み、振り返れば、その何の変哲もない風景
は読む者にとって異様な風景と化す。
まず、この詩の世界は夜なのか、それとも昼間から夜への時間の経過が詩中にあ
るのか、それすら読めば読むほどわからなくなってくる。
原田は『李賀歌詩編』で、李賀が拠った先行の魏の文帝、李白の詩が夜であるこ
とを挙げ、「夜の田中を歌った」(394頁)とはっきり言っている。
鈴木虎雄『李長吉歌詩集』(上)は「田野を過ぎて見たさまをのべた」(199頁)、
黒川洋一『李賀詩選』は「田野を過ぎたときに見たことを述べる」(87頁)とあ
るのみで、明言を避けている。
作者の意図は分からないが、成立した詩は、鬼燈が照らす夜であり普通の意味の
夜ではない。結句「鬼燈漆の如く松花を照らす」から「蛍」を見れば、蛍もまた鬼
燈に照らされ、「感諷 其の三」の「漆炬 新人を迎え 幽壙 蛍擾擾たり」(補
論2-注2)の蛍に化すのである。これは蛇笏の芥川龍之介の死を悼んだ句「たま
しひのたとへば秋のほたるかな」を思い起こさせる。もちろん、李賀は蛇笏と違い
奇怪であるが。
それと同じように「秋野明るく/秋風白し」も普通の意味の明るさでもなく白さ
でもない。「秋野明るく」の「明るく」は依田仁美の「陽は夏陽風は夏風常盤橋閑
からとしてやたら明るし」の「明るし」に通ずる明るさであろうし、「秋風白し」
は芭蕉の「石山の石より白し秋の風」の「白し」に通ずる「白し」であろう。とも
に反転された世界に属す言葉である。(依田の歌と芭蕉の句については、武馬の
HP『円形広場』の「詩歌なう」「奥の細道ぼちぼち歩き」参照)
第4句は、改めて読めばそれは雲の生まれる山上の風景である。それを田中を行
く人物が歌う。この山上の荒涼たる風景が、第5句の山上とも山のふもとも知れ
ぬ「冷紅 露に泣く 嬌啼の色」を引き出す。
第5句に関して注目すべきは、李賀の代表作「蘇小小の歌」(帰ってくるはず
もない男を待つ5世紀末に死んだ名妓の悲しみを歌う)に鬼火(翠燭)を形容して
「冷翠燭」とあることである。意訳を付けてその個所を引く。
油壁車 女性の乗るあでやかな車が
久しく相待つ 計り知れないほど長い間待っている
冷やかなる翠燭 冷ややかな翠の鬼火も
光彩を労す いつしか光が衰えてしまうほど
この用例に従えば、「冷紅」とは、死の側に冷え冷えと咲く紅い花ではないか。
それ故、この第5句は、第6句の村落の荒廃をも暗示する荒廃した田の描写へと展
開し、それが先に述べた死の側のイメージを持つ第7句の「道すれすれに斜めに飛
ぶ蛍」へと繋がるのである。そして、蛍の光がゆらゆらと揺れる泉。その泉にゆら
ゆらと揺れる光は「鬼燈」と化し、結句となる。
李賀のこの「南山田中行」は、結句「鬼燈漆の如く松花を照らす」が、全編を照
らし出すこの世でありながらこの世でない世界の風景なのだ。そのような風景の中
を李賀は歩いているのである。
補論 2 「鬼燈如漆」の「漆」とは何か
中國詩人選集⑭『李賀』の解釈に満足できなかった私は黒川洋一編『李賀詩選』
(岩波文庫)と、中國詩人選集⑭『李賀』(荒井健注)との解釈の比較を試みた。
両書は、テキストが違うため、中國詩人選集⑭『李賀』では「鬼燈如漆照松花」
となっているが、黒川洋一編『李賀詩選』(岩波文庫)では、
鬼灯如漆点松花
となっており、「鬼灯は漆の如く松花に点ず」と訓じ、「人魂の青い提灯ほの暗く
松の花に懸かりて灯(とも)る」(注1)と訳す。注では、
鬼灯如漆 鬼灯は鬼火、燐火。如漆とは如漆灯ということであり、漆灯とはほ
の暗い灯火のことである。
となっていた。「如漆」を「如漆灯」とし、「ほの暗い灯火のこと」とする。これ
は、『広漢和辞典』の「漆燈」の説明と同じである。(『大漢和辞典』では「暗い
燈火」とある。)せっかく、黒川は、
松花 松の花。松が黄色い花をつけるのは春であり、この詩の季節には合わぬ
が、それはこの詩が幻覚によって成ったものであることによると見るべきであ
る。
と述べ、荒井のように詩であることを忘れた合理的解釈を排しているのに、「漆
灯」を「ほの暗い灯火のこと」とあっさりと言い切ってしまうことの不思議さを思
う。この読みからは、李賀がなぜ「漆」と言う語をわざわざ一番大事な結句に持っ
てきたが説明されていない。たとえ黒川の言うように一歩譲って「如漆」の「漆」
は「漆灯」であったとしても、「漆灯」は単に「ほの暗い灯火こと」ではない。
「漆灯」そのものであるのだ。
『字源』に「漆灯」はないが、鐘ヶ江信光編『中国語辞典』(大学堂書林 1960
年には「漆油」があり、それは漆の実から取れる「木蝋」とされる。HP「中国
の伝統的な祭日」の「元宵の灯篭(正月15日)」に、次のようにある。
元宵に灯篭を飾ることは、南北朝のころにすでに習わしとなり、南朝の梁・簡
文帝は、かつて『列灯賦』を著わし、元宵に灯篭を飾る様子を次のように描写し
た。油灯や漆灯があり、或いは線香を焚き、ろうそくを点じ、輝く灯火と月光が
水面に映っていると。(下線、武馬)
「油灯や漆灯」とあることから、漆灯は、木蝋を直接燃やした灯の可能性もある
が、私は、「漆灯」は漆蝋から作った蝋燭ではないかと思う。(注3)「漆炬」と
いう言葉を李賀は「感諷 其の三」(98頁)(注2)で「一山唯だ白暁 漆炬新
人を迎え 幽壙蛍擾擾たり」と使っている。「炬」は「ろうそく」であり、「蝋
炬」と使う。それ故、いずれにしても、単に「ほの暗い灯火のこと」とするのは
おかしいのではないか。
そこから李賀の詩を読めば、「鬼燈(鬼火)は漆燈(漆炬=漆蝋で作った蝋燭)
のようで、それが松花を照らしている」と訳すことができる。「如漆」の「漆」は
中国文学者の黒川の言うように「漆燈」の意にまず間違いはないであろう。
しかし、話はここからである。たとえ「漆」が「漆燈」であろうとも、表記は、
「鬼燈如漆」なのである。現に二人とも
鬼燈漆の如く松花を照らす(荒井)
鬼灯は漆の如く松花に点ず(黒川)
と訓じている。
読者はまず漆の漆黒をイメージしてもよいのである。漆黒が照らすと読むのが無
理があるというのなら、同じく李賀が「北中寒」の冒頭で「一方黒く照らし 三方
紫なり」(注4)と表現しているのはどうであろうか。
ここは、文字通り漆黒の灯と読めばよい、と俳人武馬久仁裕は思うのである。
ながながと書いてきたが、要するに「鬼燈如漆照松花 鬼燈漆の如く松花を照ら
すは、「鬼火が漆黒の光で松を照らせば、そこには、松の花が照らし出される」と
読めば良いのである。たとえ解釈上は「如漆燈」であろうとも、その「少し黄色味
がかかってやわらか」く燃えているはずの鬼燈=漆燈の光は、読者の脳裏には漆黒
の光へと転ずるのである。
李賀「南山田中行」は、言葉=文字による虚構の世界なのである。
<注>
1 「鬼灯如漆照松花(鬼燈漆の如く松花を照らす)」と「鬼灯如漆点松花(鬼
灯は漆の如松花に点ず)」とどちらが表現として優れているかは、今は問わな
い。
2 「感諷 其の三」の全篇を掲げる。「南山田中行」と読み比べていただきた
い。
其の三
南山 何ぞ其れ悲しきや
鬼雨 空草に灑ぐ
長安 夜半の秋
風前 幾人か老ゆ
低迷す 黄昏の徑
裊裊たり 青櫟の道
月午にして 樹に影無く
漆炬 新人を迎え 墓穴を照らす漆蝋の燭が花嫁を迎え
幽壙 蛍擾擾たり ほの暗い墓穴に蛍が喜び乱舞する
*訓読は、荒井健注、中國詩人選集⑭『李賀』98頁、による。最後の3句
は武馬が意訳した。
3 「漆蝋(うるしろう)による和ロウソクづくりの継承(日本財団)」というH
Pに「漆蝋の炎は、市販されているパラフィン製に比べ、少し黄色味がかかっ
、 てやわらかさがあり、3倍程度長もちするそうです」という記事がある。
4 「北中寒」の全篇を掲げる。
北中寒
一方黒く照らし 三方紫なり
黄河 氷合し 魚竜死す
三尺の木皮 文理を断つ
百石の強車 河水に上る
霜花 草上 大なること銭の如し
刀を揮えども 入らず 迷濛の天
争瀯たる海水 飛凌喧し
山瀑 声無く 玉虹 懸かる
*訓読は、原田憲雄訳注、『李賀歌詩編』3、92頁による。
「一方黒照三方紫 一方黒く照らし 三方紫なり」は、原田によれば、次の
通りである。
中国では、四季に、青、赤、白、黒の色を配し、また東、南、西、北の四方
を当てる。北方は玄冬、すなわち黒である。北方の陰寒たる玄気に照射され
て、東、南、西暖の気が薄れ、青も赤も白も、その固有の色彩を失って、一
様に間色の紫となる、というのである。
これに付け加えることはない。
<参考文献>
1 荒井健注、中國詩人選集⑭『李賀』、岩波書店、1959。
底本は「宋宣城本・李賀歌詩篇四巻外集一巻」(民国7年〔1918〕董氏誦芬室
影印)。
2 鈴木虎雄注釈、『李長吉歌詩集』(全2冊)岩波書店、1961。
底本は、元の呉正子本(1818年に昌平黌より覆刻刊行された官板『唐李長吉歌
詩』三冊に拠っている)。
3 黒川洋一編、『李賀詩選』岩波書店、1993。
底本は、前掲書に同じ。
4 原田憲雄訳注、『李賀歌詩編』(全3巻)、平凡社、1998。
底本は「宋宣城本・本李賀歌詩篇四巻外集一巻」(台北の国立中央図書館が蔵
し、1971
傾き翔ぶものがある。そこにしぐれが降りかかる。そして傾き翔ぶものが実は一
機のヘリコプターであり、それは「杳し」と断定される。「飛ぶ」でなく「翔ぶ」
とされることによって、これは「ヘリコプター」の擬人化をもたらす。
初冬の冷たいしぐれ降る大空を何処へかと翔び去って行く「ヘリコプター」は、
命あるものの如く、いよいよ寂しく、いよいよ孤独の相を深くするのだ。その姿を
ヘリコプターを見上げる人物は、「杳し」と表現したのである。
「杳し」は、暗くてはっきりしないはるかな向こうの存在をイメージさせる。「
杳として行方がわからぬ」と使う時の「杳」である。
「傾き翔ぶ」の「傾き」は、もちろん翔ぶものの存在の全きならざることを暗示
している。
そして、同じしぐれに濡れながら、「ヘリコプター」を「杳し」とする句中の人
物もまた、傾き翔ぶ杳きヘリコプターを我がこととし、見上げているのである。
私は、ここで、死の前年に書かれた啄木の「飛行機」(明治44年)という詩を思
い出す。
見よ、今日も、かの蒼空に
飛行機の高く飛べるを。
ここでは、「飛行機」は希望である。その希望の飛行機を見上げているのは、
たまに非番の日曜日、
肺病やみの母親とたつた二人家にゐて、
ひとりせつせとリイダアの独学をする眼の疲れ……
を覚える「給仕づとめの少年」であった。
啄木の「飛行機」は、日本近代の始まりであった。では、双々子の「ヘリコプタ
ー」は、いかな時代のものであろうか。

山口誓子の昭和8年(1933年)の句、
夏草に汽罐車の車輪来て止まる
の「汽罐車」に対して「わが電車」と発せられた平成11年(1999年)年のこの句
は、時代というものを映し出して面白い。
誓子の句には、物理的エネルギーそのものを体現した汽罐車に拮抗する生命のエ
ネルギーを漲らせた夏草とが作り出す緊迫した世界がある。
それに対して、掲出句の「夏草」と「電車」の間には緊迫感がない。ここでは、
汽罐車を堂々と受け止める「夏草」はなく、また「夏草」にその勇姿を誇る「汽罐
車」もない。あるのは、正にすれ違う「夏草」と「電車」のみである。しかも、そ
の電車は、勇姿とはほど遠い、夏草と擦れ違いざまにあえなく「疵つ」くひ弱な電
車なのである。
十五年戦争の最中の汽罐車はあくまで力強く、平和な世紀末の「わが電車」は、
疵つきやすいひ弱な存在であった。
しかし、作者は「わが電車」のひ弱であることをいうが、されど「わが電車は」
なのである。
ここまで書き進めてきて、ふいに『奥の細道』の中の芭蕉の一句が浮かんだ。
ぜい十もあればいいと僕は思います。内容とどうかかわり、いかに思想化していく
か。本質的な意味で季語をとらえないと文化には切り込めない」が、私の頭の中で
またもや響き始めたのであった。
この「竹鋸」は、いつの頃から置かれているのだろうか。
それ故、「竹鋸」という言葉は、近世の昔を思い起こさせる。近世から近代を経
て、現代までずっと置かれ続けて来た「竹鋸」がここにある。
では、この竹鋸は、一体なぜ、ここに置かれ続けなければならないのか。この句
に書かれていない、罪人のことを考える。
竹鋸は、その首を斬るべき罪人が現れるのを待ち続けているのである。しかし、
置かれ始めて以来、幾百年かの年月は空しく過ぎ去った。現れるべき罪人は、終に
現れず、竹鋸が、今もなお、只、灼熱の炎天に置いてあるだけである。
竹鋸の置かれている炎天には、刑を待ち望む観衆の姿もない。
だが、私には見えるのだ。炎天に灼かれながら、竹鋸の前に佇立し、竹鋸と共に
ひたすら「 罪人」を待ち続けている一人の人間の姿が。
「水口やきらめきは水のみならず」と書かれると、水口から迸る水のきらめきの
中に、もしくは、きらめきの背後に水とは違う「きらめき」を見ようとする目が働
く。
そして、「水口」が田へ水を引く口であってみれば、「きらめき」に生命のきら
めきを見て鑑賞を終えることも可能であろう。
しかし、多くの人はこの鑑賞に満足しないに違いない。それは、「水口や」の
「や」が、一句の文字の表記と配置の視覚的効果と相俟って、「水口」=田へ水
を引く口であることを越えて、水口一般へ転化させるからである。
「水口や」で切れると同時に、「や」からひらがな表記が最後まで続き、しかも
ひらがなの途中に「水」という漢字を二度まで使って置かれている意味はもうお分
かりであろう。「きらめきは水のみならず」は「水口」から「や」と現れた水が落
下する姿の形象化なのである。
水口を高所にイメージとして押し上げ、そこから水はきらめきつつ落下する。だ
が突然、落下する水を見つめている者へ、「きらめきは水のみならず」と声が響く
のである。真の「きらめき」を求めよと。
鑑賞の対象としての句から、自らの生き方を問われる句への変貌である。
双々子俳句の持つ預言的響きを、この句にも私は感じる。
と、私は、かつて書いた。
それから8年。今年2012年の3月に伊賀上野にある
蓑虫庵を訪ねたおりに、土芳が芭蕉(1644~1694)に滋賀県甲賀郡の水口(みな
くち)で会い蕉門に入ったということを知ったのである。

芭蕉の『野ざらし紀行』にある
水口にて二十年を経て故人に逢ふ
命二ッの中に生たる桜哉
である。
詞書にある故人とは旧友の意。芭蕉の俳諧観を述べた名高い「
服部土芳のことである。貞享2(1685)年3月中旬、東海道の宿駅、水口で20年
ぶりに芭蕉は旧友土芳に逢った。芭蕉42歳、土芳29歳。
その感慨を芭蕉は「命二ッの中に生たる桜哉」と詠んだのである。
「今2人は確かに生きてここに有る。相対する2人の間に今咲き誇る桜も間違い
なく生きてここに有る」と。
「命」は、芭蕉があこがれた西行の「年たけてまた越ゆべしと思ひきや命なりけ
り佐夜の中山」(新古今集)を面影とし、「桜(花)」は「ねがはくは花のしたに
て春死なむそのきさらぎの望月のころ」(続古今集)を面影とする。
いい、芭蕉の句では、「命二ッの中に生たる桜哉」という。西行は死に傾き、芭蕉は生に
向くという対比が味わい深い。
と言ったことを考えながら、私は、双々子の句の「水口」は、芭蕉と土芳が子弟
の契りを結んだ東海道の水口も意味しているのではないかと思ったのである。
「水口」を東海道の水口として読むならば、まさしく「水口やきらめきは水の
みならず」なのである。「水口」を、芭蕉と土芳二つの命が出会い、命のきらめき
を見せた水口としても読むとき、一句はいよいよ耀きを増すのである。
元禄元(1688)年3月4日、土芳は自ら庵を結んだ。号して
に些中庵を訪れた芭蕉は自筆の面壁の達磨像に次の句を賛して土芳に贈った。
蓑虫の音を聞きに来よ草の

現在の蓑虫庵に掛かっている蓑虫の句の賛がある面壁の達磨図。この掛け軸の来歴ははっきりしない。
ちなみに、芭蕉は土芳の庵でこの時、「伊賀の城下にうにと云ふものあり。わる
くさき香なり」と詞書して、次の句を作った。「うに」は泥炭。「うに」の燃え
る「わるくさき香」もまた故郷の香であり、それを詠むのも俳諧であった。
香に匂へうに掘る岡の梅の花
小川双々子の句は、言葉のもつ多義性を最大限活用することによって、日本語の
表現力を最大限引き出そうとする。読む者はそれに応え双々子俳句の持つ重層的表
現を読み尽くそうとする。そこにこそ、読む者の無上の喜びがある。
|
この句を読み下すとき、「ひひ」という言葉が目に飛び込んで来た。もちろん、「ひひ」という言葉は、この句にはない。「人買ひ」の「ひ」と「ひそと」の「ひ」があるだけである。
昼食を終えた私は、大通りに面したカフェでお茶を飲んでいました。右手にティーカップを持ちながら、ふと外を見ますと、一本の桜の木から、わずかに残った花びらが、今まさに、ひらひらと音も無く歩道に散って行くところでした。 それを見た私の心に深い悔恨の情が沸き起こり、またたく間に、全身に広がりました。散り行く花びらとともに、桜の木をとりまく空間が、寂として無そのものになって行くのが怖いほどわかりました。 「本当は、今、自分はそこにいるのではないか、いや、自分が生きている世界がそのようなものとして本当は、あるのではないか」という思いが私を襲いました。 いつでも無に化す可能性を持った危ういところに自分が立っていることを、見せられたのでした。自分の中に業としか名付けようのないものが有る限り、「盻きの残花ひとひら散るところ」を、私は見続けるに違いありません。
貞享4(1687)年11月12日,尾張領を追われ渥美半島保美に隠棲していた愛弟子杜国(万菊丸)を越人とともに訪ねた芭蕉は、半島の西の鷹の渡りの名所伊良湖岬で「鷹一つ」と発して、「見付てうれしいらご埼」と結んだ。 平成14(2002)年、伊良湖岬を訪れた双々子には、芭蕉のような心の華やぎはあろうはずもなく、「鷹一つ」と発して,絶句。 「此洲崎(このすさき)にて碁石を拾ふ。世にいらご白(じろ)といふとかや」(笈の小文)と,伊良湖岬の恋路ヶ浜で美しい「空せ貝」を、愛弟子と探す芭蕉の楽しさも亦なく、双々子の前に、渚は白々と続き、求める「しろき刃」はどこにもない。それ故、「渚はしろき刃なし」とただ記すより外はなし。 11月16日,伊良湖から鳴海の知足亭に帰った芭蕉は、その夜、越人・知足と表6句を詠んだ。冬旅の苦労をなぐさめた知足の発句「焼飯や伊羅古の雪にくずれけん」に付けた芭蕉の脇句は、「砂寒かりしわが足の跡」。 だが、双々子には、砂浜に残したはずの「足の跡」もなく、あるのは「しろき刃」の幻のきらめきのみ。
蝙蝠傘を差して、ビルの谷間に来たのは誰だろう。罪を犯したその人間は、鈍い光を放射状に放つ街灯の真下に佇立して、自らの罪を謝していた。 「私は、人間を冒瀆した。このビルの谷間で。」 コンクリートの歩道の上にも、真っ黒なアスファルトの車道の上にも、雨は蕭々と降りそそいでいた。道は一直線にどこまでも続き、街灯は、道に沿ってどこまでも列をなして立っている。そして、気がつくと、どの街灯の下にも人間が佇っていた。 やがて、懺悔を終えたのか、街灯を後にして、人間達は一斉に歩き始めた。一定の間隔を保ち、あるとも知れぬこの道の果ての行き止まりに向かって、蝙蝠傘をわずかに揺らし、静かに歩いて行く。 長い時間が経って、人間達を冷ややかに見つめていた私の背後に、何者かのかすかな気配を感じた。雨、降り続く、冬の夜のことである
炭俵とは藁で出来た俵の中に炭の詰まった物である。その真っ黒な炭が詰まった炭俵という物が照らしたそこは暗いところであったというのだ。 炭=暗黒の塊が詰まった「炭俵」に照らされることによって、白日の元に「くらきところ」はさらされるのである。 そして、一句において、暗黒によって照らされるにも関わらず、それは照らす、即ち光を当てることによって物を際立たせることと変わりのないことを読者に納得させるため、「炭俵照」以下が「らしてくらきところなる」という平仮名表記にされる。通常の光と違い、照らすことによって「くらきところ」を際立たせる光がここに現れる。 それを、作品世界の人物が見つめている。炭俵が照らし出した「くらきところ」とは、外でもない、自分自身の内部なのではないかと。 「炭‐俵」と言う言葉の持つ物質感が一句にリアリィを与え、読む者を捉えて離さない。 (「亡郷」『荒韻帖』二〇〇三年六月、邑書林)
武馬久仁裕 言葉が重奏し、輻輳し、綾なす双々子俳句の世界の在り方に、代表句とも、問題句ともされる『囁囁記』所収の次の一句を解き明かすことによって、迫ってみようと思う。 風や えりえり らま さばくたに 菫 双々子 日本語のようであり、日本語のようでない不思議な言葉がここにある。まず、「えりえり らま さばくたに」を日本語だとして、句の展開に沿って読んでみよう。 この句を一句たらしめるのに大きな働きをしているのが、「風や」のあとの「えりえり」であろう。これを、日本語の範疇で読もうとすれば、風の吹く有様を「えりえり」という言葉の響きに喩えたオノマトペと言うことになる。 では、「えりえり」と吹く風はどのように吹く風であろうか。「えりえり」から連想される言葉は多くある。「えり」は「縒(よ)る」(「える」とも読む)を、そして「きりきり」を連想させる。さらに、「えりえり」は、喉の奥から絞り出されるような苦しげな響きを持っている。即ち、「えりえり」とは、風が縒られるように強く吹く様をイメージさせ、同時にその風の縒られる音が、苦しさの中人がようやく発する声のイメージへと読む者を誘うのである。 「風や」と切字によって一旦吹き上がった風は「えりえり」と吹き、同時にこの「えりえり」は「らま」に掛かり、「えりえり」と重い荷を負い砂漠を歩むラマを現出し、谷を吹き抜け、菫に到るのである。山路を来て芭蕉の出会った「菫草」とは違う「菫」に。 山路来てなにやらゆかし菫草 芭蕉 この句と姿の似た双々子の一句は、「菫」を木々の生い茂る豊かな日本的自然とは異なる荒涼たる風景の中に咲かせたのである。この菫は、何となく心惹かれる、「山道の片隅にひっそりと咲くさまは、可憐で、慎ましい」(『新日本カラー版大歳時記』(春、248頁)の菫ではない。荒涼たる風景の中に美の象徴として小さいながらも漢字の形同様毅然と咲く「菫」である。芭蕉以来強固なイメージを纏った「菫」を越えた「菫」を、双々子は一句に置くことに成功したのである。 しかし、そのように読んだあとも、読みはそこに落ち着かず、この平仮名分かち書きの「えりえり らま さばくたに」という言葉は、依然として呪文の如く不可解である。だが『囁囁記』の 桐一葉きりしとは掌をのこしけり 遠イエスゆふやけの河渉るは 泥海はありけりとほくなる十字架 を読み、 風や えりえり らま さばくたに 菫 に到った読者は、この平仮名分かち書きの「えりえり らま さばく たに」が、キリストに関係した言葉ではないかと思い至るに違いない。この苦痛に満ちた体内の奥深い所から「えりえり」と絞り出されるような響きを持つ言葉はキリストの最期の言葉にこそふさわしい、と。 聖書を紐解けば、予想に違わず、マタイ伝27‐46にその言葉を見出すのである。「エリ、エリ、レマ(ラマ)、サバクタニ」(その意味は「わが神、わが神、なんぞ我を見棄て給ひし」)(「レマ」と「ラマ」については、注参照)と十字架上のキリストは叫び、やがて息絶えるのである。 そして、「風」は『囁囁記』の「囁囁記Ⅰ」の詞書、 人はみな草なり その麗しさは、すべて野の花の如し 主の息その上に吹けば 草は枯れ、花はしぼむ。 げに人は草なり、 されど――(イザヤ書四〇ノ六-八) によって神の息となる。岩波文庫『イザヤ書(下)』では「霊風」と訳される、神が被造物に生命を与える風なのだ。だが、それはまた神との契約を違えた罪深き人々には死の風でもあった。 キリストの十字架上の言葉「エリ、エリ、レマ(ラマ)、サバクタニ」も神の息=霊風と同じく両義的である。文字通りに取れば、信頼し来たった神への恨みの言葉であるが、それはまた「この詩全体の心は神への信頼であり、苦しむ僕が嘲り笑う敵を前に神に祈る祈りである」(小嶋潤著『聖書小事典』)とされる旧約聖書の「詩編22」の冒頭の言葉でもあった。 このように様々な文化的、時代的、両義的な言葉が「重奏し、輻輳し、綾なす」のが双々子の俳句の形であり、それを「風や」の句がもっともよく体現しているのである。 それ故、この句を一義的に解することは難しい。まず読み取れるのは、風が吹きすさぶ荒野を重荷を負うて行くものの姿であり、そこに咲く一輪の菫の強さ、美しさである。そして、それに重ね合わされてあるのは、風=神の息がその上に吹く十字架上で「エリ エリ ラマ サバクタニ」と、神に向かって苦しさの中呼ばわるキリストの姿であり、キリストの最期の言葉、「エリ エリ ラマ サバクタニ」に双々子が感応し発した言葉、「菫」である。 この場合、「菫」は、「主の息その上に吹けば/草は枯れ、花はしぼむ。/げに人は草なり」と旧約で喩えられた「人」ではなく、キリストの神の愛が形象化されたものではないかと私には思われる。両義的なものを越え、安らぎを与えるものは愛だからである。 双々子は生前、新聞記者の取材時に、次のように語っている。 「少なくとも愛着をもっている季語が、一人の作家にはせいぜい十もあればいいと僕は思います。内容とどうかかわり、いかに思想化していくか。本質的な意味で季語をとらえないと文化には切り込めない」(1997年6月27日、中日新聞夕刊)。 「風や」の一句は、「菫」という言葉=季語によって、文化というものに切り込んだ一句であった。 (注)私の手元に有る『舊新約聖書』(日本聖書協会、1970年)及び『新共同訳聖書―旧約聖書続編つき』(日本聖書協会、2006年)のマタイ伝は「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」(傍線、武馬)となっている。 「風や」の句との齟齬を説明するため、「マルコ伝」では「エロイ、エロイ、ラマ、サバクタニ」になっている聖書もあるので(前者がそうである)、「双々子の音韻上の深い配慮」から、双々子によって「テキストの改変」がなされたとの坂戸惇夫の説がある。(坂戸淳夫「単独者の魂の行方は」『地表 終刊号』2006年) 岩隈直訳註『希和対訳脚註つき新約聖書2マタイ福音書(下)』の脚注によって、λ´αμα(ラマ。へブル語)となっている異本の存在が知られる。また、英訳聖書では、『欽定訳聖書』(1611年)は、Eli,Eli,lamasabachthani、『改訂標準訳聖書』(1952年)は、Eli,Eli,la’ma
Sabach-tha’ni?となっている。共に「ラマ」である。全体を片仮名表記にすれば、「エリ、エリ、ラマ サバクタニ」である。
(初出『豈』44号、2007年3月31日発行。一部加筆) |
||