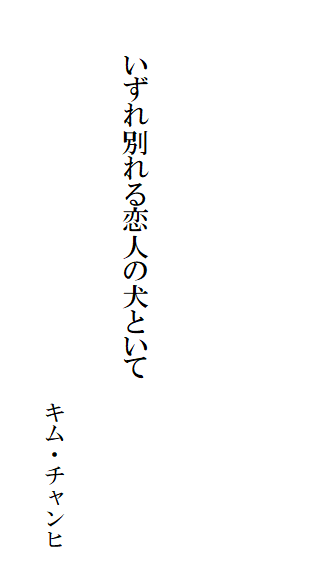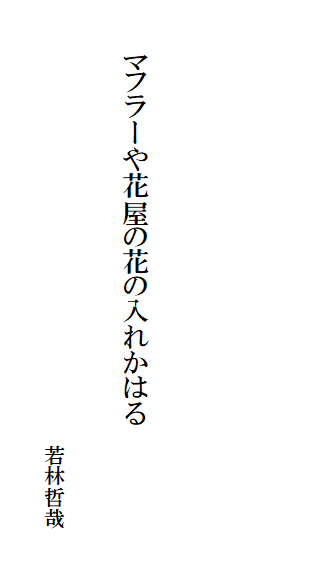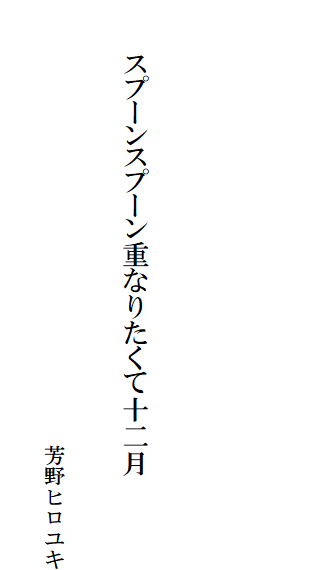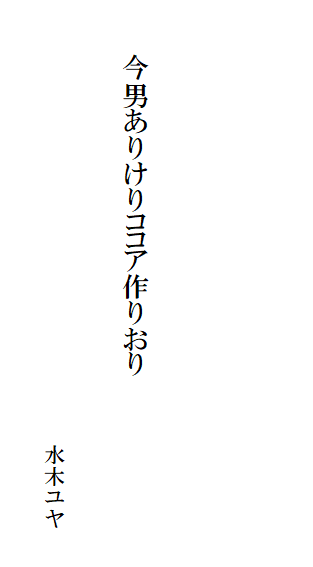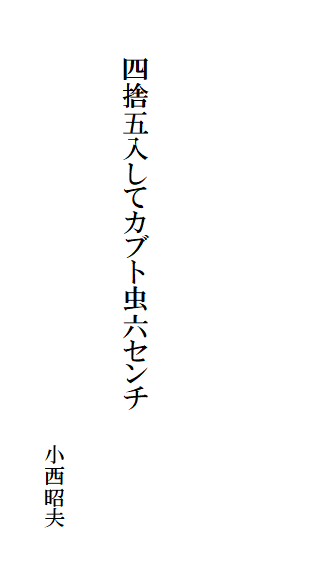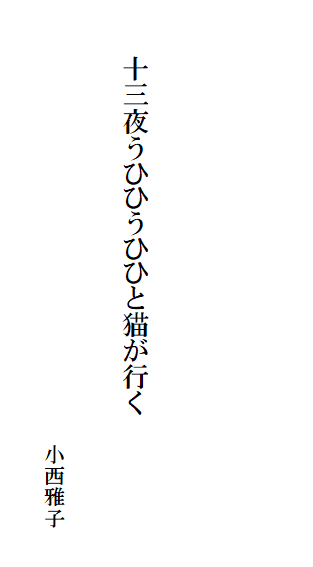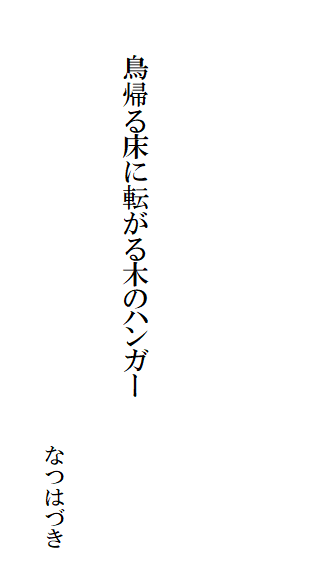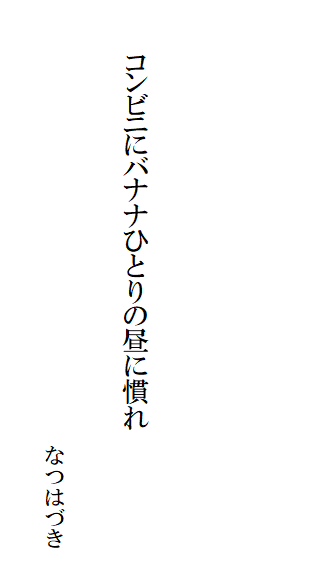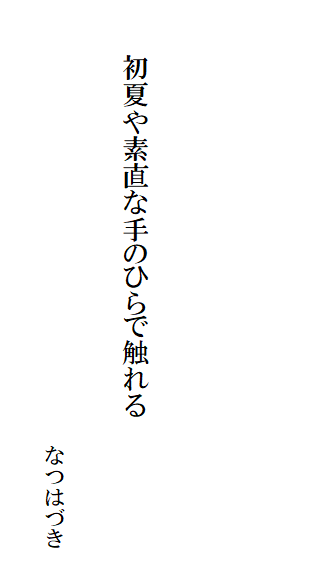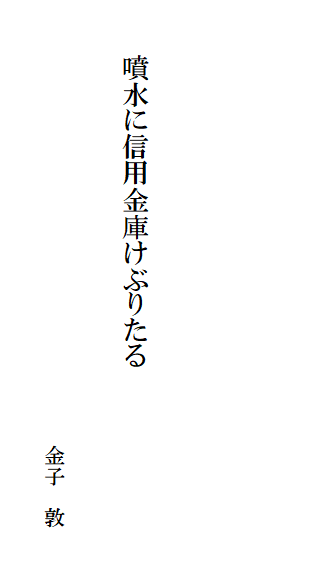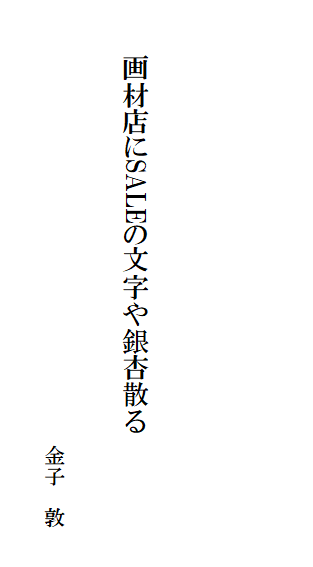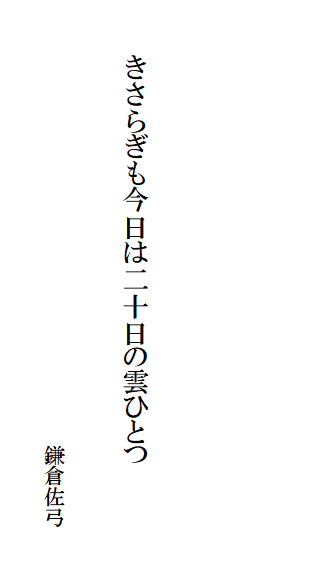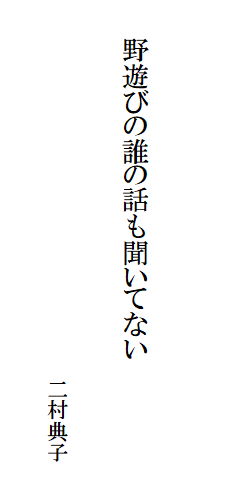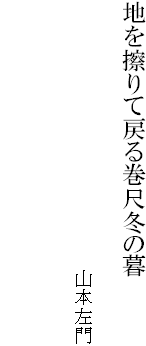| 詩歌なう |
| 俳句紀行 |
| 小川双々子の世界 |
| アートシーン |
| 奥の細道ぼちぼち歩き |
| 俳画&俳句のバックナンバー |
| 新・黎明俳壇 |
|
恋人の犬はいても恋人は今ここにいないのです。恋人の犬と句の中の人物は、静かに恋人が来るのを待っています。恋人のすでにいなくなった世界を想像しながら。もちろん、犬にはあずかり知らぬことです。平穏な日常の一齣です。
(キム・チャンヒ句集『30201』マルコボ.コム、2025年10月14日刊)
「マフラーや」だからマフラーをする季節に変わったということです。それと同時に花屋の花は入れ替わりましたが、この句にはどんな花たちからどんな花たちに入れ替わったかは書かれていません。ただ、花が入れ替わったと書かれているだけです。そこに、読者の想像が入る余地が生まれます。
この花の入れ替わった花屋は、花が入れ替わることによって、日常の世界から日常の世界とは別の世界の花屋に生まれ変りました。これを想像できるかどうかが、読者にとっての分かれ目です。
マフラーをしているこの句中の人物は、マフラーをするという特別の装いによって、この花の入れ替わった世界へ入って行きました。
「マフラーや花屋の花の入れかはる」と、さりげなく言ってのける、若林哲哉のひねりの鮮やかさに喝采です。
(若林哲哉句集『漱口』文學森、2025年6月14日)
「スプーンスプーン」と、どこからともなく聞こえて来ます。 そして、「スプーンスプーン」と重ねて言われると、二つ目の「スプーン」は、具体的なスプーンではなく、スプーンというあるかないか分からないものに思えてきます。こうして「スプーンスプーン」は、食器「スプーン」の意味を超えて呪文となります。 スプーンの形状は、それを見ているとまるで重なることを宿命としているかのようです。 しかし、重なることになんの意味もありません。ただスプーンは重なりたいだけなのです。 それは、十二ヵ月が極まった十二月に発せられるのにふさわしい言葉です。十二月には、全てが終息したくて、「スプーンスプーン」と唱えています。 (芳野ヒロユキ句集『運命のズッキーニ』株式会社シンラ 象の森書房、2025年9月29日)
この句は横書きの句です。 だから、とても分かりやすいです。 ヒマワリ2番でお待ちくださいね 空白の世界 1234 優しくはありますが、ご託宣のごとく窓口で「ヒマワリの2番でお待ちくださいね」と言われました。
「ハイ! ヒマワリの2番ですね。わかりました。でも、ヒマワリの2番ってどこ?」 この句から見えてくるのは、横に並んだ4つの診察室です。ヒ(1番)マ(2番)ワ(3番)リ(4番)です。 マの診察室の前で待たされ、日が暮れて行きます。左から空白の世界へ流れる時間の中、永久にここで待たされることになるでしょう。 私の住んでいる町には、ヒマワリクリニックという医院がありますが、この句とはまったく関係ないと思います。 (芳野ヒロユキ句集『運命のズッキーニ』株式会社シンラ 象の森書房、2025年9月29日)
集中随一の句です。読者に奇妙な快感をもたらす句です。では、この句の子細な分析をしてみましょう。 まず、この句は「今男ありけり」という不自然な言葉で始まります。何が不自然なのでしょう。それは、「今」と過去の伝聞を意味する「けり」の同居です。「けり」は「あったそうだ」です。「今……あったそうだ」ではおかしいです。 では、このおかしな表現が、なぜ許されるのでしょう。それは、「今男ありけり」は、在原業平を主人公とする『伊勢物語』の有名な言い出しの言葉「昔男ありけり」(昔一人の男がいたそうだ)を面影にしているからです。そのため、読者は、『伊勢物語』のパロディかと納得しますが、実は、そこからおかしな時空を生み出してしまったのです。「今一人の男がいたそうだ」という、現在と過去のあいだで宙ぶらりんになった世界です。 そこで、「男」は何をしているかといえば、ココアを作っているのです。「ココア作りおり」です。では、この変な時空でココアを作っている男は、いったい何者なのでしょう。作者は戯れに、今、目の前でココアづくりに勤しんでいる一人の男を、古典の中に放り込んだのです。放り込んで楽しんでいるのです。 かくして、この一人の男は、どこにもない現在と過去のあいだで宙ぶらりんになった世界の中で、永遠の今を、ココア作りという日常的なことにひたすら勤しむ存在となりました。そして、読者はそのようなココアを作り続ける不可解な男にこの句を読んで出会うのです。 これが、この句を読んだときの何ともいえない奇妙な快感の正体です。 (水木ユヤ句集『カメレオンの朝食』ふらんす堂、2025年9月25日)
十五夜より二つ少ない十三夜。それゆえ、ちょっぴりさびしさが漂います。そんな十三夜を猫が、ちょっとご機嫌で独り笑いしながらうひひうひひと行くのです。このちょっと不気味な行動はいったいなんでしょう。まともな回答はできないでしょう。そこがこの句の面白いところです。
でも、私はあえて鑑賞します。これは、漱石の名前のない猫がビールを飲んでほろ酔いかげんで月夜を行くところだと。(この句では『吾輩は猫である』と同様、猫は擬人化されています。擬人化されているからこそ、この句の世界は不気味なのです。)
このあと、猫は水甕に落ちて達観して死んで行くわけですが、死出への道をそれとは知らずご機嫌で行く猫の道行です。
「(勝手から―武馬)出ると御月様今晩はと挨拶したくなる。どうも愉快だ。/陶然とはこんな事を云ふのだらうと思ひながら、…(略)…しまりのない足をいゝ加減に運ばせてゆくと、……(以下略)」(『吾輩は猫である』新潮文庫、467頁)
(小西雅子句集『コキコキ』(創風社、2025年7月12日)
集中随一の句です。読者は、空の彼方には北へ帰る鳥を見、人の生活する地上の一室には、床に転がる木のハンガーを見ます。そして、木のハンガーをよく見ますと、翼を左右に広げたような形が見えてきます。さらに言えば、「床に転がる」という即物的な言い方によって、この木のハンガーが北へ帰ろうとして鳥に変身しそこない、いのちない木からなるハンガーに返った後の哀れな姿が見えてきます。見えないものを見せてくれる句です。 (『人魚のころ』朔出版、2025年6月)
(『人魚のころ』朔出版、2025年6月)
「初夏」は「しょか」でなく「はつなつ」であることが、この句の味噌です。「初時雨(はつしぐれ)」「初雪(はつゆき)」、「初(はつ)」がつくと言葉は美しくなります。初は、まだ何ものにも汚されていない、無垢の美しさをたたえています。初夏(はつなつ)は、そんな汚れのないいのち輝く無垢な夏です。ですから、初夏の世界にある、どんなものにも汚れのない無垢な素直な手のひらで触れるのです。美しい句です。
(『人魚のころ』朔出版、2025年6月)
(金子敦句集『ポケットの底』ふらんす堂、2025年5月)
そのきさらぎも今日は二十日、冬の寒さを脱ぎ捨てるころ。脱ぎ捨て始めたきさらぎの二十日の白い雲が春めいたおだやかな光をはなちながら、青い空に浮かんでいます。
ひとつという言葉が空の広さとさびしさをきわだたせています。伸びやかな春の到来を迎える美しい句です。
(鎌倉佐弓句集『雲へ拍手(APPLAUSE FOR A CLOUD)』Black Ocean、2025年)
上五の「さくら」が、「桜」でなく、ひらがなになっているのには2つ理由があります。1つは、さくらの愛らしさを表現するためです。そのため、「怖くなっている」と響き合います。「こわい」でなく「怖い」と本当に怖い漢字になっています。
もう1つは、ひらがな「さ」「く」「ら」が、花びら1つ1つを表現していることです。また「さくら」の「さく」は「咲く」と掛けられています。ですから「さくら」は「散る」ととても響き合っています。
そして、大切なことは、「さくら」は、桜のいのちの現れであることで
併記されているジェームス・シェイの英訳も紹介します。
Third day
of cherry blossoms
I’m
afraid
to see
them scatter
(鎌倉佐弓句集『雲へ拍手(APPLAUSE FOR A CLOUD)』Black Ocean、2025年
ご参考までに、併記されているジェームス・シェイの英訳も紹介します
(鎌倉佐弓句集『雲へ拍手(APPLAUSE FOR A CLOUD)』Black Ocean、2025年)
落胆の句と言えば、同じ作者に「一本のビールも冷えておらぬなり」があります。この句については、『新・黎明俳壇』12号の「名句暗記カード」で紹介しました。 小判草の花言葉は「大金持ち」だそうです。
(「続チンピラ」『俳句の宙2024 精選アンソロジー』本阿弥書店、2024年)
しかし、「にわとり」に声をかけますと、にわとりはすぐさま勤労者に変貌します。それも、休日もなく働きつづける勤労者に。前書きの「今日も元気に働いてくれます。」の「今日も」の「も」と「働いてくれます」の「くれます」が微妙です。
(「続チンピラ」『俳句の宙2024 精選アンソロジー』本阿弥書店、2024年)
これを、端から見れば、なんと間の抜けたことをしているの! せっかくみんなで姿を消してかくれんぼして楽しく遊んでいるのに、ということになります。
前書きの「かくれんぼとは何と淋しい遊びでしょう。」は、その両方を見た、作者「小西昭夫」の感慨です。
今回から、小西さんのちょっと変わったはすかいのユーモア俳句を3回連続でご紹介します。小西ワールドをどうぞお楽しみください。
(「続チンピラ」『俳句の宙2024 精選アンソロジー』本阿弥書店、2024年)
春になって凍っていた東京が解けて液化し、そしてついには気化して無くなってしまいます。その液化し気化し跡形もなくなった東京を見下し、鳥瞰し、鳥は悠々と故郷に帰っていくのです。「鳥帰る」が、句の天辺の上五にありますので、この光景が見て取れます。 これはこれでよいと思いますが、私にはこの句が出来上がるまでに次のような過程があったのではないかと想像しました。 まず、「東京液化」を見たとき、昔あった「東京液化ガス」という会社を思い出しました。そして、そこから「気化」を「ガス」とルビを振って読んでいました。「とりかえるとうきょうえきかそしてがす」です。 そう読んだとき、「取り替える東京液化そしてガス」が見えてきました。しかし、「そして」が不自然です。そこで、私は、作者の脳裏に最初浮かんだのは、「取り替える東京液化ガスボンベ」ではないかと思ったわけです。「ガスボンベ」を「そして気化」にし、季語がないので「取り替える」を「鳥帰る」にし、「鳥帰る東京液化そして気化」と最終的に推敲されたのではないかと推理したわけです。 エネルギーの大量消費の果てに消滅した東京と春に北方の地で子孫を残すために帰る渡り鳥との取り合わせである「鳥帰る東京液化そして気化」の完成です。もちろん、この句には「東京液化ガス」という現実の会社名が面影にありますので、テーマほどには深刻にならず、風刺の効いたおかし味が漂っています。
教室に貼られた賞状は、一枚でなく二枚という淋しさ。そして、ときは小六月(旧暦十月・立冬の月)。それと呼ぶにふさわしい小さな六月のような陽気の日でした。 二と六という控え目な数字を使って、控え目な何ごともない今日の好き日をしみじみと描いている句です。
(2024年東海地区現代俳句賞応募作より)
「あれから」と、まず、ひらがなで書き起こされます。ひらがなは漢字とくらべて漠然とした感じがするところが味噌です。 次いで、百年という時間が、明確に漢字で表現されています。百年の次は白秋です。
「目」は「百」と「白」を受けての「目」です。漢字の形からも句は自然に展開します。
眼目は、「眼」になっていないことと、「覚ます」もしくは「醒ます」ではなく「さます」になっていることです。白秋の透明さを表す「に・をさます」の中の「目」が、はっきりと読者に迫ってきます。
この句は、「あれから」という、武馬が「あいまい表現」と呼ぶ言葉さばきによって、読者をさりげなく、日常の世界とは違う世界に誘い込みます。誘い込まれた読者は、この句の中の人物と一緒に、百年ののちに目をさますのです。
そこは、それはそれは美しい白秋の季節でありました。透明感あふれる句です。

この句の眼目は、子牛であるところです。子牛たちは、トラックに載せられた分だけ少し天に近づきました。しかし、子牛です。成牛ほどには天にとどきません。せめて成牛ほどには天とどけと願いたいところですが、詮無いことです。聖なる天はいよいよ高くあるばかりです。そんな子牛たちが何も知らずに何処へともなく売られて行きます。一頭ではなく数頭であることが一層哀れを誘います。
(第21回現代俳句東海大会。2024年11月17日)
(山本純子句集『オノマトペ』2024年12月1日刊、象の森書房)

(川島由紀子句集『アガパンサスの朝』朔出版、2024年10月23日発行)
この句を一読して、いったいこんな素敵な句をどんな人が作ったのだろうと、思いました。俳句にはめずらしい明るい抒情です。
ゲーテのミニヨンの歌を思いました。はるかな異国へのあこがれが爽やかに描かれています。
君よ知るや南の国
「麦熟れて」という言葉の背後に「麦秋」(麦と秋)という言葉があることと相まって、「稲熟れて」とは違った、湿潤なアジア的世界ではなく、乾いた西欧的世界が心地よく迫ってきます。
(第21回現代俳句東海大会。2024年11月17日)
あのぺらぺらながらも腰のある白い紙に、記号のような文字列の印字されたレシート。それをチェックするのではなく、意味ある文のように「熟読してしまう」ことの不思議さ。しかも、熟読する日が「獺祭忌」という獣(かわうそ)の祭の忌と名付けられた不思議な忌日であるという二重の不思議さが、読者に迫って来ます。この二重の不思議さが綯(ない)交ぜになっているのが、この句の眼目です。本来ならば、その不思議な世界を体で感じ取るだけでもよいのです。獺祭忌の意味を事細かに説明してしまうことがはばかられる句なのです。
しかしあえて言いましょう。
獺祭忌は、正岡子規の忌日9月19日です。子規の晩年の随筆『仰臥漫録』には、毎日何を食べたか、口に入れたか克明に記されています。あたかもスーパーのレシートのごとく。しかし、それが、彼の雅俗混淆のリアルな世界であったと思います。季節の食べ物は、たちどころに彼の脳裏に古今の名句を思い起こさせたことでしょう。
死の1年ほど前の明治34年9月10日の記事を読んでみます。
「 便通間にあはず 繃帯取換
朝飯 ぬく飯二椀 佃煮 紅茶一杯 菓子パン一つ
便通
午飯 粥いも入り三椀 松魚のさしみ みそ汁葱茄子 つくだ煮 梨二つ 林
間食 焼栗八、九個 ゆで栗三、四個 煎餅四、五枚 菓子パン六、七個
夕飯 いも粥三椀 おこぜ豆腐の湯あげ おこぜ鱠 キヤベツひたし物 梨二切 林檎一つ」
こんな記述が毎日続くのです。まるでスーパーのレシートです。しかも、このレシートの中はなんと生々しく、また生き生きしていることでしょうか。読み続けても飽きない自分の命をも包み込んだ森羅万象を映し出すような世界がここにあります。レシートが、私たちの熟読を誘うのも、ひょっとしてそのためかもしれません。
歳時記に載っていてもおかしくない句です。
(第21回現代俳句東海大会。2024年
姉は全てにおいて一番の存在です。そして、妹たちには、眩しい存在です。その輝くばかりの姉が来て桃を剝きます。もちろん沢山の桃の中の一番きれいな桃を剥きます。そして、剥かれた桃からは、至高の美がこの世に現れるのです。見事な句です。
(中日総合俳句会8月例会。2024年8月11日
何のことを思い出したのだろう。きっと楽しいことに違いない。思い出し笑いだから。しかし、母の下で安らかに昼寝をしているこの子をとりまく世界は、果たして楽しい世界であろうか。私は、楽しい世界であることを切に祈りたい。
(中日総合俳句会8月例会。2024年8月11日)
「必ず咲く夏の花」ではなく、「必ずの夏の花」と書かれることによって、俳句になりました。「必ず咲く夏の花」と比べて「必ずの夏の花」とは、なんと読みにくい、屈折したもの言いでしょう。俳句の言葉で言えば、「必ずの夏の花」と、表現がひねられているのです。ひねられることによって、この原子炉に必ず咲くはずの夏の花は、不吉な、尋常でない夏の花であることを読者に予感させます。いったい膨大な核エネルギーの生れる原子炉に咲く「必ずの夏の花」は、どんな美しい、もしくは異様な姿・形をした夏の花であることでしょう。想像力を掻き立てられます。最後に申し上げます。「必ずの」を読み飛ばし、「夏の花」を原民喜の小説「夏の花」に短絡させることだけは止めてください。 (大井恒行『句集 水月伝』2024年4月23日、ふらんす堂)
句集『三月』はこの句からはじまります。
野遊びの誰の話も聞いてない
読者はこの句を読むと不思議な感覚に誘われることでしょう。『三月』は、このような句によく出会うので、そんな不思議な感覚に私は酔い痴れ、読み続けました。では、この不思議な感覚はどうしておこるのか、自分自身の感覚を見つめてみましょう。
「野遊びの」までは、どおってことはありません。「誰の話も」も少し変ですが、読むのに支障はありません。ところが「聞いてない」と書かれると、自分の感覚が横に一回転したように感じられ、句の流れについていけなくなります。
そこで、もう一度読みます。相変わらず句の流れについていけませんが、何か未体験の感覚で面白いです。句の中で浮かんでいるようです。
それは、「野遊びの誰の話も聞こえない」と無意識の内に期待するところがあったからです。
言い換えれば、現実の句は、「野遊びの誰の話も」の後「聞こえない」とせずに「聞いてない」と、ちょっとひねられ、外されているからです。
「聞いていない」とひねりはずされることによって、野遊びしながら語らっている人たちを見ている人物が突然現れます。
では、「野遊びの誰の話も聞いてない」人物とはいったいどのような人物なのでしょう。
この俳句の中には、はっきりとしたイメージをもって存在しない人物です。
そして、謎は深まります。
その人物が「野遊びの誰の話も聞いてない」のですから、当然、野遊びの人たちの語らっていたことが何かわかりません。
このように、一見春の長閑な野遊びの光景を詠んだ句のように見えて、実は、何もかもはっきりしない世界が現れるのです。
この謎めいた世界が、私たちの住んでいる長閑な野遊びの世界の本当の姿かもしれません。
次の句もそうです。『三月』の三番目、四番目の句です。
鳥の巣へ百歩手前の静かな日
近所とはどこまで香る梅の花
鳥の句は、「鳥の巣へ百歩手前の」まではすんなり分かりますが、「静かな日」とひねられています。
ここで軽いめまいを読者は体験します。そのめまいの果てに鳥の巣と百歩へだてた静かな日との緊迫した世界が現れます。百歩より狭くなれば修羅の日とかすかもしれないのです。
近所の句は、鳥の巣の句もそうですが、「野遊びの誰の話も聞いてない」と同じ言葉さばきによってできています。
野遊びの誰の話も
誰の話も聞いてない
野遊びの句は、このように、「誰の話も」が上と下の両方に掛かっています。そして、「誰の話も」でひねられているのが見てとれます。これがこの句の不思議感を生み出す構造的秘密です。
「近所」の句も同じです。「どこまで」が、上と下の両方に掛かるように書かれています。
近所とはどこまで
どこまで香る梅の花
「どこまで」でひねられているわけです。このひねりによって、読者は一瞬宙ぶらりんの感じを体験します。
このように二村典子の世界は、すこし不安定なのです。
世界を少し不安定に描く面白さを、われわれ(読者)の前に見せてくれるのが『三月』です。
先の三句は、真中の言葉が上と下に掛かり、真中の言葉でひねられていたのですが、その他にも、さまざなは言葉さばきが使われています。そのような句をもう少し紹介して、このとりあえずの句集評を終わります。
梅雨空の市バス前扉から降りる
七月の箱の内寸不正確
かばんには青無花果とジェネリック
(二村典子句集『三月』黎明書房、2024年3月25日)
この句の眼目は、子牛であるところです。子牛たちは、トラックに載せられた分だけ少し天に近づきました。しかし、子牛です。成牛ほどには天にとどきません。せめて成牛ほどには天とどけと願いたいところですが、詮無いことです。聖なる天はいよいよ高くあるばかりです。そんな子牛たちが何も知らずに何処へともなく売られて行きます。一頭ではなく数頭であることが一層哀れを誘います。
(第21回現代俳句東海大会。2024年11月17日)
(山本純子句集『オノマトペ』2024年12月1日刊、象の森書房)

(川島由紀子句集『アガパンサスの朝』朔出版、2024年10月23日発行)
この句を一読して、いったいこんな素敵な句をどんな人が作ったのだろうと、思いました。俳句にはめずらしい明るい抒情です。
ゲーテのミニヨンの歌を思いました。はるかな異国へのあこがれが爽やかに描かれています。
君よ知るや南の国
「麦熟れて」という言葉の背後に「麦秋」(麦と秋)という言葉があることと相まって、「稲熟れて」とは違った、湿潤なアジア的世界ではなく、乾いた西欧的世界が心地よく迫ってきます。
(第21回現代俳句東海大会。2024年11月17日)
あのぺらぺらながらも腰のある白い紙に、記号のような文字列の印字されたレシート。それをチェックするのではなく、意味ある文のように「熟読してしまう」ことの不思議さ。しかも、熟読する日が「獺祭忌」という獣(かわうそ)の祭の忌と名付けられた不思議な忌日であるという二重の不思議さが、読者に迫って来ます。この二重の不思議さが綯(ない)交ぜになっているのが、この句の眼目です。本来ならば、その不思議な世界を体で感じ取るだけでもよいのです。獺祭忌の意味を事細かに説明してしまうことがはばかられる句なのです。
しかしあえて言いましょう。
獺祭忌は、正岡子規の忌日9月19日です。子規の晩年の随筆『仰臥漫録』には、毎日何を食べたか、口に入れたか克明に記されています。あたかもスーパーのレシートのごとく。しかし、それが、彼の雅俗混淆のリアルな世界であったと思います。季節の食べ物は、たちどころに彼の脳裏に古今の名句を思い起こさせたことでしょう。
死の1年ほど前の明治34年9月10日の記事を読んでみます。
「 便通間にあはず 繃帯取換
朝飯 ぬく飯二椀 佃煮 紅茶一杯 菓子パン一つ
便通
午飯 粥いも入り三椀 松魚のさしみ みそ汁葱茄子 つくだ煮 梨二つ 林
間食 焼栗八、九個 ゆで栗三、四個 煎餅四、五枚 菓子パン六、七個
夕飯 いも粥三椀 おこぜ豆腐の湯あげ おこぜ鱠 キヤベツひたし物 梨二切 林檎一つ」
こんな記述が毎日続くのです。まるでスーパーのレシートです。しかも、このレシートの中はなんと生々しく、また生き生きしていることでしょうか。読み続けても飽きない自分の命をも包み込んだ森羅万象を映し出すような世界がここにあります。レシートが、私たちの熟読を誘うのも、ひょっとしてそのためかもしれません。
歳時記に載っていてもおかしくない句です。
(第21回現代俳句東海大会。2024年
姉は全てにおいて一番の存在です。そして、妹たちには、眩しい存在です。その輝くばかりの姉が来て桃を剝きます。もちろん沢山の桃の中の一番きれいな桃を剥きます。そして、剥かれた桃からは、至高の美がこの世に現れるのです。見事な句です。
(中日総合俳句会8月例会。2024年8月11日
何のことを思い出したのだろう。きっと楽しいことに違いない。思い出し笑いだから。しかし、母の下で安らかに昼寝をしているこの子をとりまく世界は、果たして楽しい世界であろうか。私は、楽しい世界であることを切に祈りたい。
(中日総合俳句会8月例会。2024年8月11日)
「必ず咲く夏の花」ではなく、「必ずの夏の花」と書かれることによって、俳句になりました。「必ず咲く夏の花」と比べて「必ずの夏の花」とは、なんと読みにくい、屈折したもの言いでしょう。俳句の言葉で言えば、「必ずの夏の花」と、表現がひねられているのです。ひねられることによって、この原子炉に必ず咲くはずの夏の花は、不吉な、尋常でない夏の花であることを読者に予感させます。いったい膨大な核エネルギーの生れる原子炉に咲く「必ずの夏の花」は、どんな美しい、もしくは異様な姿・形をした夏の花であることでしょう。想像力を掻き立てられます。最後に申し上げます。「必ずの」を読み飛ばし、「夏の花」を原民喜の小説「夏の花」に短絡させることだけは止めてください。 (大井恒行『句集 水月伝』2024年4月23日、ふらんす堂)
句集『三月』はこの句からはじまります。
野遊びの誰の話も聞いてない
読者はこの句を読むと不思議な感覚に誘われることでしょう。『三月』は、このような句によく出会うので、そんな不思議な感覚に私は酔い痴れ、読み続けました。では、この不思議な感覚はどうしておこるのか、自分自身の感覚を見つめてみましょう。
「野遊びの」までは、どおってことはありません。「誰の話も」も少し変ですが、読むのに支障はありません。ところが「聞いてない」と書かれると、自分の感覚が横に一回転したように感じられ、句の流れについていけなくなります。
そこで、もう一度読みます。相変わらず句の流れについていけませんが、何か未体験の感覚で面白いです。句の中で浮かんでいるようです。
それは、「野遊びの誰の話も聞こえない」と無意識の内に期待するところがあったからです。
言い換えれば、現実の句は、「野遊びの誰の話も」の後「聞こえない」とせずに「聞いてない」と、ちょっとひねられ、外されているからです。
「聞いていない」とひねりはずされることによって、野遊びしながら語らっている人たちを見ている人物が突然現れます。
では、「野遊びの誰の話も聞いてない」人物とはいったいどのような人物なのでしょう。
この俳句の中には、はっきりとしたイメージをもって存在しない人物です。
そして、謎は深まります。
その人物が「野遊びの誰の話も聞いてない」のですから、当然、野遊びの人たちの語らっていたことが何かわかりません。
このように、一見春の長閑な野遊びの光景を詠んだ句のように見えて、実は、何もかもはっきりしない世界が現れるのです。
この謎めいた世界が、私たちの住んでいる長閑な野遊びの世界の本当の姿かもしれません。
次の句もそうです。『三月』の三番目、四番目の句です。
鳥の巣へ百歩手前の静かな日
近所とはどこまで香る梅の花
鳥の句は、「鳥の巣へ百歩手前の」まではすんなり分かりますが、「静かな日」とひねられています。
ここで軽いめまいを読者は体験します。そのめまいの果てに鳥の巣と百歩へだてた静かな日との緊迫した世界が現れます。百歩より狭くなれば修羅の日とかすかもしれないのです。
近所の句は、鳥の巣の句もそうですが、「野遊びの誰の話も聞いてない」と同じ言葉さばきによってできています。
野遊びの誰の話も 誰の話も聞いてない
野遊びの句は、このように、「誰の話も」が上と下の両方に掛かっています。そして、「誰の話も」でひねられているのが見てとれます。これがこの句の不思議感を生み出す構造的秘密です。
「近所」の句も同じです。「どこまで」が、上と下の両方に掛かるように書かれています。
近所とはどこまで どこまで香る梅の花
「どこまで」でひねられているわけです。このひねりによって、読者は一瞬宙ぶらりんの感じを体験します。
このように二村典子の世界は、すこし不安定なのです。
世界を少し不安定に描く面白さを、われわれ(読者)の前に見せてくれるのが『三月』です。
先の三句は、真中の言葉が上と下に掛かり、真中の言葉でひねられていたのですが、その他にも、さまざなは言葉さばきが使われています。そのような句をもう少し紹介して、このとりあえずの句集評を終わります。
梅雨空の市バス前扉から降りる
七月の箱の内寸不正確
かばんには青無花果とジェネリック
(二村典子句集『三月』黎明書房、2024年3月25日)
この句の眼目は、子牛であるところです。子牛たちは、トラックに載せられた分だけ少し天に近づきました。しかし、子牛です。成牛ほどには天にとどきません。せめて成牛ほどには天とどけと願いたいところですが、詮無いことです。聖なる天はいよいよ高くあるばかりです。そんな子牛たちが何も知らずに何処へともなく売られて行きます。一頭ではなく数頭であることが一層哀れを誘います。
(第21回現代俳句東海大会。2024年11月17日)
(山本純子句集『オノマトペ』2024年12月1日刊、象の森書房)

(川島由紀子句集『アガパンサスの朝』朔出版、2024年10月23日発行)
この句を一読して、いったいこんな素敵な句をどんな人が作ったのだろうと、思いました。俳句にはめずらしい明るい抒情です。
ゲーテのミニヨンの歌を思いました。はるかな異国へのあこがれが爽やかに描かれています。
君よ知るや南の国
「麦熟れて」という言葉の背後に「麦秋」(麦と秋)という言葉があることと相まって、「稲熟れて」とは違った、湿潤なアジア的世界ではなく、乾いた西欧的世界が心地よく迫ってきます。
(第21回現代俳句東海大会。2024年11月17日)
あのぺらぺらながらも腰のある白い紙に、記号のような文字列の印字されたレシート。それをチェックするのではなく、意味ある文のように「熟読してしまう」ことの不思議さ。しかも、熟読する日が「獺祭忌」という獣(かわうそ)の祭の忌と名付けられた不思議な忌日であるという二重の不思議さが、読者に迫って来ます。この二重の不思議さが綯(ない)交ぜになっているのが、この句の眼目です。本来ならば、その不思議な世界を体で感じ取るだけでもよいのです。獺祭忌の意味を事細かに説明してしまうことがはばかられる句なのです。
しかしあえて言いましょう。
獺祭忌は、正岡子規の忌日9月19日です。子規の晩年の随筆『仰臥漫録』には、毎日何を食べたか、口に入れたか克明に記されています。あたかもスーパーのレシートのごとく。しかし、それが、彼の雅俗混淆のリアルな世界であったと思います。季節の食べ物は、たちどころに彼の脳裏に古今の名句を思い起こさせたことでしょう。
死の1年ほど前の明治34年9月10日の記事を読んでみます。
「 便通間にあはず 繃帯取換
朝飯 ぬく飯二椀 佃煮 紅茶一杯 菓子パン一つ
便通
午飯 粥いも入り三椀 松魚のさしみ みそ汁葱茄子 つくだ煮 梨二つ 林
間食 焼栗八、九個 ゆで栗三、四個 煎餅四、五枚 菓子パン六、七個
夕飯 いも粥三椀 おこぜ豆腐の湯あげ おこぜ鱠 キヤベツひたし物 梨二切 林檎一つ」
こんな記述が毎日続くのです。まるでスーパーのレシートです。しかも、このレシートの中はなんと生々しく、また生き生きしていることでしょうか。読み続けても飽きない自分の命をも包み込んだ森羅万象を映し出すような世界がここにあります。レシートが、私たちの熟読を誘うのも、ひょっとしてそのためかもしれません。
歳時記に載っていてもおかしくない句です。
(第21回現代俳句東海大会。2024年
姉は全てにおいて一番の存在です。そして、妹たちには、眩しい存在です。その輝くばかりの姉が来て桃を剝きます。もちろん沢山の桃の中の一番きれいな桃を剥きます。そして、剥かれた桃からは、至高の美がこの世に現れるのです。見事な句です。
(中日総合俳句会8月例会。2024年8月11日
何のことを思い出したのだろう。きっと楽しいことに違いない。思い出し笑いだから。しかし、母の下で安らかに昼寝をしているこの子をとりまく世界は、果たして楽しい世界であろうか。私は、楽しい世界であることを切に祈りたい。
(中日総合俳句会8月例会。2024年8月11日)
「必ず咲く夏の花」ではなく、「必ずの夏の花」と書かれることによって、俳句になりました。「必ず咲く夏の花」と比べて「必ずの夏の花」とは、なんと読みにくい、屈折したもの言いでしょう。俳句の言葉で言えば、「必ずの夏の花」と、表現がひねられているのです。ひねられることによって、この原子炉に必ず咲くはずの夏の花は、不吉な、尋常でない夏の花であることを読者に予感させます。いったい膨大な核エネルギーの生れる原子炉に咲く「必ずの夏の花」は、どんな美しい、もしくは異様な姿・形をした夏の花であることでしょう。想像力を掻き立てられます。最後に申し上げます。「必ずの」を読み飛ばし、「夏の花」を原民喜の小説「夏の花」に短絡させることだけは止めてください。 (大井恒行『句集 水月伝』2024年4月23日、ふらんす堂)
句集『三月』はこの句からはじまります。
野遊びの誰の話も聞いてない
読者はこの句を読むと不思議な感覚に誘われることでしょう。『三月』は、このような句によく出会うので、そんな不思議な感覚に私は酔い痴れ、読み続けました。では、この不思議な感覚はどうしておこるのか、自分自身の感覚を見つめてみましょう。
「野遊びの」までは、どおってことはありません。「誰の話も」も少し変ですが、読むのに支障はありません。ところが「聞いてない」と書かれると、自分の感覚が横に一回転したように感じられ、句の流れについていけなくなります。
そこで、もう一度読みます。相変わらず句の流れについていけませんが、何か未体験の感覚で面白いです。句の中で浮かんでいるようです。
それは、「野遊びの誰の話も聞こえない」と無意識の内に期待するところがあったからです。
言い換えれば、現実の句は、「野遊びの誰の話も」の後「聞こえない」とせずに「聞いてない」と、ちょっとひねられ、外されているからです。
「聞いていない」とひねりはずされることによって、野遊びしながら語らっている人たちを見ている人物が突然現れます。
では、「野遊びの誰の話も聞いてない」人物とはいったいどのような人物なのでしょう。
この俳句の中には、はっきりとしたイメージをもって存在しない人物です。
そして、謎は深まります。
その人物が「野遊びの誰の話も聞いてない」のですから、当然、野遊びの人たちの語らっていたことが何かわかりません。
このように、一見春の長閑な野遊びの光景を詠んだ句のように見えて、実は、何もかもはっきりしない世界が現れるのです。
この謎めいた世界が、私たちの住んでいる長閑な野遊びの世界の本当の姿かもしれません。
次の句もそうです。『三月』の三番目、四番目の句です。
鳥の巣へ百歩手前の静かな日
近所とはどこまで香る梅の花
鳥の句は、「鳥の巣へ百歩手前の」まではすんなり分かりますが、「静かな日」とひねられています。
ここで軽いめまいを読者は体験します。そのめまいの果てに鳥の巣と百歩へだてた静かな日との緊迫した世界が現れます。百歩より狭くなれば修羅の日とかすかもしれないのです。
近所の句は、鳥の巣の句もそうですが、「野遊びの誰の話も聞いてない」と同じ言葉さばきによってできています。
野遊びの誰の話も 誰の話も聞いてない
野遊びの句は、このように、「誰の話も」が上と下の両方に掛かっています。そして、「誰の話も」でひねられているのが見てとれます。これがこの句の不思議感を生み出す構造的秘密です。
「近所」の句も同じです。「どこまで」が、上と下の両方に掛かるように書かれています。
近所とはどこまで どこまで香る梅の花
「どこまで」でひねられているわけです。このひねりによって、読者は一瞬宙ぶらりんの感じを体験します。
このように二村典子の世界は、すこし不安定なのです。
世界を少し不安定に描く面白さを、われわれ(読者)の前に見せてくれるのが『三月』です。
先の三句は、真中の言葉が上と下に掛かり、真中の言葉でひねられていたのですが、その他にも、さまざなは言葉さばきが使われています。そのような句をもう少し紹介して、このとりあえずの句集評を終わります。
梅雨空の市バス前扉から降りる
七月の箱の内寸不正確
かばんには青無花果とジェネリック
(二村典子句集『三月』黎明書房、2024年3月25日)
この句の眼目は、子牛であるところです。子牛たちは、トラックに載せられた分だけ少し天に近づきました。しかし、子牛です。成牛ほどには天にとどきません。せめて成牛ほどには天とどけと願いたいところですが、詮無いことです。聖なる天はいよいよ高くあるばかりです。そんな子牛たちが何も知らずに何処へともなく売られて行きます。一頭ではなく数頭であることが一層哀れを誘います。
(第21回現代俳句東海大会。2024年11月17日)
(山本純子句集『オノマトペ』2024年12月1日刊、象の森書房)

(川島由紀子句集『アガパンサスの朝』朔出版、2024年10月23日発行)
この句を一読して、いったいこんな素敵な句をどんな人が作ったのだろうと、思いました。俳句にはめずらしい明るい抒情です。
ゲーテのミニヨンの歌を思いました。はるかな異国へのあこがれが爽やかに描かれています。
君よ知るや南の国
「麦熟れて」という言葉の背後に「麦秋」(麦と秋)という言葉があることと相まって、「稲熟れて」とは違った、湿潤なアジア的世界ではなく、乾いた西欧的世界が心地よく迫ってきます。
(第21回現代俳句東海大会。2024年11月17日)
あのぺらぺらながらも腰のある白い紙に、記号のような文字列の印字されたレシート。それをチェックするのではなく、意味ある文のように「熟読してしまう」ことの不思議さ。しかも、熟読する日が「獺祭忌」という獣(かわうそ)の祭の忌と名付けられた不思議な忌日であるという二重の不思議さが、読者に迫って来ます。この二重の不思議さが綯(ない)交ぜになっているのが、この句の眼目です。本来ならば、その不思議な世界を体で感じ取るだけでもよいのです。獺祭忌の意味を事細かに説明してしまうことがはばかられる句なのです。
しかしあえて言いましょう。
獺祭忌は、正岡子規の忌日9月19日です。子規の晩年の随筆『仰臥漫録』には、毎日何を食べたか、口に入れたか克明に記されています。あたかもスーパーのレシートのごとく。しかし、それが、彼の雅俗混淆のリアルな世界であったと思います。季節の食べ物は、たちどころに彼の脳裏に古今の名句を思い起こさせたことでしょう。
死の1年ほど前の明治34年9月10日の記事を読んでみます。
「 便通間にあはず 繃帯取換
朝飯 ぬく飯二椀 佃煮 紅茶一杯 菓子パン一つ
便通
午飯 粥いも入り三椀 松魚のさしみ みそ汁葱茄子 つくだ煮 梨二つ 林
間食 焼栗八、九個 ゆで栗三、四個 煎餅四、五枚 菓子パン六、七個
夕飯 いも粥三椀 おこぜ豆腐の湯あげ おこぜ鱠 キヤベツひたし物 梨二切 林檎一つ」
こんな記述が毎日続くのです。まるでスーパーのレシートです。しかも、このレシートの中はなんと生々しく、また生き生きしていることでしょうか。読み続けても飽きない自分の命をも包み込んだ森羅万象を映し出すような世界がここにあります。レシートが、私たちの熟読を誘うのも、ひょっとしてそのためかもしれません。
歳時記に載っていてもおかしくない句です。
(第21回現代俳句東海大会。2024年
姉は全てにおいて一番の存在です。そして、妹たちには、眩しい存在です。その輝くばかりの姉が来て桃を剝きます。もちろん沢山の桃の中の一番きれいな桃を剥きます。そして、剥かれた桃からは、至高の美がこの世に現れるのです。見事な句です。
(中日総合俳句会8月例会。2024年8月11日
何のことを思い出したのだろう。きっと楽しいことに違いない。思い出し笑いだから。しかし、母の下で安らかに昼寝をしているこの子をとりまく世界は、果たして楽しい世界であろうか。私は、楽しい世界であることを切に祈りたい。
(中日総合俳句会8月例会。2024年8月11日)
「必ず咲く夏の花」ではなく、「必ずの夏の花」と書かれることによって、俳句になりました。「必ず咲く夏の花」と比べて「必ずの夏の花」とは、なんと読みにくい、屈折したもの言いでしょう。俳句の言葉で言えば、「必ずの夏の花」と、表現がひねられているのです。ひねられることによって、この原子炉に必ず咲くはずの夏の花は、不吉な、尋常でない夏の花であることを読者に予感させます。いったい膨大な核エネルギーの生れる原子炉に咲く「必ずの夏の花」は、どんな美しい、もしくは異様な姿・形をした夏の花であることでしょう。想像力を掻き立てられます。最後に申し上げます。「必ずの」を読み飛ばし、「夏の花」を原民喜の小説「夏の花」に短絡させることだけは止めてください。 (大井恒行『句集 水月伝』2024年4月23日、ふらんす堂)
句集『三月』はこの句からはじまります。
野遊びの誰の話も聞いてない
読者はこの句を読むと不思議な感覚に誘われることでしょう。『三月』は、このような句によく出会うので、そんな不思議な感覚に私は酔い痴れ、読み続けました。では、この不思議な感覚はどうしておこるのか、自分自身の感覚を見つめてみましょう。
「野遊びの」までは、どおってことはありません。「誰の話も」も少し変ですが、読むのに支障はありません。ところが「聞いてない」と書かれると、自分の感覚が横に一回転したように感じられ、句の流れについていけなくなります。
そこで、もう一度読みます。相変わらず句の流れについていけませんが、何か未体験の感覚で面白いです。句の中で浮かんでいるようです。
それは、「野遊びの誰の話も聞こえない」と無意識の内に期待するところがあったからです。
言い換えれば、現実の句は、「野遊びの誰の話も」の後「聞こえない」とせずに「聞いてない」と、ちょっとひねられ、外されているからです。
「聞いていない」とひねりはずされることによって、野遊びしながら語らっている人たちを見ている人物が突然現れます。
では、「野遊びの誰の話も聞いてない」人物とはいったいどのような人物なのでしょう。
この俳句の中には、はっきりとしたイメージをもって存在しない人物です。
そして、謎は深まります。
その人物が「野遊びの誰の話も聞いてない」のですから、当然、野遊びの人たちの語らっていたことが何かわかりません。
このように、一見春の長閑な野遊びの光景を詠んだ句のように見えて、実は、何もかもはっきりしない世界が現れるのです。
この謎めいた世界が、私たちの住んでいる長閑な野遊びの世界の本当の姿かもしれません。
次の句もそうです。『三月』の三番目、四番目の句です。
鳥の巣へ百歩手前の静かな日
近所とはどこまで香る梅の花
鳥の句は、「鳥の巣へ百歩手前の」まではすんなり分かりますが、「静かな日」とひねられています。
ここで軽いめまいを読者は体験します。そのめまいの果てに鳥の巣と百歩へだてた静かな日との緊迫した世界が現れます。百歩より狭くなれば修羅の日とかすかもしれないのです。
近所の句は、鳥の巣の句もそうですが、「野遊びの誰の話も聞いてない」と同じ言葉さばきによってできています。
野遊びの誰の話も 誰の話も聞いてない
野遊びの句は、このように、「誰の話も」が上と下の両方に掛かっています。そして、「誰の話も」でひねられているのが見てとれます。これがこの句の不思議感を生み出す構造的秘密です。
「近所」の句も同じです。「どこまで」が、上と下の両方に掛かるように書かれています。
近所とはどこまで どこまで香る梅の花
「どこまで」でひねられているわけです。このひねりによって、読者は一瞬宙ぶらりんの感じを体験します。
このように二村典子の世界は、すこし不安定なのです。
世界を少し不安定に描く面白さを、われわれ(読者)の前に見せてくれるのが『三月』です。
先の三句は、真中の言葉が上と下に掛かり、真中の言葉でひねられていたのですが、その他にも、さまざなは言葉さばきが使われています。そのような句をもう少し紹介して、このとりあえずの句集評を終わります。
梅雨空の市バス前扉から降りる
七月の箱の内寸不正確
かばんには青無花果とジェネリック
(二村典子句集『三月』黎明書房、2024年3月25日)
カタカナが効果的です。「水抜いた」のあとに「プール」が来ますと、隙間だらけのカタカナ表記からは空虚感が漂います。しかし、下五まで来て小さな春、「小春」に出会いますと、「プール」という開かれた字面のカタカナ表記からは明るい光を感じます。空虚感と明るさが綯交ぜになったこのプールを眺めている人のこころの内がしみじみと伝わってくる佳句です。私は、思います。ひょっとしてこの人の見ているものは、「プール」というカタカナで表記された言葉ではないかと。
(山本純子句集『オノマトペ』2024年12月1日刊、象の森書房)

(川島由紀子句集『アガパンサスの朝』朔出版、2024年10月23日発行)
この句を一読して、いったいこんな素敵な句をどんな人が作ったのだろうと、思いました。俳句にはめずらしい明るい抒情です。
ゲーテのミニヨンの歌を思いました。はるかな異国へのあこがれが爽やかに描かれています。
君よ知るや南の国
「麦熟れて」という言葉の背後に「麦秋」(麦と秋)という言葉があることと相まって、「稲熟れて」とは違った、湿潤なアジア的世界ではなく、乾いた西欧的世界が心地よく迫ってきます。
(第21回現代俳句東海大会。2024年11月17日)
あのぺらぺらながらも腰のある白い紙に、記号のような文字列の印字されたレシート。それをチェックするのではなく、意味ある文のように「熟読してしまう」ことの不思議さ。しかも、熟読する日が「獺祭忌」という獣(かわうそ)の祭の忌と名付けられた不思議な忌日であるという二重の不思議さが、読者に迫って来ます。この二重の不思議さが綯(ない)交ぜになっているのが、この句の眼目です。本来ならば、その不思議な世界を体で感じ取るだけでもよいのです。獺祭忌の意味を事細かに説明してしまうことがはばかられる句なのです。
しかしあえて言いましょう。
獺祭忌は、正岡子規の忌日9月19日です。子規の晩年の随筆『仰臥漫録』には、毎日何を食べたか、口に入れたか克明に記されています。あたかもスーパーのレシートのごとく。しかし、それが、彼の雅俗混淆のリアルな世界であったと思います。季節の食べ物は、たちどころに彼の脳裏に古今の名句を思い起こさせたことでしょう。
死の1年ほど前の明治34年9月10日の記事を読んでみます。
「 便通間にあはず 繃帯取換
朝飯 ぬく飯二椀 佃煮 紅茶一杯 菓子パン一つ
便通
午飯 粥いも入り三椀 松魚のさしみ みそ汁葱茄子 つくだ煮 梨二つ 林
間食 焼栗八、九個 ゆで栗三、四個 煎餅四、五枚 菓子パン六、七個
夕飯 いも粥三椀 おこぜ豆腐の湯あげ おこぜ鱠 キヤベツひたし物 梨二切 林檎一つ」
こんな記述が毎日続くのです。まるでスーパーのレシートです。しかも、このレシートの中はなんと生々しく、また生き生きしていることでしょうか。読み続けても飽きない自分の命をも包み込んだ森羅万象を映し出すような世界がここにあります。レシートが、私たちの熟読を誘うのも、ひょっとしてそのためかもしれません。
歳時記に載っていてもおかしくない句です。
(第21回現代俳句東海大会。2024年
姉は全てにおいて一番の存在です。そして、妹たちには、眩しい存在です。その輝くばかりの姉が来て桃を剝きます。もちろん沢山の桃の中の一番きれいな桃を剥きます。そして、剥かれた桃からは、至高の美がこの世に現れるのです。見事な句です。
(中日総合俳句会8月例会。2024年8月11日
何のことを思い出したのだろう。きっと楽しいことに違いない。思い出し笑いだから。しかし、母の下で安らかに昼寝をしているこの子をとりまく世界は、果たして楽しい世界であろうか。私は、楽しい世界であることを切に祈りたい。
(中日総合俳句会8月例会。2024年8月11日)
「必ず咲く夏の花」ではなく、「必ずの夏の花」と書かれることによって、俳句になりました。「必ず咲く夏の花」と比べて「必ずの夏の花」とは、なんと読みにくい、屈折したもの言いでしょう。俳句の言葉で言えば、「必ずの夏の花」と、表現がひねられているのです。ひねられることによって、この原子炉に必ず咲くはずの夏の花は、不吉な、尋常でない夏の花であることを読者に予感させます。いったい膨大な核エネルギーの生れる原子炉に咲く「必ずの夏の花」は、どんな美しい、もしくは異様な姿・形をした夏の花であることでしょう。想像力を掻き立てられます。最後に申し上げます。「必ずの」を読み飛ばし、「夏の花」を原民喜の小説「夏の花」に短絡させることだけは止めてください。 (大井恒行『句集 水月伝』2024年4月23日、ふらんす堂)
句集『三月』はこの句からはじまります。
野遊びの誰の話も聞いてない
読者はこの句を読むと不思議な感覚に誘われることでしょう。『三月』は、このような句によく出会うので、そんな不思議な感覚に私は酔い痴れ、読み続けました。では、この不思議な感覚はどうしておこるのか、自分自身の感覚を見つめてみましょう。
「野遊びの」までは、どおってことはありません。「誰の話も」も少し変ですが、読むのに支障はありません。ところが「聞いてない」と書かれると、自分の感覚が横に一回転したように感じられ、句の流れについていけなくなります。
そこで、もう一度読みます。相変わらず句の流れについていけませんが、何か未体験の感覚で面白いです。句の中で浮かんでいるようです。
それは、「野遊びの誰の話も聞こえない」と無意識の内に期待するところがあったからです。
言い換えれば、現実の句は、「野遊びの誰の話も」の後「聞こえない」とせずに「聞いてない」と、ちょっとひねられ、外されているからです。
「聞いていない」とひねりはずされることによって、野遊びしながら語らっている人たちを見ている人物が突然現れます。
では、「野遊びの誰の話も聞いてない」人物とはいったいどのような人物なのでしょう。
この俳句の中には、はっきりとしたイメージをもって存在しない人物です。
そして、謎は深まります。
その人物が「野遊びの誰の話も聞いてない」のですから、当然、野遊びの人たちの語らっていたことが何かわかりません。
このように、一見春の長閑な野遊びの光景を詠んだ句のように見えて、実は、何もかもはっきりしない世界が現れるのです。
この謎めいた世界が、私たちの住んでいる長閑な野遊びの世界の本当の姿かもしれません。
次の句もそうです。『三月』の三番目、四番目の句です。
鳥の巣へ百歩手前の静かな日
近所とはどこまで香る梅の花
鳥の句は、「鳥の巣へ百歩手前の」まではすんなり分かりますが、「静かな日」とひねられています。
ここで軽いめまいを読者は体験します。そのめまいの果てに鳥の巣と百歩へだてた静かな日との緊迫した世界が現れます。百歩より狭くなれば修羅の日とかすかもしれないのです。
近所の句は、鳥の巣の句もそうですが、「野遊びの誰の話も聞いてない」と同じ言葉さばきによってできています。
野遊びの誰の話も 誰の話も聞いてない
野遊びの句は、このように、「誰の話も」が上と下の両方に掛かっています。そして、「誰の話も」でひねられているのが見てとれます。これがこの句の不思議感を生み出す構造的秘密です。
「近所」の句も同じです。「どこまで」が、上と下の両方に掛かるように書かれています。
近所とはどこまで どこまで香る梅の花
「どこまで」でひねられているわけです。このひねりによって、読者は一瞬宙ぶらりんの感じを体験します。
このように二村典子の世界は、すこし不安定なのです。
世界を少し不安定に描く面白さを、われわれ(読者)の前に見せてくれるのが『三月』です。
先の三句は、真中の言葉が上と下に掛かり、真中の言葉でひねられていたのですが、その他にも、さまざなは言葉さばきが使われています。そのような句をもう少し紹介して、このとりあえずの句集評を終わります。
梅雨空の市バス前扉から降りる
七月の箱の内寸不正確
かばんには青無花果とジェネリック
(二村典子句集『三月』黎明書房、2024年3月25日)
カタカナが効果的です。「水抜いた」のあとに「プール」が来ますと、隙間だらけのカタカナ表記からは空虚感が漂います。しかし、下五まで来て小さな春、「小春」に出会いますと、「プール」という開かれた字面のカタカナ表記からは明るい光を感じます。空虚感と明るさが綯交ぜになったこのプールを眺めている人のこころの内がしみじみと伝わってくる佳句です。私は、思います。ひょっとしてこの人の見ているものは、「プール」というカタカナで表記された言葉ではないかと。
(山本純子句集『オノマトペ』2024年12月1日刊、象の森書房)

(川島由紀子句集『アガパンサスの朝』朔出版、2024年10月23日発行)
この句を一読して、いったいこんな素敵な句をどんな人が作ったのだろうと、思いました。俳句にはめずらしい明るい抒情です。
ゲーテのミニヨンの歌を思いました。はるかな異国へのあこがれが爽やかに描かれています。
君よ知るや南の国
「麦熟れて」という言葉の背後に「麦秋」(麦と秋)という言葉があることと相まって、「稲熟れて」とは違った、湿潤なアジア的世界ではなく、乾いた西欧的世界が心地よく迫ってきます。
(第21回現代俳句東海大会。2024年11月17日)
あのぺらぺらながらも腰のある白い紙に、記号のような文字列の印字されたレシート。それをチェックするのではなく、意味ある文のように「熟読してしまう」ことの不思議さ。しかも、熟読する日が「獺祭忌」という獣(かわうそ)の祭の忌と名付けられた不思議な忌日であるという二重の不思議さが、読者に迫って来ます。この二重の不思議さが綯(ない)交ぜになっているのが、この句の眼目です。本来ならば、その不思議な世界を体で感じ取るだけでもよいのです。獺祭忌の意味を事細かに説明してしまうことがはばかられる句なのです。
しかしあえて言いましょう。
獺祭忌は、正岡子規の忌日9月19日です。子規の晩年の随筆『仰臥漫録』には、毎日何を食べたか、口に入れたか克明に記されています。あたかもスーパーのレシートのごとく。しかし、それが、彼の雅俗混淆のリアルな世界であったと思います。季節の食べ物は、たちどころに彼の脳裏に古今の名句を思い起こさせたことでしょう。
死の1年ほど前の明治34年9月10日の記事を読んでみます。
「 便通間にあはず 繃帯取換
朝飯 ぬく飯二椀 佃煮 紅茶一杯 菓子パン一つ
便通
午飯 粥いも入り三椀 松魚のさしみ みそ汁葱茄子 つくだ煮 梨二つ 林
間食 焼栗八、九個 ゆで栗三、四個 煎餅四、五枚 菓子パン六、七個
夕飯 いも粥三椀 おこぜ豆腐の湯あげ おこぜ鱠 キヤベツひたし物 梨二切 林檎一つ」
こんな記述が毎日続くのです。まるでスーパーのレシートです。しかも、このレシートの中はなんと生々しく、また生き生きしていることでしょうか。読み続けても飽きない自分の命をも包み込んだ森羅万象を映し出すような世界がここにあります。レシートが、私たちの熟読を誘うのも、ひょっとしてそのためかもしれません。
歳時記に載っていてもおかしくない句です。
(第21回現代俳句東海大会。2024年
姉は全てにおいて一番の存在です。そして、妹たちには、眩しい存在です。その輝くばかりの姉が来て桃を剝きます。もちろん沢山の桃の中の一番きれいな桃を剥きます。そして、剥かれた桃からは、至高の美がこの世に現れるのです。見事な句です。
(中日総合俳句会8月例会。2024年8月11日
何のことを思い出したのだろう。きっと楽しいことに違いない。思い出し笑いだから。しかし、母の下で安らかに昼寝をしているこの子をとりまく世界は、果たして楽しい世界であろうか。私は、楽しい世界であることを切に祈りたい。
(中日総合俳句会8月例会。2024年8月11日)
「必ず咲く夏の花」ではなく、「必ずの夏の花」と書かれることによって、俳句になりました。「必ず咲く夏の花」と比べて「必ずの夏の花」とは、なんと読みにくい、屈折したもの言いでしょう。俳句の言葉で言えば、「必ずの夏の花」と、表現がひねられているのです。ひねられることによって、この原子炉に必ず咲くはずの夏の花は、不吉な、尋常でない夏の花であることを読者に予感させます。いったい膨大な核エネルギーの生れる原子炉に咲く「必ずの夏の花」は、どんな美しい、もしくは異様な姿・形をした夏の花であることでしょう。想像力を掻き立てられます。最後に申し上げます。「必ずの」を読み飛ばし、「夏の花」を原民喜の小説「夏の花」に短絡させることだけは止めてください。 (大井恒行『句集 水月伝』2024年4月23日、ふらんす堂)
句集『三月』はこの句からはじまります。
野遊びの誰の話も聞いてない
読者はこの句を読むと不思議な感覚に誘われることでしょう。『三月』は、このような句によく出会うので、そんな不思議な感覚に私は酔い痴れ、読み続けました。では、この不思議な感覚はどうしておこるのか、自分自身の感覚を見つめてみましょう。
「野遊びの」までは、どおってことはありません。「誰の話も」も少し変ですが、読むのに支障はありません。ところが「聞いてない」と書かれると、自分の感覚が横に一回転したように感じられ、句の流れについていけなくなります。
そこで、もう一度読みます。相変わらず句の流れについていけませんが、何か未体験の感覚で面白いです。句の中で浮かんでいるようです。
それは、「野遊びの誰の話も聞こえない」と無意識の内に期待するところがあったからです。
言い換えれば、現実の句は、「野遊びの誰の話も」の後「聞こえない」とせずに「聞いてない」と、ちょっとひねられ、外されているからです。
「聞いていない」とひねりはずされることによって、野遊びしながら語らっている人たちを見ている人物が突然現れます。
では、「野遊びの誰の話も聞いてない」人物とはいったいどのような人物なのでしょう。
この俳句の中には、はっきりとしたイメージをもって存在しない人物です。
そして、謎は深まります。
その人物が「野遊びの誰の話も聞いてない」のですから、当然、野遊びの人たちの語らっていたことが何かわかりません。
このように、一見春の長閑な野遊びの光景を詠んだ句のように見えて、実は、何もかもはっきりしない世界が現れるのです。
この謎めいた世界が、私たちの住んでいる長閑な野遊びの世界の本当の姿かもしれません。
次の句もそうです。『三月』の三番目、四番目の句です。
鳥の巣へ百歩手前の静かな日
近所とはどこまで香る梅の花
鳥の句は、「鳥の巣へ百歩手前の」まではすんなり分かりますが、「静かな日」とひねられています。
ここで軽いめまいを読者は体験します。そのめまいの果てに鳥の巣と百歩へだてた静かな日との緊迫した世界が現れます。百歩より狭くなれば修羅の日とかすかもしれないのです。
近所の句は、鳥の巣の句もそうですが、「野遊びの誰の話も聞いてない」と同じ言葉さばきによってできています。
野遊びの誰の話も 誰の話も聞いてない
野遊びの句は、このように、「誰の話も」が上と下の両方に掛かっています。そして、「誰の話も」でひねられているのが見てとれます。これがこの句の不思議感を生み出す構造的秘密です。
「近所」の句も同じです。「どこまで」が、上と下の両方に掛かるように書かれています。
近所とはどこまで どこまで香る梅の花
「どこまで」でひねられているわけです。このひねりによって、読者は一瞬宙ぶらりんの感じを体験します。
このように二村典子の世界は、すこし不安定なのです。
世界を少し不安定に描く面白さを、われわれ(読者)の前に見せてくれるのが『三月』です。
先の三句は、真中の言葉が上と下に掛かり、真中の言葉でひねられていたのですが、その他にも、さまざなは言葉さばきが使われています。そのような句をもう少し紹介して、このとりあえずの句集評を終わります。
梅雨空の市バス前扉から降りる
七月の箱の内寸不正確
かばんには青無花果とジェネリック
(二村典子句集『三月』黎明書房、2024年3月25日)
カタカナが効果的です。「水抜いた」のあとに「プール」が来ますと、隙間だらけのカタカナ表記からは空虚感が漂います。しかし、下五まで来て小さな春、「小春」に出会いますと、「プール」という開かれた字面のカタカナ表記からは明るい光を感じます。空虚感と明るさが綯交ぜになったこのプールを眺めている人のこころの内がしみじみと伝わってくる佳句です。私は、思います。ひょっとしてこの人の見ているものは、「プール」というカタカナで表記された言葉ではないかと。
(山本純子句集『オノマトペ』2024年12月1日刊、象の森書房)

(川島由紀子句集『アガパンサスの朝』朔出版、2024年10月23日発行)
この句を一読して、いったいこんな素敵な句をどんな人が作ったのだろうと、思いました。俳句にはめずらしい明るい抒情です。
ゲーテのミニヨンの歌を思いました。はるかな異国へのあこがれが爽やかに描かれています。
君よ知るや南の国
「麦熟れて」という言葉の背後に「麦秋」(麦と秋)という言葉があることと相まって、「稲熟れて」とは違った、湿潤なアジア的世界ではなく、乾いた西欧的世界が心地よく迫ってきます。
(第21回現代俳句東海大会。2024年11月17日)
あのぺらぺらながらも腰のある白い紙に、記号のような文字列の印字されたレシート。それをチェックするのではなく、意味ある文のように「熟読してしまう」ことの不思議さ。しかも、熟読する日が「獺祭忌」という獣(かわうそ)の祭の忌と名付けられた不思議な忌日であるという二重の不思議さが、読者に迫って来ます。この二重の不思議さが綯(ない)交ぜになっているのが、この句の眼目です。本来ならば、その不思議な世界を体で感じ取るだけでもよいのです。獺祭忌の意味を事細かに説明してしまうことがはばかられる句なのです。
しかしあえて言いましょう。
獺祭忌は、正岡子規の忌日9月19日です。子規の晩年の随筆『仰臥漫録』には、毎日何を食べたか、口に入れたか克明に記されています。あたかもスーパーのレシートのごとく。しかし、それが、彼の雅俗混淆のリアルな世界であったと思います。季節の食べ物は、たちどころに彼の脳裏に古今の名句を思い起こさせたことでしょう。
死の1年ほど前の明治34年9月10日の記事を読んでみます。
「 便通間にあはず 繃帯取換
朝飯 ぬく飯二椀 佃煮 紅茶一杯 菓子パン一つ
便通
午飯 粥いも入り三椀 松魚のさしみ みそ汁葱茄子 つくだ煮 梨二つ 林
間食 焼栗八、九個 ゆで栗三、四個 煎餅四、五枚 菓子パン六、七個
夕飯 いも粥三椀 おこぜ豆腐の湯あげ おこぜ鱠 キヤベツひたし物 梨二切 林檎一つ」
こんな記述が毎日続くのです。まるでスーパーのレシートです。しかも、このレシートの中はなんと生々しく、また生き生きしていることでしょうか。読み続けても飽きない自分の命をも包み込んだ森羅万象を映し出すような世界がここにあります。レシートが、私たちの熟読を誘うのも、ひょっとしてそのためかもしれません。
歳時記に載っていてもおかしくない句です。
(第21回現代俳句東海大会。2024年
姉は全てにおいて一番の存在です。そして、妹たちには、眩しい存在です。その輝くばかりの姉が来て桃を剝きます。もちろん沢山の桃の中の一番きれいな桃を剥きます。そして、剥かれた桃からは、至高の美がこの世に現れるのです。見事な句です。
(中日総合俳句会8月例会。2024年8月11日
何のことを思い出したのだろう。きっと楽しいことに違いない。思い出し笑いだから。しかし、母の下で安らかに昼寝をしているこの子をとりまく世界は、果たして楽しい世界であろうか。私は、楽しい世界であることを切に祈りたい。
(中日総合俳句会8月例会。2024年8月11日)
「必ず咲く夏の花」ではなく、「必ずの夏の花」と書かれることによって、俳句になりました。「必ず咲く夏の花」と比べて「必ずの夏の花」とは、なんと読みにくい、屈折したもの言いでしょう。俳句の言葉で言えば、「必ずの夏の花」と、表現がひねられているのです。ひねられることによって、この原子炉に必ず咲くはずの夏の花は、不吉な、尋常でない夏の花であることを読者に予感させます。いったい膨大な核エネルギーの生れる原子炉に咲く「必ずの夏の花」は、どんな美しい、もしくは異様な姿・形をした夏の花であることでしょう。想像力を掻き立てられます。最後に申し上げます。「必ずの」を読み飛ばし、「夏の花」を原民喜の小説「夏の花」に短絡させることだけは止めてください。 (大井恒行『句集 水月伝』2024年4月23日、ふらんす堂)
句集『三月』はこの句からはじまります。
野遊びの誰の話も聞いてない
読者はこの句を読むと不思議な感覚に誘われることでしょう。『三月』は、このような句によく出会うので、そんな不思議な感覚に私は酔い痴れ、読み続けました。では、この不思議な感覚はどうしておこるのか、自分自身の感覚を見つめてみましょう。
「野遊びの」までは、どおってことはありません。「誰の話も」も少し変ですが、読むのに支障はありません。ところが「聞いてない」と書かれると、自分の感覚が横に一回転したように感じられ、句の流れについていけなくなります。
そこで、もう一度読みます。相変わらず句の流れについていけませんが、何か未体験の感覚で面白いです。句の中で浮かんでいるようです。
それは、「野遊びの誰の話も聞こえない」と無意識の内に期待するところがあったからです。
言い換えれば、現実の句は、「野遊びの誰の話も」の後「聞こえない」とせずに「聞いてない」と、ちょっとひねられ、外されているからです。
「聞いていない」とひねりはずされることによって、野遊びしながら語らっている人たちを見ている人物が突然現れます。
では、「野遊びの誰の話も聞いてない」人物とはいったいどのような人物なのでしょう。
この俳句の中には、はっきりとしたイメージをもって存在しない人物です。
そして、謎は深まります。
その人物が「野遊びの誰の話も聞いてない」のですから、当然、野遊びの人たちの語らっていたことが何かわかりません。
このように、一見春の長閑な野遊びの光景を詠んだ句のように見えて、実は、何もかもはっきりしない世界が現れるのです。
この謎めいた世界が、私たちの住んでいる長閑な野遊びの世界の本当の姿かもしれません。
次の句もそうです。『三月』の三番目、四番目の句です。
鳥の巣へ百歩手前の静かな日
近所とはどこまで香る梅の花
鳥の句は、「鳥の巣へ百歩手前の」まではすんなり分かりますが、「静かな日」とひねられています。
ここで軽いめまいを読者は体験します。そのめまいの果てに鳥の巣と百歩へだてた静かな日との緊迫した世界が現れます。百歩より狭くなれば修羅の日とかすかもしれないのです。
近所の句は、鳥の巣の句もそうですが、「野遊びの誰の話も聞いてない」と同じ言葉さばきによってできています。
野遊びの誰の話も 誰の話も聞いてない
野遊びの句は、このように、「誰の話も」が上と下の両方に掛かっています。そして、「誰の話も」でひねられているのが見てとれます。これがこの句の不思議感を生み出す構造的秘密です。
「近所」の句も同じです。「どこまで」が、上と下の両方に掛かるように書かれています。
近所とはどこまで どこまで香る梅の花
「どこまで」でひねられているわけです。このひねりによって、読者は一瞬宙ぶらりんの感じを体験します。
このように二村典子の世界は、すこし不安定なのです。
世界を少し不安定に描く面白さを、われわれ(読者)の前に見せてくれるのが『三月』です。
先の三句は、真中の言葉が上と下に掛かり、真中の言葉でひねられていたのですが、その他にも、さまざなは言葉さばきが使われています。そのような句をもう少し紹介して、このとりあえずの句集評を終わります。
梅雨空の市バス前扉から降りる
七月の箱の内寸不正確
かばんには青無花果とジェネリック
(二村典子句集『三月』黎明書房、2024年3月25日)
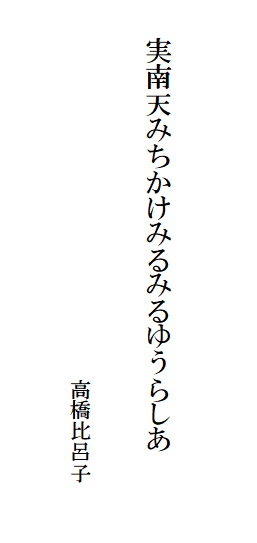
鮮やかな赤い「実南天」が「南天」に垂れています。そして、「天」には月が満ち欠けを繰り返します。すると、「みるみる」「ゆうらしあ」が生まれてくるのです。「実南天」以下はひらがなです。天に垂れる赤い実南天を際立たせるためです。そして、赤いイメージを持つ実南天に相対することによってひらがな「みちかけみるみるゆうらしあ」に、白い透明感を持った世界がゆらめきながら現れるのです。 「ユーラシア」とカタカナではなく「ゆうらしあ」と、ひらがなで書かれているのはそのためでもありますが、もう一つ大事な理由があります。それは、「ゆうらしあ」と書くことによって、現実の「ユーラシア」を超えた虚構の「ユーラシア」を、作者は生み出そうとしているからです。この「ゆうらしあ」は、現実のユーラシアを面影に持ちながらも作者によって作り出されたこの句の中にしかない広い広い世界なのです。 「ひらがな」という言葉さばきのすごさを思い知る一句です。 (『ロマネコンティ』№85を加筆修正)
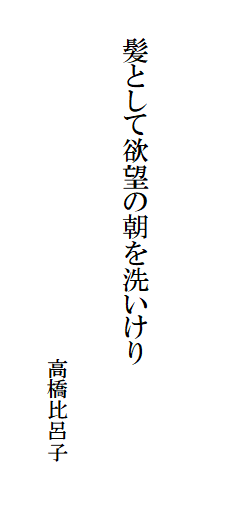
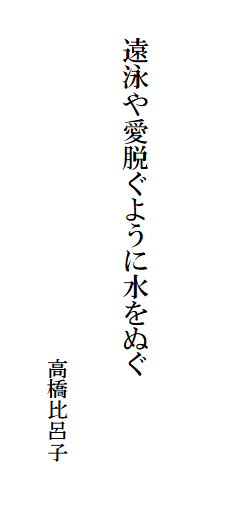
官能的な句です。
そして、「愛脱ぐように水をぬぐ」で、上五を受けて、愛する人から遠く離れ、一度は受け入れた性愛を脱しようとしている人物を思います。脱に肉月がありますから。
この人は、水をかいた手を水からぬくごとに、あかたも自らの身体を覆っているかのような水をぬぎつづけるのです。いままでの愛を脱し、脱皮し、生まれ変わって行くかのように。この「ぬぐ」がどうしてひらがなになっているかは、考えてください。
(『ロマネコンティ』№241より転載)
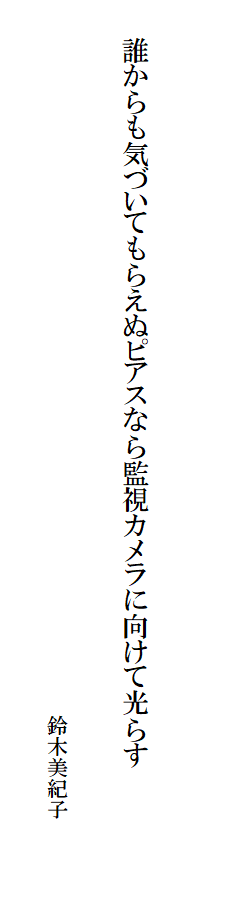
柔らかい耳の温もりを持ち、煌めくピアスなのに、すれ違う生身の誰からも気づいてもらえない悲しさ。それならと誰にも気づかれることなく作動する無機的な非人間的な目、監視カメラを挑発するのです。身体を捩り、ピアスをことさら煌めかせるのです。「私はここにいるのよ。」と。「なら」によって捩られた日常から非日常への不穏な転換でです。ピアスとカメラという三文字のカタカナが効果的です。ピアスというカタカナは煌めき、カメラというカタカナには煌めきはありません。
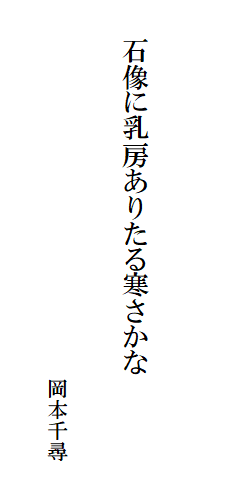
石像のひと際盛り上がって寒気に晒されている、冷え冷えとした石の乳房の姿に、冬の厳しい寒さを感じた句です。それは、また、冬の厳しい寒さの中、物言わず立っている乳房を持つ石像に、この石像を見ている句中の人物が、同じ乳房を持つものとして深くこころを寄せた句でもあります。「乳房ありたる寒さ」がとても身にしみたのです。
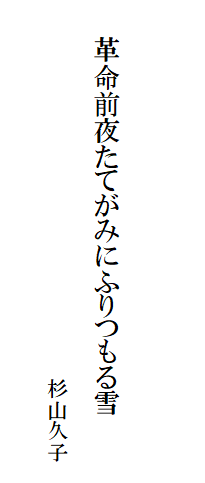
革命前夜はこのように静謐な時なのでありましょう。汚れなきまっさらな白い雪が軍馬の鬣に静かに降り積る時なのでありましょう。ひらがな表記の「たてがみにふりつもる」の一字一字は、今まさに、天上から無限に降り続いている白い雪そのものです。そして、一句の最後に置かれた「雪」は、積もった雪そのものです。日本語の縦書き表記によって美しく描かれた革命前夜の美学と言える句です。 (杉山久子句集『栞』朔出版、2023年9月刊)
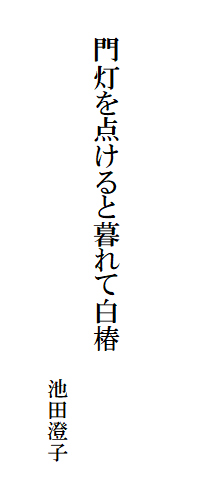
散文の世界では、暮れてきたから門灯を点けます。しかし、俳句の世界では、門灯を点けると暮れるのです。門灯を点けると、あたりは明るくなります。しかし、その門灯の明るさによって、門灯を取り巻く世界はその暗さを一段と増すことになります。それを作者は「門灯を点けると暮れて」と表現しました。そして、門灯を点けることによって現れた夕暮は、さらに美しいものを出現させます。白椿です。世界が暗さを増すことで、かえってその無垢の白さを際立させて行く、白椿の花の前にしばし呆然です。なんと美しい句でしょう。
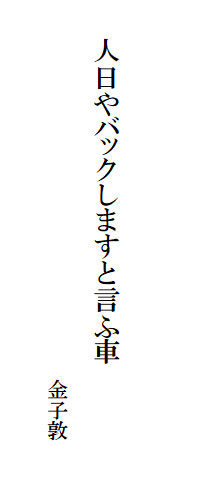
一見なんでもない句に見えます。正月七日、人日(じんじつ)の日に、運転者が「バックします」と言って止まっていた車を動かそうとしただけのことです。ところが、不思議なことに、それだけではないような気持ちを読者に抱かせるのす。
これは、「バックしますと言ふ車」という中七下五の表現の面白さから来ています。文字通り読めば、「車」自身が「バックします」と言っていることになるのです。ですから、人が言っているのと車が言っているのとが重なった世界をこの句は表現していることになります。
これが、この句の不思議さの元です。しかも「人日」、「人の日」です。上五の「人日」が切れ字「や」によって強調され、一句を覆います。車も人の日には、人になるのです。 (『金子敦句集』2023年4月刊、ふらんす堂)
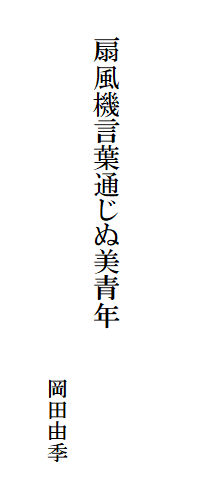
扇風機が爽やかに力強く回り続けています。私に向かって心を込めて回っています。その目元涼しい扇風機に向かって、私は一言挨拶をしました。もとより私の言葉は通じませんでした。美しくもたくましい扇風機へ愛を込めた一句です。
(岡田由季句集『中くらゐの町』ふらんす堂、2023年6月)
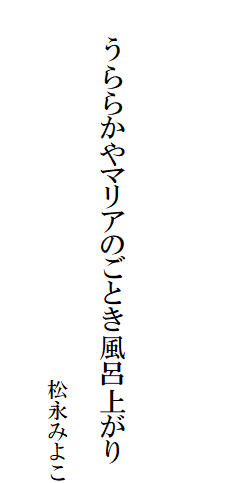
句の中の風呂上がりの女性を見ている「私」は、彼女のことを、神の子をみごもったマリアのようだと言っています。それは、子をみごもったすべての女性のことを言っているに違いありません。みごもったわがいとし子は、神の子にも比すべき存在です。「うららかや」は、そんな女性の晴れ晴れとした満足気な姿を表現した言葉です。 なお、この句の中の風呂上がりの女性は、「私」が見ている女性であると同時に、「私」自身でもあります。 このように句を挟み撃ちにして読むことによって、風呂上がりという日常的な俗なる姿から立ち上がる身ごもった女性の神々しいまでに美しいこころとからだが、奥行きをもって読者の前に現れるのです。
(中部日本俳句作家会々報、2023年3月号)
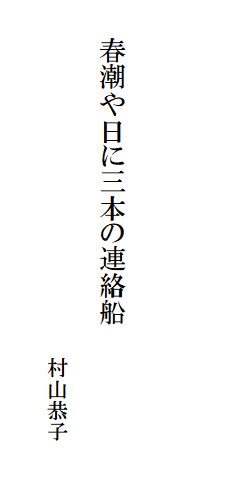
春の潮がゆたったりたゆたう明るく広い世界があります。その世界には日に三本ながら連絡船がありました。しかし、この三本は、単に少ないこと、さびしいことだけを言っているわけではありません。イギリスの昔話『三匹のこぶた』やチェーホフの戯曲『三姉妹』ように、ドラマが変化を持って展開する最小の単位三を表わしています。 さびしい澪を引きながらも、ゆったりとしたのどかに見える世界ですが、複雑なドラマをはらんだ世界がここにあります。
(中部日本俳句作家会々報、2023年3月号)
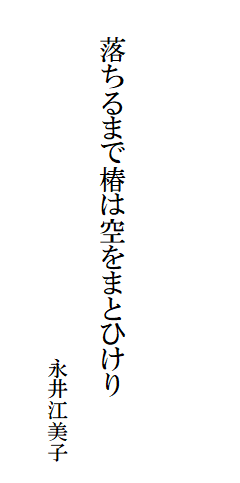
椿が枝から地上に落ちるまでの間、椿は、空(そら)と空(くう)をまとっていたという。空(そら)は「椿」の中にある幸せな「春」の空の青さ、空(くう)は、椿自身が椿であることを否定すること。椿であることを止めること。止めることによって、落ちるまでのほんの短い間、椿はそのいのちをひと際際立たせるのです。 上五から下五に向かって、空の青をまとってただ落下する一筋の真っ赤な椿の花の軌跡が目に見えるようです。
(中部日本俳句作家会々報、2023年3月号)
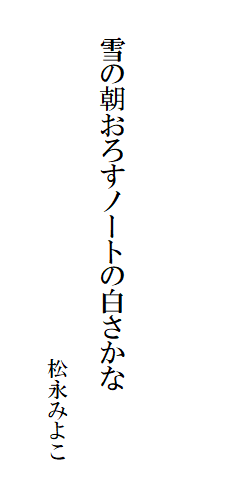
雪が一面に降り積もり、あらゆるものが汚れのないまっさらな美しい朝が訪れました。このような素晴らしい朝におろすノートもまたまっさらなのです。
世界と人生が美しく始まる朝です。
(中日総合俳句会、2023年2月例会)
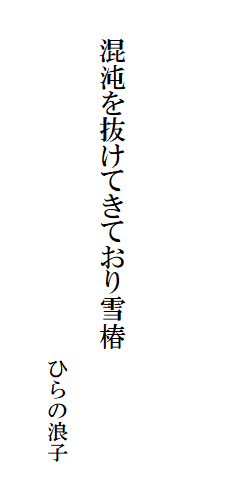
降り積もった真っ白な雪の面影を持つ雪椿。その真っ白な雪の面影の中に真っ赤な椿の花が、こちらの世界を見ています。
それは、万物を生み出す漆黒のカオスの世界を抜けて生れ出たばかりの花に違いありません。
なぜなら、なんの汚れもない美しい雪椿なのですから。
(中日総合俳句会、2023年2月例会)
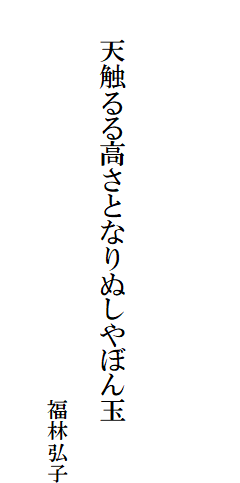
飛ばした人はしゃぼん玉が天に触れる喜びとともに、聖なるものを前にしてしゃぼんゃ玉が跡かたもなく割れて消えてしまうのではないかと恐れました。 この世のものであるちっぽけなしゃぼん玉が、この世のものを越えたものになるかも知れないという淡い期待を抱かせる美しい句です。 (中日総合俳句会、2023年2月例会)
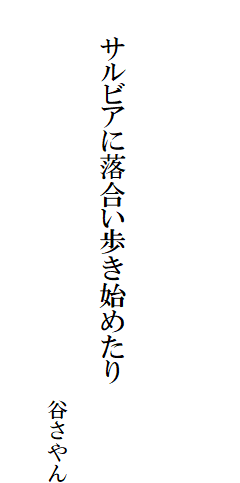
この句は、
サルビアで落合い歩き始めたり
でないところが、味噌です。
「で」は「に」より強く明快ですので、普通の説明的な文章に近づきます。ところが、「に」にしますと、「サルビアに」の意味が少しはっきりしなくなります。サルビアで落合ったという意味だけでなく、サルビアが少し擬人化され、サルビアで落合いサルビアと一緒に歩き始めたという意味も少し持って来ます。
それを踏まえて、この句を読んでみましょう。
房状に真っ赤な花がいくつも咲いている華やかな「サルビアに落合い」ました。「で」なく「に」ですから、さりげなく落合ったのでしょう。自分とは違う方向から歩いてきた人と、目と目を合わせ少しにっこり笑い、そして、身を寄せ合い、さりげなく満ち足りた気分の中を歩き初めたのです。
「サルビアに」で「サルビア」が少し擬人化されていますから、落合った相手は、あの華やかな赤いサルビアの面影をまとった素敵な人に違いありません。夏のある日のなにげない美しい光景です。 付記 意味的に「で」でもよいところを「に」にするのは、「で」より弱くし、曖昧にすることによって、句に奥行きを持たせるためです。このような言葉さばきを、私は曖昧表現と呼んでいます。中村汀女に、次のような句があります。 あちこちに蝗取居り顔を上ぐ 汀女 (『汀女句集』昭和十九年) 「あちこちで」でなく「あちこちに」にすることによって、句に奥行きが出ています。 (『谷さやん句集』朔出版、2022年11月1日)
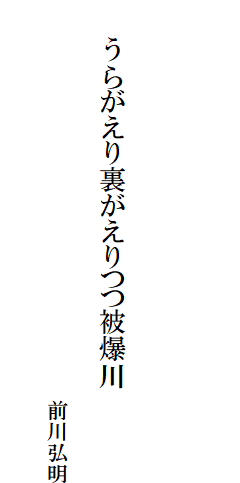
この句からは、原爆によって非人間的な仕打ちを受けた多くの人の遺体が、裏返り、裏返り流れて行く光景が見えてきます。そして、被爆川とありますから、川も被爆したに違いありません。その絶え間なく流れる水の有様もまた、裏返り裏返りしています。ここでは表はありません。裏しかない表を失った世界が、描かれています。 なお、この句の「うらがえり裏がえりつつ」のひらがなは、川の流れ(水)を文字の姿形(すがたかたち)で表したものです。真中の漢字「裏」は、流され行く裏返ったものたちの姿を表わしたものです。 (前川弘明句集『蜂の歌』2022年7月1日発行、拓思舎。頒価2500円(税込))
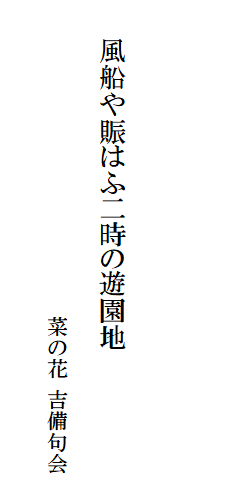
風船が空高くいくつも浮かんでいます。そして、賑わっている遊園地があります。しかし、時刻は午後二時です。
この二時という一時でもなく、三時でもない、二時という中途半端な時がこの句の眼目です。午後一時は、午後の活動がスタートする時です。午後三時は、お八つの時で、午後の活動が一休みと言ったところの時刻です。
その中間の二時は、本当は午後の活動のまっさかりのころですが、そんなイメージもなくあやふやな時です。
そんなあやふやな二時の、風船が空高く浮かぶ遊園地の賑わいは、なぜかうつろです。
読む者に不思議な感じを抱かせる二時の句です。
(2022年4月17日「菜の花」700号記念祝賀会地区対抗句相撲より)
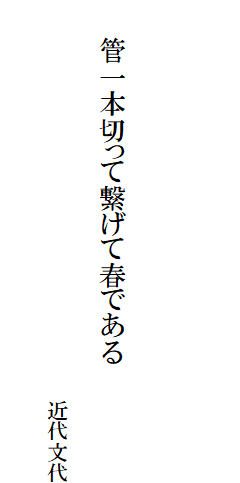
この句からは、自分のことが思い出されます。 管は、二度切り、二度繋げました。結局、一度目も二度目も切ったのは春でした。完全な空調の中で過ごし、冬はありませんでした。 即物的に管一本切って繋げてと書いても、五・七を纏っている限りそうは行きません。情緒が生まれます。その情緒が春に繋がるわけです。春でよかったです。春は、とにかく冬より待ち遠しい季節ですから。 (『猫街5号』2022年5月)
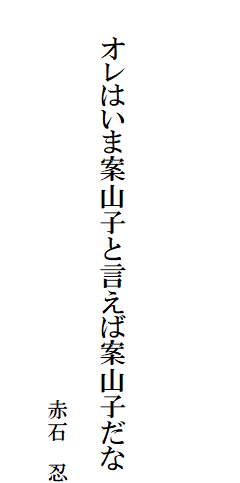
一つ目の「案山子」は日常世界の案山子です。そして、二つ目の「案山子」を読む時、読み手は、その案山子を二つ目の案山子に重ねて読むことになります。
二つ目の案山子が、一つ目の案山子に強調されることになります。強調されることによって、二つ目の案山子は、日常世界の案山子ではなく、案山子という存在そのもの(案山子の本質)になります。
読者のみなさんが意識してこの句を読まれれば、納得されることと思います。 そんな案山子ついて、赤石忍は、まず、次のように語ります。
昔、或る番組でこんな三段オチがあった。「ワーイ僕のお父さん、泥棒見張ってる警官なんだぞ」「ワーイ僕のお父さん、火事見張ってる消防士なんだぞ」「ワーイ僕のお父さん、雀見張ってる案山子なんだぞ」。この落ちには笑ったが、ふとその時、案山子の父の存在に「待てよ」と思った。
この「待てよ」が、二度目に「案山子」を読む時に案山子という存在そのもの(案山子の本質)が、読者の前に現れる瞬間にほかなりません。では、赤石忍に現れた案山子の本質とは何だったでしょう。赤石忍の文はこのように続きます。
ぼうっと立っているだけで、日々を過ごせるなんて何とも素敵な事だと。
理想化された「案山子」の句です。 (俳句・文:赤石忍 写真:唐木田敏彦『風宿』ピエトラ・ロッサ、2022年4月)
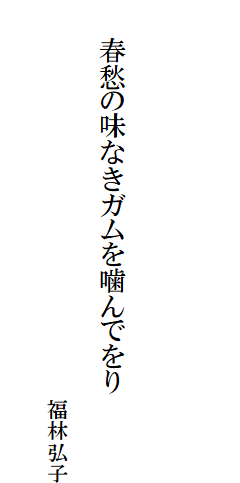
春の愁いの深さのあまり、ガムをあまりに長く噛みすぎて、もう味もなにもかもなくなってしまいました。しかし、それでもなおガムを噛むよりほか、この愁いを晴らす術はないのです。いや、晴らすというよりは、この人は、このように味気のない愁いをいつまでも反芻しているほかないのです。アンニュイの極みといえる句です。
「春愁の味なき」と「味なきガム」と、「味なき」が両方に掛かるのがこの句の味噌です。
(第23回 東海地区現代俳句賞、佳作「母の日」より)
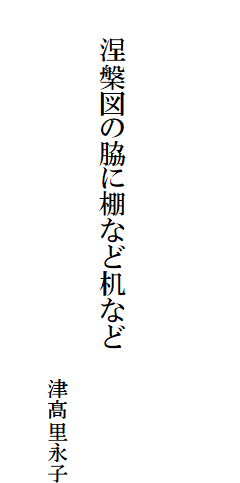
涅槃図の中には、沙羅双樹の下で亡くなられたお釈迦様の周りに、弟子や人々、神々、象や鳥などが、悲しみに涙する姿が描かれています。この句では、さらにその涅槃図のわきに棚や机などがあると書かれています。これは、情景から言えば、供物を供える棚やら机などということになるでしょう。 しかし、これでは俳句になりません。読者による意味づけ(主体的な読み)が必要になります。この句は、深い悲しみが込められた涅槃図というものが、一句の中にある「棚」や「机」と響き合っているのです。生きとし生けるものは泣き、今はいのち無き「棚」や「机」は静かに悲しみに沈んでいるのです。「…など…など」の静かな寂しい響きの中で。「棚」や「机」が共に木偏であることも味わうべきです。 (津髙里永子句集『寸法直し』東京四季出版、2022年2月22日)
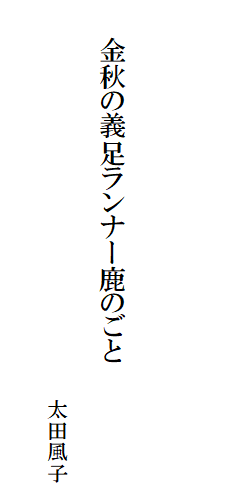
秋の透き通った大気の中、すべてのものが金色に光り輝いています。義足のランナーも、義足のランナーと重なって走る鹿も金色に光り輝いています。それは、句の天辺にある「金」のためです。この「金」が天辺より一句の世界を遍く金色に輝かせているのです。
なお、義足ランナーは鹿に譬えられていますが、譬えられたとたん、読者には鹿のイメージが義足のランナーに重なって見えることになります。
ちなみに、陰陽五行説では、世界を作っている木、火、土、金、水の五つの元素のうち秋には、金が配当されています。そのため、秋を金秋と呼びます。その金秋が見事に働いている美しい句です。 (第23回 東海地区現代俳句賞、応募作品「笹五位」より)
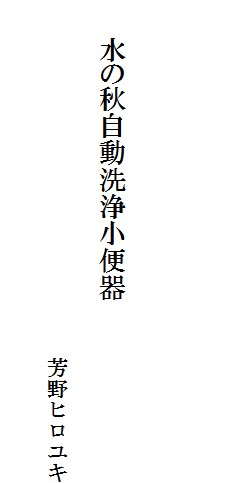
1917年(!)4月、マルセル・デュシャンは、男性用小便器に「泉」と題をつけて、展覧会に出品しようとしました。そして、拒否されました。時は移って、2020年10月、わが芳野ヒロユキは、自動洗浄小便器に「水の秋」と題して、猫街の紙面に発表しました。拒否されることなく。
この句は、とてもよくできています。まず、上五と下五の最後の音が、みずのあき、しょうべんきと、きの音で響き合っています。響き合うとは、上五と下五が分かちがたく存在しているということです。そして、おそらく、芳野ヒロユキは、自動洗浄小便器の音の成り立ちにも非常な心地よさを感じたに違いないのです。このこういうことです。
みずのあき じどう せん じょう しょう べんき
すばらしい響き合いです。そして、一句全体が響き合いで成り立つように、上五に秋の水をひっくり返して水の秋を置きました。秋の水では、先に述べたように、上五と下五が響き合いませんから。しかも、それによって、天辺の水が、下の自動洗浄小便器に落下するようになっています。
そして、水の秋と言う言葉が、澄み切った水に満たされた秋のイメージをかもし出し、小便器を常に自動洗浄しているというわけです。
雅と俗との絶妙のバランスを味わいましょう。
(『猫街』2号、2020年10月) 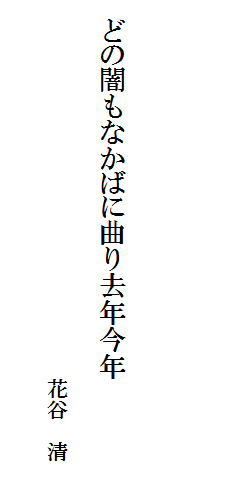
人は、一人ひとり大なり小なりそれぞれの闇を抱えて生きています。しかし、この句は、人の抱えるどの闇も半ばで曲がるものだといいます。闇も曲がって明るいところに出るのです。その明るいところに闇がひょっこり顔を出したのが、去年から今年への変わり目というわけです。かつて、高浜虚子は
去年今年貫く棒の如きもの 虚子
と、森羅万象の運行の揺るぎなさを見事に詠んで皆を驚かせたものですが、花谷清の句は、人の闇は曲がるものだと言いました。
花谷清が主宰する『藍』の今年1月号巻頭「去年今年」8句の最後に置かれた一句です。
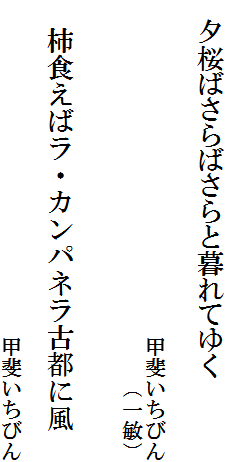
甲斐さんの句には、一見、声喩(オノマトペ)には見えない言葉が、声喩の働きをしています。それがまた魅力です。例えば、
夕桜ばさらばさらと暮れてゆく いちびん
です。句集の名に取られた「ばさら」は、言わば、旧代を蹴散らし、時代の過渡期を豪奢に生きようとする生き様。ですから、優雅な夕桜は、ばさらを生きるものにとっては、
夕桜さらさらと暮れてゆく
のようにさらさらと散っては行きません。ばさらばさらと、どうだと言わんばかりに散って行くのです。では、この句においての「ばさらばさら」は、夕桜の散る様子だけでしょうか。私は、甲斐さんのこの句を読んでいて、村上鬼城の名句
ゆさゆさと大枝ゆるる桜かな 鬼城
を思いました。なぜこの句が名句かといいますと、「ゆさゆさ」という声喩は、大枝が風にゆれている様を表現しているだけでなく、桜のいのちの現れだからです。
それと同じように、甲斐さんのこの句が優れているのは、この「ばさらばさら」が夕桜のいのちの現れだからです。夕桜は、ばさらばさらと聞こえない音を発して、ばさらを生きているのです。
そして、この夕桜自身の暮れて行き方も尋常ではありません。「さらば」を内に秘めて、豪奢に優雅に夕闇に散って行くのです。
では、「柿食えばラ・カンパネラ古都に風」はどうでしょう。これは、一目見れば、
柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺 正岡子規
を面影に持っていることは分かります。子規のこの句は、美味しい柿を食べる至福の時を、尊い法隆寺の鐘の音が荘厳(美しく厳かに飾る)するというものでした。
甲斐さんの句は、同じ「鐘」ですが、イタリア語の「カンパネラ」に置き換え、しかもリストのピアノの名曲「ラ・カンパネラ」を響かせ、この至福の時を荘厳しました。その「ラ・カンパネラ」のピアノの響きに乗って古都には秋の風が吹いて行くのです。
甲斐さんは、子規の伝統的な世界を、日本でもない、西洋でもない、どこにもない世界をつくり出そうとしたのです。丁度、先々回に紹介しました
ミモザ咲きましたかと耳なし芳一 甲斐一敏
のように。
ところで、この「柿食えばラ・カンパネラ古都に風」には、一見声喩は見当たりません。しかし、この句にも声喩は働いています。それは、「ラ・カンパネラ」です。この硬質な乾いた形と響きを持つカタカナで表記されたラ・カンパネラは、西洋の鐘の音であり、ピアノの音です。柿食えば、ラ・カ・ン・パ・ネ・ラと古都に響き渡るのです。
どこにもない古都に爽やかな風の吹く至福の時が流れています。 (甲斐いちびん句集『ばさら』2021年11月1日)
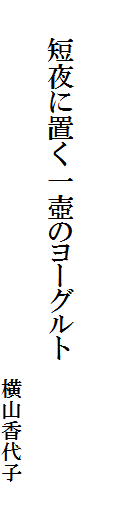
*俳句に「写生」という方法がありますが、これは、書かれたことを現実に見せるための方法です。しかし、俳句は言葉の芸術、しかも極小の文芸ですから絵とは違います。言葉は、五七五の中で、不思議な振る舞いをします。この不思議な振る舞いを不思議な振る舞いとして素直に読まないから、多くの名句が泣いています。
(横山香代子句集『人』文學の森、2007年2月刊)
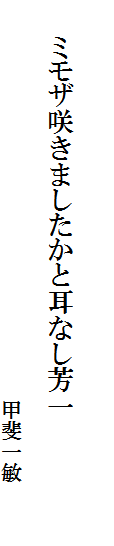
この句は、昨年の五月に亡くなった甲斐さんがよく口にした句です。これが出来たとき、自分の句ができたと思ったと、甲斐さんからお酒が入るたびに聞きました。では、この不思議な雰囲気を持つ句の文学的な味わいはどこにあるのでしょう。
その源泉は、次の二つにあります。 一、耳なし芳一と言われても、私たちが普通耳といっている頭の外側につい ているラッパ状のもの(耳介)がないだけで、実は彼は耳が聞こえること。 一、耳なし芳一と言われていますが、耳が聞こえないのではなく、実は目が 見えないこと。彼は、平家物語を語る盲目の平家琵琶の名手なのです。
この二つのことの絡み合い、響きあいによって、読者に文学的な深い味わいを読者にもたらします。
読者は、「ミモザ咲きましたか」と言われても、一瞬「耳なし芳一」という名にまどわされ、耳なし芳一が聞いても答えを聞くことがないのではと思わず思ってしまいます。
しかし、盲目の琵琶法師は、ミモザが咲くのが見えないからわざわざ聞いているのです。このへだたりが、この句に不思議さをかもし出しています。
そして、さらに桜ではなくなぜミモザかですが、これは、日本的な世界をずらし、どこにもない、この句にだけある世界を出現させる俳句の言葉さばきなのです。
目が見えないから、ミモザ咲きましたかと耳なし芳一が聞くことによって、この日本で、フランスの春告げ花があたかも咲くようなふうに思わせるところが味噌です。
それに、上五に当たる「ミモザ」のミ音と下五に当たる「ミミナシホウイチ」のミ音が上下で響きあうことによって、この破調の句に一句としての統一感をもたらしていることも見逃せません。
甲斐一敏は、この句ができたとき、この句に、確かに俳句にしかできない世界を作りだしたという手ごたえを持ったに違いありません。
異界と現実との皮膜の間に住む、春待つ盲目の琵琶法師耳なし芳一が、異国の花の開花を聞くという不思議な句、それがこの句です。
ミモザというカタカナ語についてさらに言えば、ミモザが、上五に来ていることによって、カタカナの形から来る明るさが、読者に伝わります。そして、読者には、カタカナの明るさからミモザが咲いているのが見えて来ます。ですから、芳一の「ミモザ咲きましたか」の問いに、読者は答えるに違いありません。「咲きました」と。
耳なし芳一は、読者からその答えを待っているのです。
明るい希望の春を待つ芳一の心根が偲ばれます。
甲斐一敏、以って瞑すべし。
(甲斐一敏句集『忘憂目録』ふらんす堂、2014年11月刊)
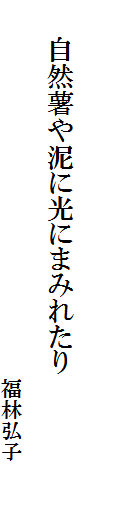
自然の育んだ無垢のいのちの塊、自然薯。その自然薯が大地から掘り出され、この世に現れた時、泥に光に相次いでまみれました。泥にまみれるのは分かり
(2021年11月14日、中日俳句会)
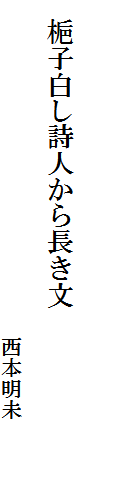
はからずも届いた『紫』九月号。
私好みの句がが一句。
くちなし、しろし、しじんと、「し」の音の連続から現れる「長き文」。
梔子の白が、長き文の紙の白さに及ぶ美しい句です。
やはり梔子は『枕草子(まくらのそうし)』の「口無し」でしょうか。あち
しかし、長き文とはありますが、それを書く一句は、わずか十一文字。
俳句とは味わい深いものです。
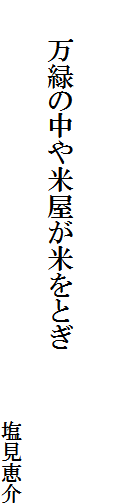
第三句集『隣の駅が見える駅』の中の随一の句です。なぜ、随一かと言えば、言葉だけでみごとに立っているからです。俳句は言葉さばき(レトリックを武馬はこう呼んでいます)によって成り立つ文芸ですが、この句の言葉さばきの中心は、〈重ね言葉〉です。 〈重ね言葉〉は、思い思い、一人一人と言った畳語とはちょっと違います。 離れていていてもかまいません。一句の中に同じ言葉がくり返されることです。多くの人は、くり返しは、言葉の強調ぐらいにしか思っておりませんが、それは違います。 極小の五七五の定型詩の中では、言葉たちは、散文の中とは違って自由な不思議なふるまいをします。その自由な不思議なふるまいの意味をこそ、読者は読み取らねばなりません。〈重ね言葉〉も自由な不思議なふるまいの一つの現れです。 では、万緑の句を読んでみましょう。この句でいえば、「米」という言葉(文字)が二度くり返されます。一度目は「米屋が」、二度目は「米をとぎ」という形で。 まず一句は、「万緑の中や」と始まります。やによって強調された万緑は、その緑のいのちの輝きを全世界に及ぼします。その緑輝く世界あって、白いイメージを持つ米を冠した店、「米屋」が登場します。その「米屋」が「米をとぎ」と展開することによって、読者の中で米屋の「米」が米をとぎの「米」に重なります。そうすると、この「米」が普通の米ではなく何か特別の米のように感じられるのです。 読者の方で確信が持てない方は、くり返しこの句を読んでみてください。米屋の米が違う米に変化するはずです。米の米たることを発見すると言ってもかまいません。何か特別の米のように感じられたとき、この句は、一句として成り立ったことになります。 特別の米とは何か。私の読みを述べましょう。 それは、緑のいのち輝く中で、四方八方に白く光を発する米です。「米」の字を改めて見てください。四方八方に延びているでしょう。とぐことによってますます米の発する光は白さを増すのです。では、その白い光とは、なんでしょう。言うまでもありません。米のいのちです。名句です。
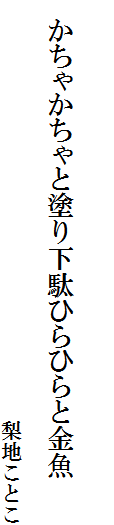
石畳にかちゃかちゃと涼しげな音が響きます。赤い塗り下駄の行く音です。なぜ赤いかっていえば、下に金魚とあるから。ここで、かちゃかちゃと行く塗り下駄とともに尾をひらひらとさせながら行く金魚を、下駄の鼻緒の絵柄と読んではつまりません。「かちゃかちゃと塗り下駄」と読むと同時に「塗り下駄ひらひらと金魚」とも読みます。赤い塗り下駄がかちゃかちゃと行く度に、赤い塗り下駄がひらひらと金魚に変身するのです。赤い塗り下駄を履いて行く女の人の優雅な歩き方が目に見えるようです。幻想的な美しい俳句です。 (梨地ことこ著『鏡ハシル』青磁社、2020年1月) 
死者の霊を迎える朱のほうずきの向うに文字通り情念の鬼灯(きとう)、鬼火が燃えています。
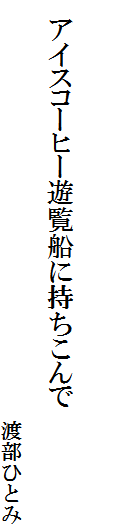
この句、じっと見つめていますと、「遊覧船」の前に置かれたカタカナの「アイスコーヒー」が、遊覧船の航跡のように見えてきませんか。この人は、遊覧船に持ち込んだアイスコーヒーを片手に、水尾(みお)を作って陸地から遠ざかっていく光景を船尾から眺めているのです。このゆったり感がここちよい素敵な句です。 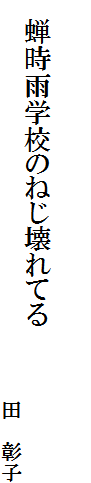
喧騒の蝉の声が、一切のものをかき消して、時雨となって降りそそいでいます。そこに生まれる静けさ、さびしさ、喧騒が失われた子どもたちのいない学校。そして、全てを固くつなぎとめるはずのねじは壊れ、冷たくあるだけです。すべてのものの崩壊の始まりを告げるかのような句です。田彰子句集『田さん』一番の句です。 (田彰子句集『田さん』ふらんす堂、2020年7月26日) 
秋の風が吹いてきた! ここはベトナム雑貨屋の二階だ。散文にすれば、たったこれだけです。たったこれだけのことが、なぜ、一句として成り立つのでしょうか。それは、まず、一階ではなく二階だからです。一階は地上であり、間違いなく現実世界ですが、二階はそうではありません。ベトナム雑貨屋というほかでもない異国の雑貨を商う店の二階は、秋の風に吹かれることによって一瞬、非現実の別の世界になるのです。
静誠司には、「二階」を使った句に、「マックの二階にたむろしている晩夏」もあります。これも味わい深い句です。 (静誠司句集『優しい人』ふらんす堂、2020年7月26日) 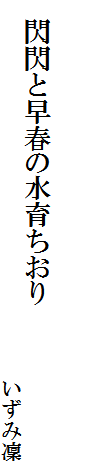
閃閃(せんせん)はきらきらと輝く様。これは、単に水が早春の光にきらきらと輝いて流れていることを言っているだけではありません。春を迎え、冬の間凍っていた水が融けてようやく流れ始めた水のいのちの輝きでもあります。なぜならば、下五に「水育ちおり」と書かれているからです。
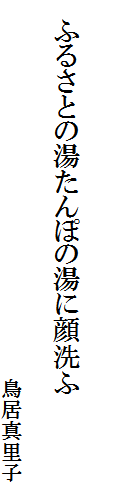 故郷というものは、優しく暖かいものです。そして、大きく人を包んで暮れます。この句は、そのことが美しく書かれています。 「ふるさと」とひらがなで書かれることで、故郷の優しさ、暖かさが表現されています。湯湯婆が「湯たんぽ」となっているのも、同じです。 この場合読み落してはならないのは、「湯で顔洗ふ」となっていないことです。「湯に顔洗ふ」となりますと、入れ子が完成します。湯の中に顔が入るニュアンスが出てくるからです。「に」によって、この句は、俳句になりました。 一句の世界の成り立ちを図で示せば、下のようになります。 石川啄木の次の歌と同じ、クローズアップの形になっています。 東海の小島の磯の白砂に 念のために申し添えます。この句は、ネット上でのような横書きで読める句ではありません! 横書きでは、大きなものから順に上から下へと包み込む、入れ子の構造が見え 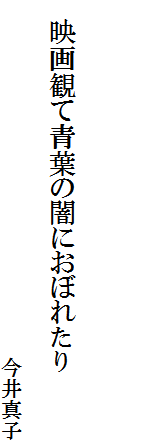 暗闇で人間の真の生き様を一瞬に見て、それを体験します。それが、映画です。外界とは時間のありようが違います。そして、映画の世界から一歩外界に出れば、当然、そこは、いつもと変わらぬ速度で時間が流れる、まばゆいばかりのいのち溢れる青葉の世界のはずです。しかし、瑞々しいいのちの発露であるはずの青葉は、その時、闇の光に満ちていました。この人の感情の全ては、何人とい えども避けては通ることのできないいのちの闇におぼれるほかなかったのです。 (今井真子句集『脱皮する月』黎明書房、2020年3月)
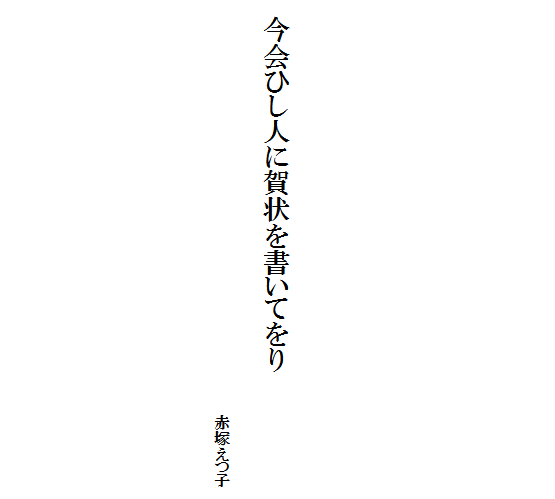
この句の眼目は、上五の「今会ひし人」の「今」です。この「今」が、一句全体に強く響き渡っています。別れの手を振れば、これが今生の別れかもしれません。これがこの世の習いです。誰も明日ことは分かりません。この、新しき年を迎えることを寿ぐ賀状を書いている時、もしくは賀状が着いた時、たった今会った人はこの世の人ではないかもしれません。さらに言えば、今会った人へ賀状を書いている自分自身にとっても、この世で書く最後の賀状になるかもしれないのです。新年を寿ぐことと裏腹の明日をも知れぬいのちについて書かれた、世の無常を考えさせる句です。
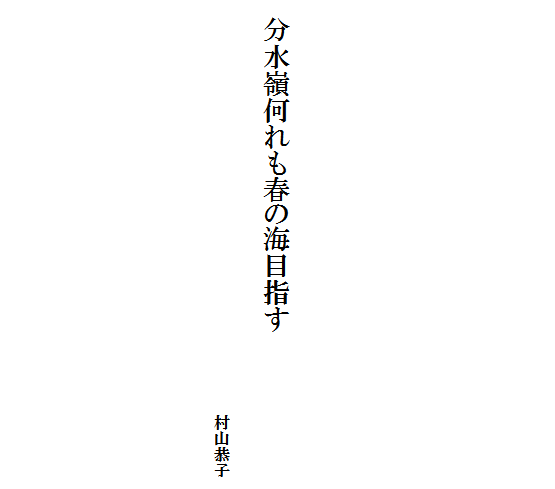
句の天辺に「分水嶺」が来るのは必然です。上にあるものは上に下にあるものは下にが、一行縦書きの俳句の原則だからです。「分水嶺」と読みますと、さっと左右に尾根が分かれる峰のイメージが浮かびます。そして、その尾根から左右に分かれ出た何れの水も、目指すものは、他でもない春の光にきらめく明るい海なのです。春は誰もが待ち望むものです。そして、大きく広がる海は誰もが持つ可能性の象徴です。
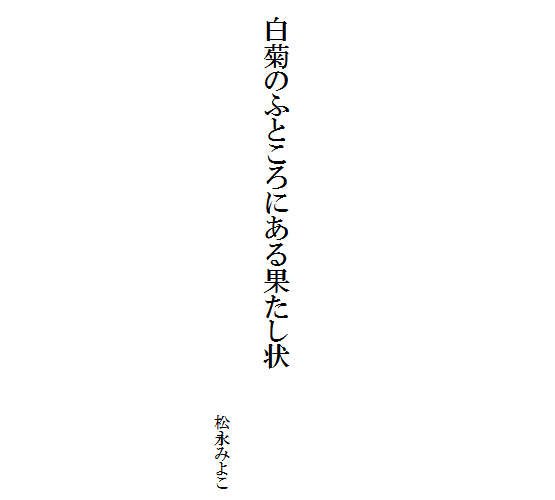
白菊と書かれますと、白一色に被われた菊の潔さをイメージします。その白菊のふところにあるものが果たし状なのです。白装束に身を固めた決死の姿が見えてきます。人が大いなるものに挑戦しようとする時の輝くばかりの美しさがここにあります。
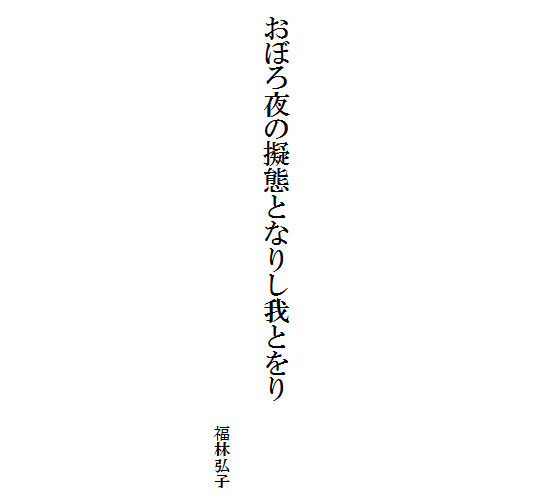
この句には、二人の自分が出てきます。一人は、おぼろ夜の擬態となった「我」です。もう一人は、おぼろ夜の擬態となった「我」と一緒にいる自分です。希薄化した、ぼーっとした存在を装って、おぼろな春の夜に紛れてしまった自分自身を、もの憂く見つめている人がここにいます。
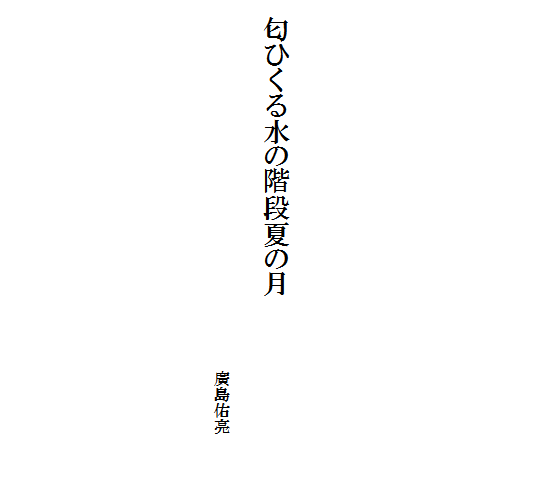
水の匂いがただよってくる。それは、水で出来た階段の匂いであった。水で出来た階段の一段一段には、夏の月が映っている。水に映った夏の月が、一段一段、涼しげにゆらめいているのである。(水に映った月だからこそ、一番下〔下五〕に来ている。)このゆらめく夏の月が演出する実体のない水の階段では、何かが演じられようとしている。果たしてどのような『真夏の夜の夢』がくり広げられるかは、読み手一人ひとりに任せられたこと。
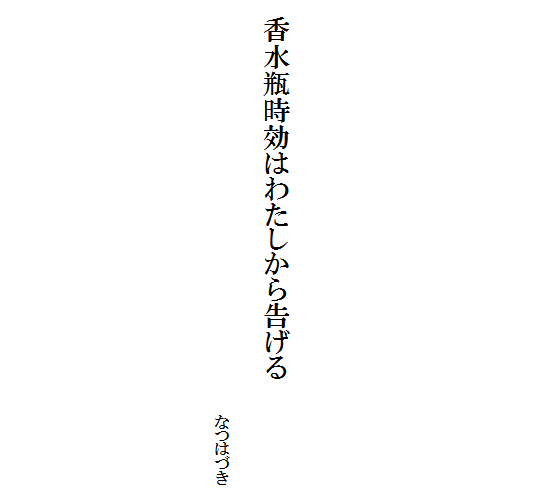
一段高い所に置かれた(上五にあります)香水瓶が、ある日突然、御託宣をのたもうたのです。「時効はわたしから告げる」と。「わたし」とは言うまでもなく香水瓶です。恋人と会う時にいつも肌にふりかけられ、彼女を
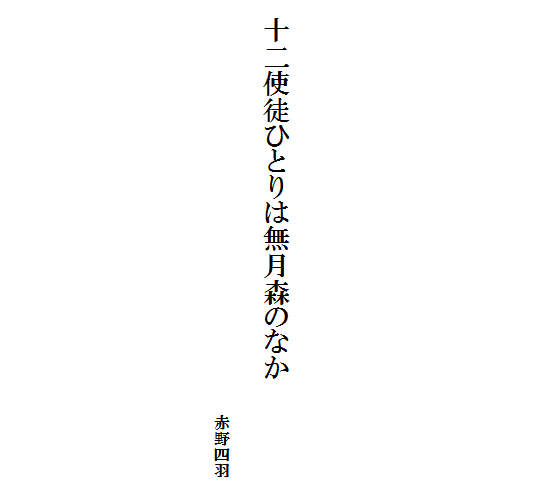
神の子イエス・キリストから後を託されたが故に十二使徒は尊いのです。天上に近き故に一番上(上五)に置かれます。そこから転落するものは周知の通りただ一人、イスカリオテのユダです。イエスを体制側に銀三十枚で売り渡した男です。だから、彼は、聖者のもつ光輪をもちません。作者は、それを季語の「無月」で表しました。そこに、新約聖書の世界を、季的世界に包摂しようという意志が見られます。光輪を頭部にもたず、無月を負う男は、下五の森の中に沈淪する外ないのです。
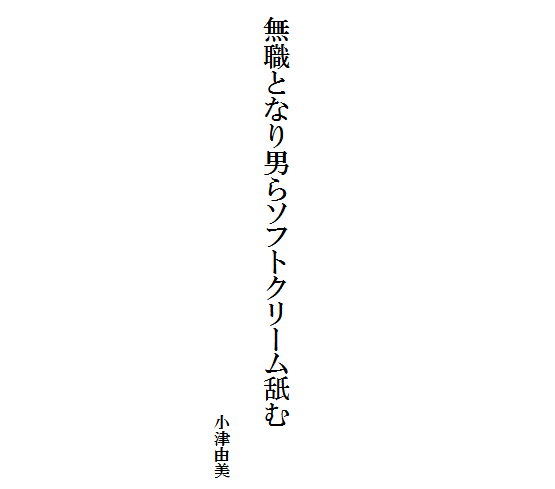
今は無職となって社会的分業から外された男たちのすることと言えば、あのそそり立つ高い山のような形でありながら、幻のようにはかなく溶けて行くソフトクリームを、棒立ちになってただ舐めるだけという、哀感漂う句です。その哀しさは、最後の「舐む」という官能的な言葉によって、我々にリアルに伝わってきます。また、幻のような「ソフトクリーム」と言うカタカナ表記も効果的です。 (第16回現代俳句東海大会作品。2019年10月27日) 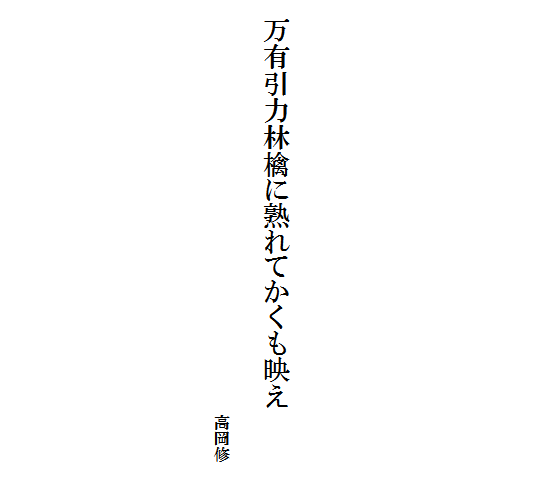
「に熟れて」という斬新な表現法に、心惹かれます。 万有引力というものが、今、林檎そのものとなり、真っ赤に熟れていることを、このように表されると思わず唸ってしまいます。 ここには、落下する林檎を万有引力で意味づけたニュートン=人類などいません。ニュートン=人類などがいないからこそ、林檎は、世界の中で燦燦と光を浴びその存在をこんなにも輝かせているのです。『剝製師』随一の句です。
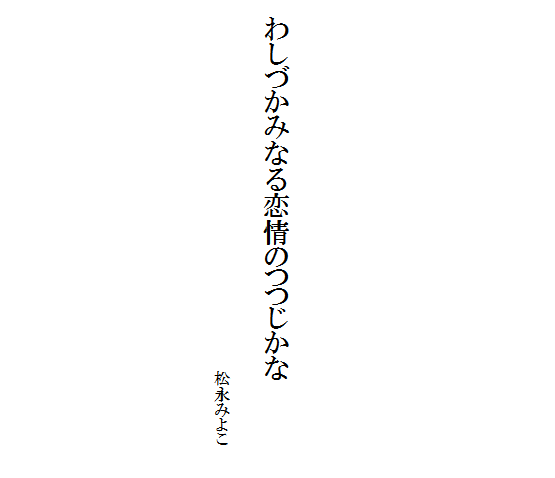
かたまって咲く紅蓮のつつじは、「恋情」そのものとしてありました。その恋情のつつじを、大きな手が、一挙にわしづかみにしたのです。内なる恋情をわしづかみにし、その恋情がこの世から消えてしまわないために。 (船団名古屋句会、2019年5月18日)
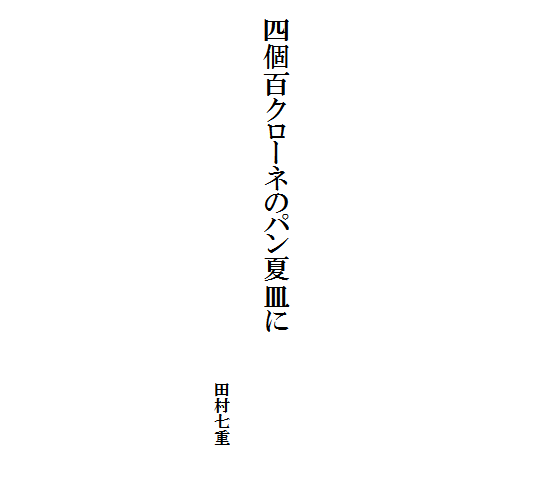
四個百クローネという具体的な物の値段を持つパンが、夏皿という不思議なものの上に置かれることによって、生活(俗)臭を脱し美(雅)の世界に昇華されています。 (船団松山句会、2019年6月8日)
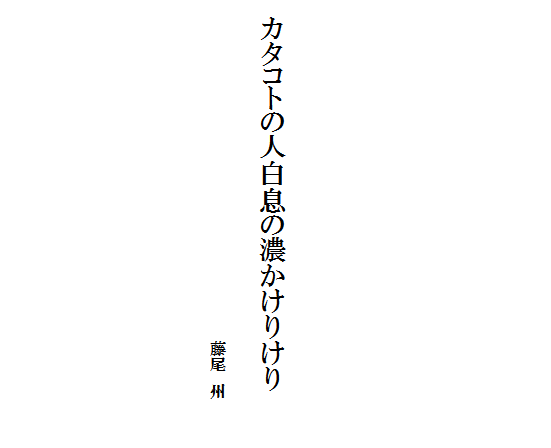
カタコトとカタカナで書かれているから外国の人でしょう。異国で懸命に生きる人だからこそ、厳しい寒さの中で吐く息の白さはひときわ濃いのです。
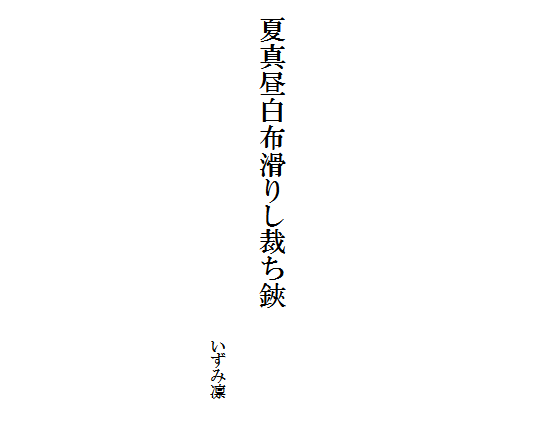
夏の真昼の眩むような明るい日差しの中、白布は光り輝いています。白布を切断する鋏は、白布を切断すると同時に、白布の発する白い光を滑るように切断して行きます。汚れなき白布を切断する鋏の動きが、快感として読む者の身体に伝わってくる官能的な句です。 (『ロマネコンティ』№193)
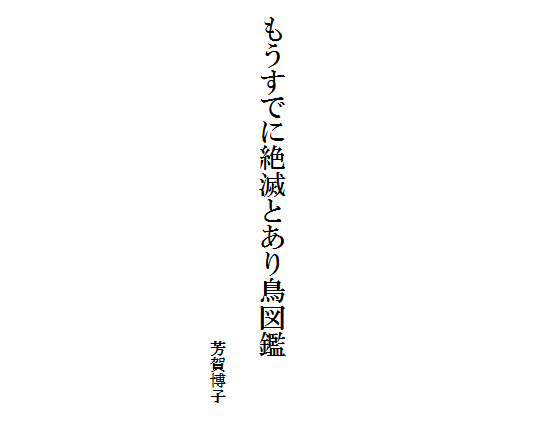
鳥図鑑には「すでに絶滅」とありました。 この句を読んだ人は、普通は、ある特定の鳥の種類のところにそう書いてあったと読むことでしょう。そして、「すでに一羽も生きていない鳥がいることへの感慨と、すでにこの世に一羽も生きていないにもかかわらずその鳥が図鑑にあることへの不思議さ、不条理さ」を感じることでしょう。だが、この句の面白さはそこに止まりません。もう一度読み直してみましょう。 そこには、絶滅した鳥が特定の鳥だけではないことが見えてきます。この句の「すでに絶滅」とは、鳥図鑑に書いてある言葉ですが、その言葉を読む人物の深い感慨が「もうすでに絶滅とあり」に示されています。そして、「絶滅とあり」と切れることによって、その深い感慨がさらに強調されます。 一旦切れることによって生れたさらに強調された深い感慨は、その切れをバネにして鳥図鑑そのものへと向かいます。そのことによって、鳥図鑑にある「すでに絶滅」は、特定の鳥ではなく、すべての鳥を指しているように思われてくるのです。絶滅した鳥類という類の図鑑である鳥図鑑がここに現われます。 特定の鳥たちが絶滅したと読むことから、全ての鳥が絶滅したと読むことへの転換と飛躍の面白さがこの句の命です。 中七・下五をひらがなで書けば、「 かくしてこの句は、一つの類の消滅を書いた句となり、句集『髷を切る』の中で一番面白い句となるのです。 (芳賀博子川柳句集『髷を切る』青磁社、2018年9月13日発行)
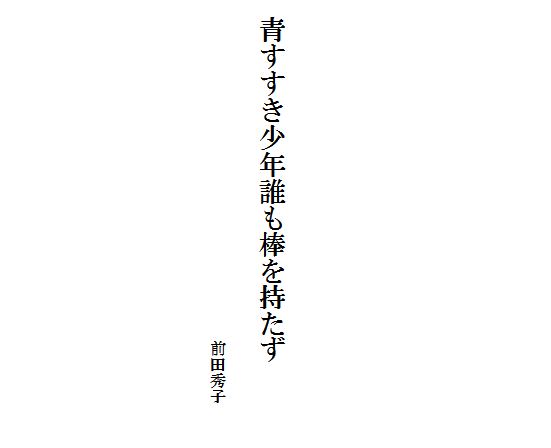
俳句と言う五七五の小さな定型詩の中では、言葉は通常とは違う不思議な振る舞いを見せます。 だから鑑賞する際、一字一句もおろそかにできません。 たとえばこの句です。この句の「青すすき」は、単に夏の野に青々と茂った芒ではありません。「青すすき」は「青」が漢字で書かれ、「すすき」はひらがなで書かれています。 この俳句と言う小さな詩形の中でこのように書かれますと、蛇笏の名句「をりとりてはらりとおもきすすきかな」を待つまでもなく、青々とした、荒々しい、若い命とともに、穂を白銀色に輝かせ、風になびかせるしなやかなすすきの美しい姿が現われます。この二つのイメージが重ねあわされて「青すすき」は現われます。 (2018年10月26日「鈴木しづ子 いのちの俳句大会」応募作品より)
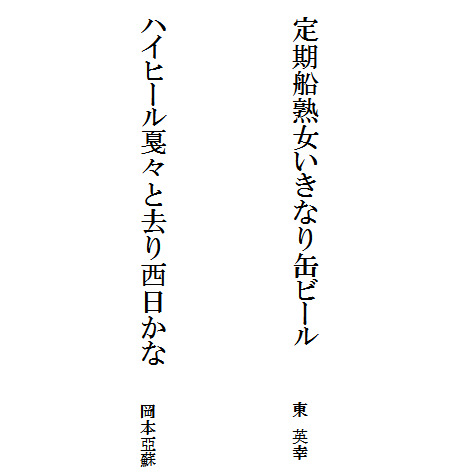
2句並ぶといいですねえ。
男は偶然乗り合わせた定期船で、熟女がいきなり缶ビールのプルトップを引き、ビールをぐびっと飲む光景に出会います。「おお、決まってる」と、熟女を見つめる男の驚きのまなざしが目に見えるようです。読者は思わず男のまなざしを借りて、熟女を見てしまうのです。さて、ところで、この定期船、ビールの熟女と男を乗せていったいどこへ行くのでしょうか。ひょっとして定期航路を外れて見知らぬ土地へと行ってしまうのではないかと気になってきます。
昭和12年、富沢赤黄男は日華事変に出征し、中支(華中)において 戞々とゆき戞々と征くばかり と書きました。戞々(戛々)は、前にこのように使われたことがありますが、ハイヒールが無表情に乾いた音を立てて去って行くのに、戛々という声喩を使ったのは、初めてではないでしょうか。 この句は、ハイヒールを履いた女性の姿をイメージすべきではありません。書かれたとおり、ハイヒールだけが、ハイヒールそのものが西日に照らされて戛々と去り、後には西日の照らす荒涼とした世界だけが残るというシュールな光景をイメージすべきでしょう。 戛々にある戈(ほこ)と言う字が、戦いを予感させる不穏な空気を漂わせます。
(『船団』第116号)
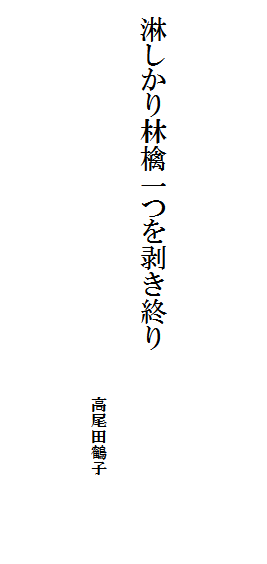
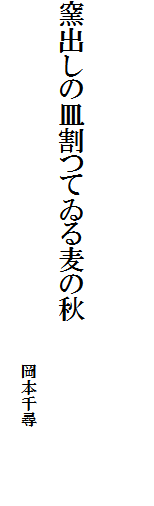
そして、この句においては、音を立てて割ったその破片が飛び散る様を、読者は不快感をもって受け取ることはない。 それはなぜか。 一つは、「麦の秋」から、黄に輝く美しい麦畑をイメージするためであるが、 もう一つ見落としてはいけないことがある。 それは、「麦の秋」という語が、「秋」という語を含んでいることである。「麦の秋」は、秋を面影としているのである。そのため、一句に爽やか感が生まれるのである。 それ故、長時間かけて焼いた末に、おびただしい作品を壊すという、本来悔しさに満ちた行為であるはずのも麦の秋の美と快感に身を投げ出すという行為へと転化するのである。 陶芸家の潔い生き方が、この句には書かれている。 単に麦にとっての実りと収穫の時だから、「麦」に「秋」がついているのだ、と単純に納得して読み過ごしてはならない。どんな言葉であろうと、常に新鮮な気持ちで、一語一語に接することが大切である。
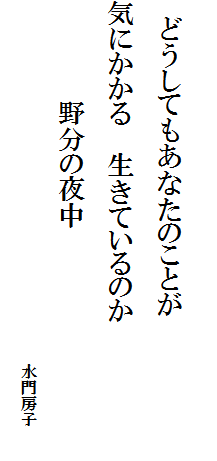 先の2月の船団ブックレビューで、水門房子歌集『いつも恋して』について、 恋する女の瞬間、350態(首)。例えば、「あと五秒/きっとあいつはkissをする/すこしまぶしい木もれ陽の中」。僕が悔やんだ一首。「じんじんとヒゲの感触/残ってる/ほんとの名前も知らないひとの」本名とは違う俳号にすればよかった! しかし、次の歌は気にかかる。「どうしてもあなたのことが/気にかかる 生きているのか/野分の夜中」 と書いた。書いたが、この歌、その後も気にかかることには変わりがない。それはなぜか自問してみた。 一首が、縦書き中央揃えになっているため、歌の中の人物が宙を踏んで歩いているかのごとき感じを読み手に与えることは確かだ。そして、これは一人で歩む道行の歌であることも身体的に伝わってくる。しかしながら、 どうしてもあなたのことが気にかかる生きているのか野分の夜中 と五七五七七定型に人物の意識は流されてはいない。意識は、流されることに抵抗している。それは、 どうしてもあなたのことが 気にかかる 生きているのか という形で、三行書きになっていることからも分かる。あなたが生きているのか、死んでいるのかその判断への葛藤を一首の形は抱え込んでいる。しかし、それだけでは、私が気にかかる理由にはなっていない。その答えは、一首を何度も口ずさむとき現われて来る界を結ぶ呪的な童歌であると思われる『かごめ』の一節が示唆している。 かごめかごめ かごのなかのとりは いついつでやる よあけのばんに つるとかめがすべった うしろのしょうめんだあれ 私には、この歌の三行目「野分の夜中」を読む時、この『かごめ』の「よあけのばんに」が、「野分の夜中」の面影となって現れるのである。そして、この矛盾した表現を持つ「よあけのばんに」を面影とする「野分の夜中」という表現に呪的な世界の不穏さを感じるのである。「野分の夜中」とは、この世ならぬ結界の外の世界なのだ。(従って「野分の夜中」は「のわけのよなか」と読む。「のわきのよなか」ではない。) かくして、一首は、結界の外へと野分の夜中を「あなた=男」を探しに一歩一歩宙をむが如く行く人物=女の歌であると結論づけることができる。 これで少しは気持ちが軽くなった。

何処へ行くのか太い航跡を残し巨大なタンカーは沖へ、大洋へと出て行く。今日は外でもない太平洋戦争の開戦日である。タンカーを見ている人物は、かつて、大洋の果てに出撃して行った巨大な艦船の像とそのタンカーを重ねあわせ、行きて帰らぬ多くの船と人のことを思うのである。 「航跡太き」の「太き」に、タンカーを見ている人物の、戦争に対する痛切な思いが表現されている。見送る船の航跡の「太き」が故に、却って滅びの哀れさ、悲しさを誘う一句となっている。

遠くの花火を女と並んで見ていた。遠くの花火に照らされて浮かび上がったものは、「横顔という岬」であった。女の横顔は、地の果つるところ、岬そのものであった。遠く離れてしまったその女の存在を、遅れてくる花火の音を聞きながら思うのである。


人生の終焉が間近いこの世界で、風に静かに身を任せる繊細な貴婦人のごとき風蘭の花の甘い甘い匂いほどの甘い情事に身を任せる幸せを詠う。風蘭(ふうらん)という官能的な言葉の響きが儚くも切ない。 ※『翼座』第9号、2016年1月

ネットで引かれる俳句は、ほぼ百%横書きである。これらはもともと縦書きで書かれ、発表された文学作品であるので、随分無理があるなあと思わずにおれない。縦書きの句を横書きにし、それを観賞しているのだから随分おかしなことだ。 
ソフトクリーム掲げてさびしさを告げる 池田澄子 これは、ニューヨーク港の自由の女神を面影にした一句である。 句中の人物は、自由の女神の姿に自らを重ね、黄色いコーンカップのアイスクリームを、たいまつよろしく高々と掲げたのである。自分を取り巻く世界に向って、自らのさびしさを告げるために。 ソフトクリームと言えば、見ての通りポップな陽気な食べ物である。陽気であるが故にさびしい人間の有様がこの一句に表現されている。
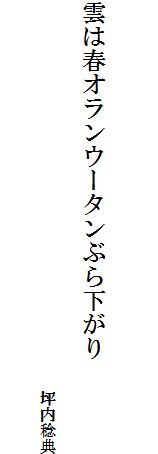
一句は、「雲は春」と、まず暖かな春の空にぽっかりと浮かんでいる雲を誉めます。同時に読者の視線を、空の上の雲に導きます。
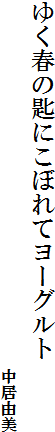
この素敵な句は、両掛かりの構造になっている。それが、一句に奥行きをもたらしている。 まず、普通は、「ゆく春の」で切って、「匙にこぼれてヨーグルト」と読もうとするであろう。しかし、これでは何のことか分からず、読み切れない。そこで、中七の「匙にこぼれて」を、上五の「ゆく春の」と下五の「ヨーグルト」の両方に掛けるのである。「ゆく春の匙にこぼれて」、「匙にこぼれてヨーグルト」と読むのである。
※2016年5月14日、船団松山句会にて。 ※両掛かりについては『ロマネコンティ』№141、2014年3月号掲載の拙稿

初め、「なつきたる」と読んでしまった。「かしゃかしゃ」「パイプ椅子」を運ぶのかと思ったわけである。しかし、おかしい。「か」が一つ余分だ。そこで、もう一度上から読み直す。今度は、「なつくるか」。「しゃかしゃか」。うまく行った。「しゃかしゃか」パイプ椅子を運ぶのだ。これが正しいはずだが、先に読んだ「かしゃかしゃ」も頭に残っている。そうだ、運ばれるパイプ椅子は「かしゃかしゃしゃかしゃか」嬉しそうに音を立てているのだ。いよいよ海辺に、戸外にパイプ椅子の活躍する、開放的な楽しい夏が来るのだ。夏の到来に寄せるうきうきした気分の充溢した一句である。
*『子規新報』第2巻第54号、2016年2月29日発行より転載。

十月、もっとも秋らしい爽やかな月。十月の子とは、その爽やかさを持って十月に生まれた子であろう。その十月生まれの子を地下鉄に乗せることによって、地上の秋とは無縁な地下鉄は、一転爽やかな空間へと変化する。そんな心地よい地下鉄に乗って、親子はわが家へと帰るのである。これが一般的な句意である。 しかし、ここで読者は、一句の中央のやや上に位置する「十月」という文字の鮮烈さに向き合わなくてはならない。重い歴史の数々をこの十月は背負っている。たとえ知らなくても、十月の子は生き続ける限りその歴史を背負わなくてはならないのだ。十月の子とは、爽やかさの中にも十字架を背負った一個の人間のことなのである。
*『子規新報』第2巻第53号、2015年12月20日発行より転載。
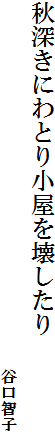
一句では、鶏小屋を壊した理由が書かれていない。何の意味もなく鶏小屋を壊したことになっている。
アンパンマンの神輿が通る秋の空 大西健司
恙なくリハビリ終わる秋日和 丹羽艶枝
などの秋は何ごとにおいても人を爽やかにする。それが、秋が深まると、一転不穏な空気が漂うことになる。先行句もそれを示している。
秋深き隣は何をするひとぞ 芭蕉
気にかゝる消息も又秋深し 稲畑汀子
この句において問題は切れである。芭蕉の句と同じく、「秋深き」で切れるが、「秋深きにわとり小屋」とも読めるので、上五の「秋深き」が、「秋深きにわとり小屋」へと掛かって行く読みの構造になっている。「秋深き」と今まさに噫秋が深まって行くことだと、世界の秋の深まりを読者にイメージさせ、さらにその世界にあってどこよりも「秋深きにわとり小屋」であることだと絞り込んで行くのである。そして、不穏の中の不穏の存在たる「にわとり小屋」を壊すのである。家畜であるといっても日々「にわとり」が生を営む場を壊す人物のさらに不穏であることよ。かくて深まる秋へと鶏鳴とともに「にわとり小屋」は世界から消滅する。ここまでである。
ちなみに、芭蕉の句も同じ構造になっている。「秋深き」は世界であると同時に「隣」でもある。深まり行く秋の中、不穏さがいよいよ漂う。「秋深き隣は何をするひとぞ」と、問わずにおれない作者である。
*谷口智子氏、大西健司氏、丹羽艶枝氏の句は、すべて第13回現代俳句東海大会(2015年11月29日)に投句された句である。

八月を詠んだ優れた句である。 著しい死者と共にある八月の町。生者は、黙祷をした後でなくては、八月の町に出ることはできないのだ。 無言の内に、霊を鎮め、自らの罪の許しを請い、誓いを立て自らを浄化した後に出た八月の町は、あくまでも広く、強い日差しを浴びて白く光り輝いている聖性を帯びた場であった。

この句の人物は、子どもは胎内にいるため、子どもを直接見ることはできない。母親のおなかを蹴っている光景を見て胎児の姿を見たのだ。それはまだ見ぬ子なのだが、その動いる様を見てそこに紛れもなく一個の意志有る生命を発見したのである。そして、その生命は直接月の光を浴びてはいない。浴びているのは母親である。しかし、人物は、しきりに動く胎児を見て、あたかも胎児自身が柔らかな春の月の光を浴び、その月の光によって生命を育まれているかのように感じたのである。春月を戴いているとは、外でもない、その子は、頭上に天からの優しさに満ちた大きな愛を戴いているということなのである。 ところで、この句は倒置法の句である。それゆえ、読み手は、一読、いわゆる正常な語順にもどって読もうとする意識が働く。「春月戴いて」と読んだ後、句の冒頭に戻って読もうとするのである。「春月戴いて/胎児しきりに動く」と。それの円環的繰り返しによって、春の月の光を、浴びては動き、動いては浴びるという光景が現われる。 (2015年7月16日)
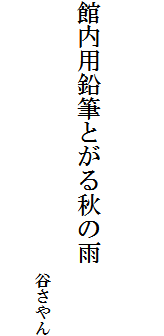
ある日の図書館のことであろうか、そこには来館者用鉛筆が置かれていた。しかし、その鉛筆は使われることもなく、削られたままに尖っていた。そんな館を包み込みように降る淋しい秋の雨。 そこまで読むと、一句はさびしい秋の雨の降る日、訪れる人もないがらんとした館内の、そのさびしさが凝って尖った鉛筆の先端の鋭さのみが読む者に迫ってくる光景となる。 そこには鉛筆を削った者など消え、ただ秋の雨に降り込められた大きな建物の中で館内用鉛筆の尖っている世界があるだけなのである。尖りとはさびしさそのものである。 「とがる」と平仮名になっているのは、もちろん漢字の多用される一句において「とがる」という言葉を際立たせるためであり、さびしさを演出するためのものである。 ※2013年8月24日、松山船団句会にて
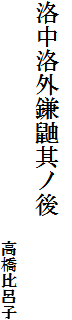
漢文調の一句は物語の一節を切り取って来たものである。散文中ならば引用符「」に括られるはずのものである。しかし、俳句定型と化した物語の一節は、物語から切り離され、それ自体で自立して一つの世界を作ることになる。では、肝心の物語とは、と問われると、答えに窮する。 一句は、高橋比呂子が書いたに違いない遠い昔の物語から、高橋比呂子が切り取ってきたものだからである。 だから、有体に言えば、一句は、物語の一節のように高橋比呂子によって書かれているのである。即ち、この句は、物語の一節を偽装しているのである。「其の後」ではなく「其ノ後」とあるのも、古の物語めいて奥ゆかしい。 では、一句の世界を読んでみよう。 一句の物語る世界は、当然ながら「洛中洛外」を舞台とする。「洛中洛外」とは「洛中洛外図」を引き合いに出すまでもなく、京=都の内外のことである。洛陽の洛から来た雅の地「洛中」と雅の風がまだ及ぶ「洛外」で「鎌鼬」が猖獗を極めたのである。 旋風とともに来る鎌鼬即ち冬の魔物の出没は、洛中洛外の荒廃、雅の衰退、動乱の冬の時代をイメージさせる。 その猖獗を極めた鎌鼬がある日を境にふっと消えた。「鎌鼬」の後の切れがそれをイメージさせる。切れの後の「其ノ後」とは、その「ある日」以後に新たに始まる物語のことだ。 だが、一句は「其ノ後」で終わり、その後は語らない。しかし、「其ノ後」に来る出来事への読者の関心は途切れない。では、いかなる事が「其ノ後」起こるのであろうか。「其の後」でなく、「其ノ後」という無機質な片仮名表記に厳し さが漂う。それ故「鎌鼬」の後に春の時代が訪れるとは思えない。 読者は予想するであろう。「鎌鼬」以上の厄災が「其ノ後」も繰り返し訪れるであろうことを。 高橋比呂子の筐底深くしまわれている「物語」には、それが書かれているはずである。 ※初出:武馬久仁裕「№127同人作品鑑賞・評」『ロマネコンティ』№129を一部訂正の上、転載。。
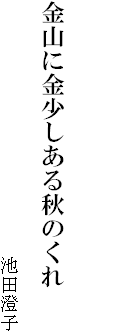 私の好きな透明感溢れる句である。 冒頭の「金山」に「金少し」と「金」が重ねられ、一句の「金」は更に輝きを増す。そして、その「金」が「少し」と書かれることによって「金」の純度が高まるのである。僅かであるがゆえに愈々輝きを増して、読む者の前に「金」は現れる。頃は「秋のくれ」。夜の気配がおとずれた澄み切った秋気の中に金色の光がきらきらと零れている。 秋には万物を形作る五行(木・火・土・金・水)の内の「金」が、配されている。「金秋」という。「秋」自体にも「金」は隠されているのだ。 なんと贅沢な句であろう。 同じ文字を一句の中で繰り返す技法は、この句が収められた『拝復』によく使われているが、「金山」の句は、特に見事である。 『拝復』からもう一句紹介しよう。 皿割れて絵の花割れて春のくれ 素晴らしいの一語である。 皿の割れる様に、さらに皿に画かれた色鮮やかな絵の花が割れて散る様が重なり、一句を前にしてしばし呆然とするのである。それがまた「春のくれ」である。※ 華やかさと儚さが同時に胸にせまり、美しい光景となっている。 さらに、さらにと紹介したくなるのだが、切りがないのでやめることにする。もっともっとうっとりしたい方は直接『拝復』を読まれんことを。
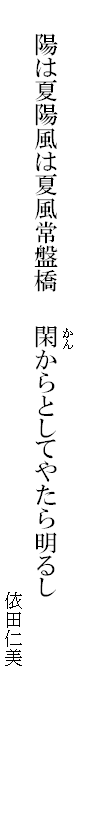
「陽は夏陽」。「陽」が二つ繰り返され、夏の日の強い陽ざしが強調される。昜昜(ようよう)と降りそそぐ夏の陽に次いで、「風は夏風」と「風」が二つ、風風と繰り返され、炎暑の中の涼風が引き出される。そして、風は川風となり、「常盤橋」が現れる。ここまでは此岸の世界である。 そして一字空きから、いきなり「閑からとしてやたら明るし」で、意味もなく空っぽのやたら明るくて仕様の無い、真夏の「常盤橋」界隈に一変する。何もかもがあるにはあるが、何処かへ行ってしまった、永遠の相を持つ世界、彼岸である。 「常盤橋」の「常盤」は「ときわ=とこしえ」である。それは同時に永遠の女性の名でもある。その名を冠する橋を、満腔の悲しみを内に秘めて、夏の空を仰ぎながら男は渡ろうとしているのだ。夏の強烈な日差しの中、彼岸の風を肩で切りながら。 *「大手町有情」より。(
しかし不思議なことに、この句には、地を擦って今まさに戻ってこようとする巻尺はあるが、巻き戻している人物はいないのだ。 確かに巻尺は「地を擦りて戻る」と書かれている。しかし、戻るところは書かれていない。この巻尺には戻るところがないのだ。 冬の重く垂れ込めた夕暮れの空の下、戻ってくるのだが戻るところはどこにもないという、この不条理な寒々とした光景が繰り広げられているのである。 そして、冬の夕暮に巻尺がたとえ戻るところがなくてもひたすら地を擦って戻るしかないという蕭条とした光景を、離れたところから見ている一人の人物がいる。 「地を擦りて戻る」と書かれた言葉が、その人物のなんともやるせない、冷え冷えとした心のありようを、見、声を出して読むという身体的行為を介して読者に引き起こす。確たる質感を持って。 それにしても、我々は、一体どこから来てどこへ行こうとしているのであろうか。薄暗い冬空の下、じっと佇むばかりである。 *2010年4月発行の『韻』4号、山本左門作「無月物語」より。
姉は全てにおいて一番の存在です。そして、妹たちには、眩しい存在です。その輝くばかりの姉が来て桃を剝きます。もちろん沢山の桃の中の一番きれいな桃を剥きます。そして、剥かれた桃からは、至高の美がこの世に現れるのです。見事な句です。
(中日総合俳句会8月例会。2024年8月11日) |
|